19年の時を経て:第20回IUBMB Congress回顧録
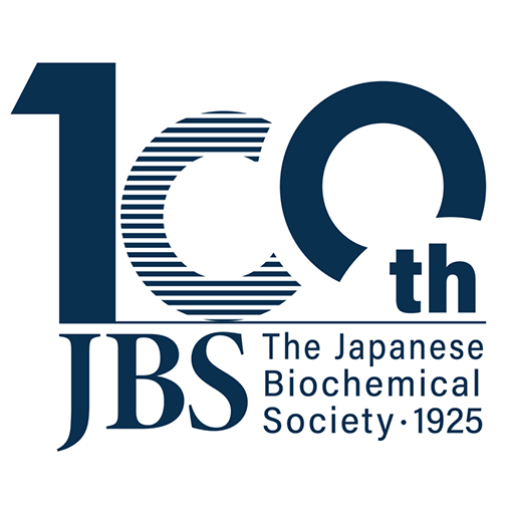

19年の時を経て:第20回IUBMB Congress回顧録
名誉会員 本庶 佑
第20回IUBMB Congress(国際生化学・分子生物学会議)から19年の歳月が流れた。当時は目の前に積み上がった山ほどの開催準備作業を一つずつ解決していくことで精一杯だったが、このたびの会誌「生化学」創刊100周年記念特別寄稿の依頼を受けたことをきっかけに、あの怒涛の日々を振り返ってみると、当時の記憶が鮮やかに蘇ってくる。あの経験は、私の研究者人生の中でも忘れられない瞬間の一つだったと、改めて実感している。
日本開催の決定と組織委員会の発足
1998年9月、安楽泰宏先生の先見的な発案により日本生化学会と日本分子生物学会の代表による準備委員会が発足し、私が委員長の大役を務めることとなった。翌年5月のサンフランシスコでの招請演説。緊張と期待が入り混じる中、39年ぶりの日本開催が正式に決定した瞬間の高揚感は、今も鮮明に心に刻まれている。
私の委員長としての方針は明確だった。日本の生化学者と分子生物学者の総力を結集し、学術的に最高水準の国際会議を実現すること、そして若手研究者の国際的な活躍の場を創出することだった。この理念に共感した優秀な組織委員の先生方とともに、2000年4月から実に20回もの委員会を重ねた。季節が移り変わるたびに、議論は深まり、構想は具体化していった。
財政基盤の確立と予想外の展開
国際会議の成否を左右する財政面では、興味深い出来事があった。新井賢一財務委員長が上代淑人先生を募金委員長に指名したのだ。師弟関係を超えた人事に一瞬戸惑ったが、上代先生は「若手の国際交流を支援する意義」を強調され、快諾してくださった。その熱意は多くの賛同者を生み、結果として目標の106%という驚異的な募金成果を実現していただいた。
一時は日本分子生物学会が2006年末に別フォーラムを開催すると決定したことで参加者減少が懸念された。しかし結果は杞憂に終わり、最終的に9477名もの参加者が京都に集結。財政的にも安定した大会運営が可能となり、学術プログラムの充実に全力を注ぐことができた。
学術プログラムと若手育成の実現
中西重忠プログラム委員長の卓越したリーダーシップのもと、真に学問的な質を重視したプログラム編成に取り組むことができた。国際学会ではしばしば政治的配慮が優先されがちだが、私たちは徹底して科学的価値を第一に考えた。その結果、世界トップクラスの研究者による講演が実現し、多くの参加者から「真の学問を中心にした稀有な国際会議だった」との評価をいただけたことは、最大の喜びであった。
若手研究者支援には特別な思い入れを持って取り組んだ。学生登録費を7000円(事前登録なら6000円)という破格の金額に設定するという決断は、一部より懸念の声を生んだが、結果として3216名もの学生会員が参加する活気に満ちた大会となった。特に印象深かったのは、ポスター会場の熱気だ。会場は議論に熱中する若者たちの声で溢れ、時間終了後も研究の未来について語り合う姿に、この会議の本当の成功を見た思いがした。仲野徹委員長が指揮したYoung Scientists' Programも100名の地域代表を集め、国際的な友情の種が蒔かれていった。
皇太子殿下のご臨席と忘れられない開会式

学会のちょうど10日前の2006年6月8日、緊張感の中で東宮御所を訪問し、当時の皇太子殿下(今上陛下)にご臨席をお願いする機会に恵まれた。格式ある空間での緊張は想像以上だったが、殿下は生命科学に対する深い造詣と温かい人柄で迎えてくださった。分子生物学の最新動向についての的確な質問に、殿下の学術への真摯な関心を感じた瞬間だった。
開会式当日、谷口直之総務委員長の緻密な調整により、厳重な警備の中にも温かい交流の場が生まれた。殿下が若手海外からの研究者と親しく言葉を交わされる姿に、多くの外国人研究者参加者が感銘を受け、日本への親近感を深めた。松田岩夫・小坂憲次両大臣や黒川清学術会議会長の流暢な英語でのスピーチも、国際舞台における日本の存在感を示す瞬間として、主催者として誇らしく感じた。
19年を経た今、科学の架け橋として
6年に及ぶ準備期間は、振り返れば一瞬のように過ぎ去った。株式会社コングレの小倉徳子顧問と西村郁子さんの献身的なサポート、内閣府学術会議の方々の緻密な調整力、そして京都府関係者の温かいおもてなしの心なしには、あの成功はなかっただろう。
今、19年の時を経て改めて思うのは、あの国際会議が単なる学術イベントではなく、日本の生命科学界における重要な転換点だったということだ。当時若手として参加した研究者たちは今や世界の第一線で活躍し、会議で結ばれた国際的な絆が今日の研究交流の礎となっている。
生化学会創刊100周年という節目に寄稿するにあたり、改めて実感するのは、科学の進歩が人と人との出会いから生まれるということだ。研究者としての人生において、これほど多くの人々と力を合わせ、一つの大きな目標を達成した経験は他にない。年月が経つにつれ、あの6年間の苦労と喜びの記憶はますます鮮明に、そして大切なものとして感じられるようになった。
あの国際会議に関わった全ての方々—組織委員、スタッフ、参加者、そして支援してくださった多くの団体に、改めて心からの感謝を捧げたい。そして次の世代が、私たちが感じたのと同じ情熱と使命感を持って、未来の国際交流を担ってくれることを願ってやまない。科学の言語は普遍であり、国境を超える。その架け橋を築く一助となれたことを、誇りに思う。
(京都大学大学院医学研究科附属がん免疫総合研究センター センター長、京都大学特別教授)
生化学会役職歴
- 1988年・1989年度 理事
- 1992年・1993年度 常務理事
- 1996年・1997年度 常務理事
- 2001年・2002年度 理事
- 2002年度 各種授賞等選考委員会委員長
- 2006年度 第79回日本生化学会大会会頭、第20回国際生化学・分子生物学会議会長


