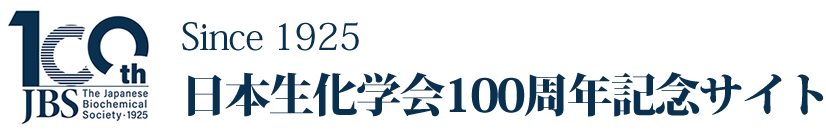ConBio2017第90回日本生化学会大会 生命科学系学会合同年次大会
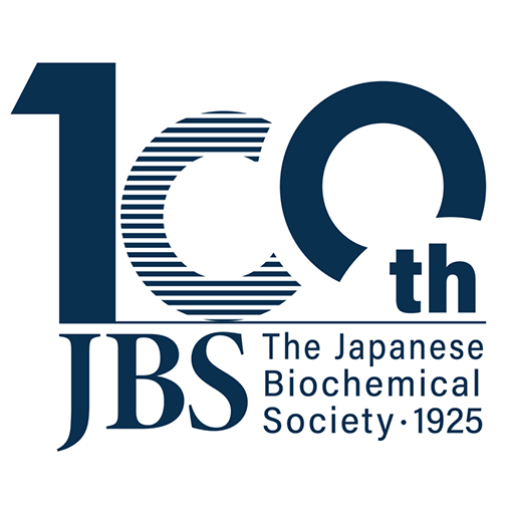

ConBio2017第90回日本生化学会大会 生命科学系学会合同年次大会
名誉会員 大野 茂男
日本生化学会に育てていただいた一研究者として、また第90回の大会会頭を務めさせていただいた者として、学会発足100周年を記念する企画に一文を寄せる機会をいただき、光栄の至りである。ここでは、第90回大会について、その経緯と問題意識、そして具体的な取り組みについて記したい。
学術分野の細分化と融合が急速に進んでいる現代の研究者の卵にとっての生化学会大会の意味
研究生活を始めた者にとって、年に一回の学会発表は、その後の研究生活にも関わる極めて貴重な機会である。私が大学院に入ったときには、それが生化学会であり、論文で名前を知っていた方から質問を受けたときの高揚感は今でも忘れない。いうまでもなく、現在その状況は大きく変わっている。学術の進歩に応じて様々な学会ができ、研究者たちは毎月のように学会、研究会、シンポジウムなどに参加して自身の役割を果たすことに汲々としている。学会は、学術誌の発行、学術集会の開催、基準・標準用語の策定などを通じて、学術分野の質を担保するツールとして機能してきたが、学術分野の細分化と融合が急速に進み、歴史的・質的な転換点を迎えている。このような中で、学会の存続、学会員数の増加が目的化してしまうという本末転倒の側面もある。
そのような中で、研究を始めた学生はどの学会に参加し、発表すべきなのか? 私が勧めていたのは、生化学会か分子生物学会である。学会参加の一つ目の目的は、自身の研究成果を発表し関連分野の研究者と直接議論することである。二つ目の目的は生命科学の様々な分野でどんな人がどんなことをやっているのか、その動向を知ることで、「予想もしていないこと」を発見することである。自身の研究成果を発表し関連分野の研究者と直接議論する場は、近年格段に増えており、その意味では、生化学会の存在意義は減じている。その一方で、自身のテーマとはかけ離れた分野に触れて、「予想もしていないこと」を発見する場としての意義は、ますます増えている。そして、細分化されすぎた学会単位ではない生化学会や分子生物学会のような大きな学会こそが、このような場を提供する役割がある。実際、生化学会と分子生物学会は、いずれも、上述した二つの目的を達成すべく趣向を凝らしてきた。ただ、二つの学会が独立に活動している意義は理解しがたい。私の周辺では、演題申し込みの締切が分子生物学会の方が3か月ほど遅いという理由で、多くが分子生物学会に発表していたと記憶している。
生化学会と分子生物学会を取り巻く社会環境の変化
そもそも、生化学会と分子生物学会とが独立に存在し、年に一回の大会(年会)を独立に開催するのは、我が国だけに見られる特異な現象である。我が国の人口規模と経済規模が、このような状況を許すギリギリのサイズを有している(いた)ことが一因だと思うが、人口規模や経済規模などの学術環境は大きく変化した。実際、2000年を境に生化学会の会員数は大きく減少に転じている(ピークの2000年はおよそ14,000人、2015年は8000人)。分子生物学会は、2005年までは会員数を増やしてきたが、それ以降は会員数が減少してきている(ピークの2005年は約16,000人、2015年は14,000人を割り込んでいた)。2004年の国立大学法人化、2008年のリーマンショックを経て、生物系の大学院進学率は、2010年には60%であったのが、2017年には40%に激減している。我が国の基礎科学を取り巻く社会状況は、大きく変化した。このような中で、これまでの状況を変える必要があることは明白である。
生化学会と分子生物学会の合同年会、そして生命科学系学会合同年次大会ConBio2017
理屈で考えれば単純な話でも、実際に異なった歴史を有する巨大学会が合同で大会を開催するのは簡単ではないことを歴史が示している。学会運営の基盤となっている学会会員の勧誘活動と密接に関連していることがその大きな原因である。つまり、合同大会は、必ずしも二つの学会の会員数の増加には結びつかないことがその理由である。そのような中で、二つの学会の年会を合同で開催する試みは、1996年第69回大会(大塚栄子会頭)に初めて行われている。その後、2006年第79回大会(本庶佑会頭)は第20回国際生化学・分子生物学会議として、続いて2007年(清水孝雄会頭)、2008年(大隅良典会頭)、2010年(田中啓二会頭)、2015年(遠藤斗志也会頭)が合同で開催されてきた。
合同開催のメリットの一つは、なにより学生にとってわかりやすいことである。そして、研究者を含む全てにとって悪いことではない。もう一つのメリットは、合理化により単独の学会ではできないことができる、ということである。2016年の夏頃に私が2017年第90回日本生化学会大会の会頭を引き受けたときに真っ先に行ったことは、分子生物学会の年会長予定者である篠原彰氏(大阪大学)との調整である。羽田空港のレストランで、何回も一緒に議論したことを思い出す。私たちは、上述した問題意識を完全に共有した。そして、両学会の大会(年会)の合同開催に加えて、他の基礎生命科学系の学会を含んだ新しい形の学会大会を模索することとした。結果として、2017年の第90回日本生化学会大会は、ConBio2017生命科学系学会合同年次大会として、第40回日本分子生物学会年会との合同大会として、更に、第26回アジア・オセアニア生化学者・分子生物学者連合カンファランス(FAOBMB, Federation of National Societies of Biochemistry and Molecular Biology in the Asian and Oceanian Region)との共同開催(これは生化学会の役割として決定していた)、そして37にのぼる基礎生命科学系(基礎医学系を含む)学会/団体の協賛からなる新しい形態の大会として開催された[2017年12月6日(水)~9日(土)(4日間)、会場:神戸ポートアイランド(神戸国際会議場、神戸ポートピアホテル、神戸国際展示場、神戸商工会議所)]。参加者10,201名、4,704演題にのぼる一般演題を含む大会となった(図1)。
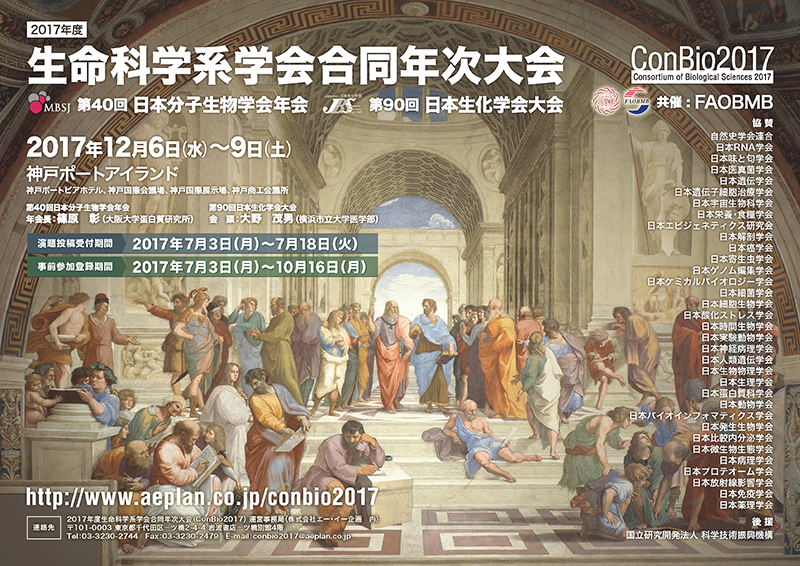
ConBio2017生命科学系学会合同年次大会のスケールメリットを生かした新しいとりくみ
ConBio2017生命科学系学会合同年次大会では、以下のセッションを行った。プレナリーレクチャー(10件)、シンポジウム(生化学会・分子生物学会の合同企画として10件、協賛学会の企画として23件)、ワークショップ(提案された160件の中から131件を採択)、フォーラム(20件)、一般口頭セッション(59件)、FAOBMBセッション(5件)、学会企画セッション(7件)を開催した。これに加えて、スケールメリットを生かした新しいとりくみを行った(詳細は、2017年会長便り6号:第90回日本生化学会大会 大野茂男会頭に聞くhttps://www.jbsoc.or.jp/letter-archive-mizushima/2017-6.html)。
合同年次大会のスケールメリットを生かした新しいとりくみとして、以下の三つを紹介したい。第一は、オンデマンド配信である。大きな大会ではいくつものシンポジウムが並走するため、聴きたい講演を聴けないことが起きる。また、自分の専門分野の講演は聴かざるをえないとすると、新しい発見のチャンスがなくなってしまう。そこで、一部の講演を録画して、大会終了後に一定期間オンデマンド配信することにした。視聴は大会参加者に限定し、誰が視聴したかもわかるような仕組みにした。講演する側にしても、誰が視聴したかという情報が得られるのは利点である(10のプレナリーレクチャー、23のシンポジウム、105のワークショップの講演を、オンデマンド配信)。
第二は、参加証にバーコードをつけたことである。学会の大会の運営は協賛企業の協力なしには不可能である。企業展示などで研究者情報を提供するのを迅速化効率化できる。研究者側にとっても手間をかけずに後でパンフレットを送ってもらったりできる。嫌ならバーコードをかざさなければよい。
取り組みの第三は、プレナリーレクチャー(10件)のコンテンツ化である。大会では歴史に残るような講演がたくさんあるが、残念ながらそのほとんどはその場限りで消えて無くなってしまう。それはあまりにもったいないことである。特にプレナリーレクチャーは、優れた教育コンテンツでもあり、人類の宝でもある。学会の責任でアーカイブ化し利用すべきである。今回のプレナリーレクチャーの講演者の方々にはあらかじめアーカイブ化についてこ説明しご了解を得ている。この貴重なコンテンツをどのように活用できるかどうかは、今後の学会の取り組みに委ねられている(プレナリーレクチャーのオンデマンド配信https://www.jbsoc.or.jp/notice/2018-03-01-2.html)。
(順天堂大学大学院医学研究科 特任教授、横浜市立大学名誉教授)
生化学会役職歴
- 2014年・2015年度 常務理事
- 2017年度 第90回日本生化学会大会会頭