私と日本生化学会
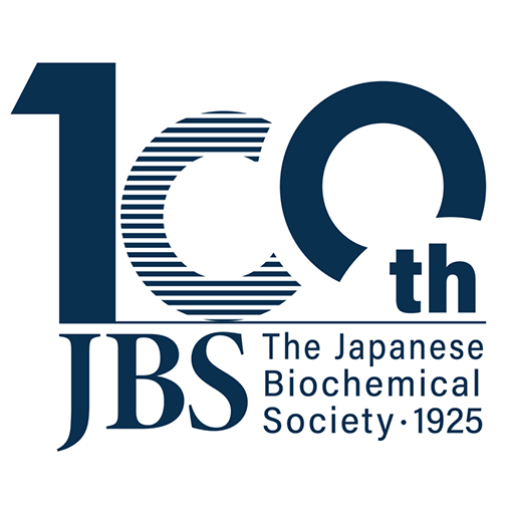

私と日本生化学会
名誉会員 大隅 良典
今の時代、生命科学分野で所属している学会が一つだけの人は稀であろう。私も、多い方ではないが、日本生化学会、分子生物学会、細胞生物学会、植物学会、植物生理学会などの会員である。しかしその中にあって、私にとって長年、生化学会が中心にあった。それは大学院時代を、今堀和友先生の研究室で酵素学を学び、スタッフの大島泰郎、鈴木紘一先生を始めとして生化学会を支えてこられた先生方々と身近に接してきたお陰に違いない。初めて助手として採用された東大理学部・植物学教室の研究室の主宰者、安楽泰宏先生もまた生化学会で長年活躍された方であり、研究室を上げて生化学会の大会に参加していた。
私の生化学会との出会いで個人的な思い出は、大学院生の時に、東大農学部で開催された関東支部会で話をさせていただいたことである。実はそれが初めての生化学会での発表の機会であった。当時取り組んでいたコリシンE3の作用機作について、まだそれほど話せるほどの成果があったとは言い難く、貧しい内容の発表であった。その時、別府輝彦先生、安楽先生から質問を頂いた。それが別府先生、安楽先生と初めて会話をした機会であった。その後、別府先生には、微生物学に関して度々教えをいただくことになった。また、米国留学でほとんど成果を上げることができずにいた私を、安楽先生に東大理学部・植物学教室の助手として採用していただくことになるとは夢にも思わなかった。学会が大事な出会いの機会であることを思い知ることとなった。
その後、生化学会の評議員などを務めることになり、2008年の会頭を仰せつかった。その年は分子生物学会との合同開催であり、分子生物学会の大会長は、長田重一氏であった。生化学会のプログラム幹事は貝淵弘三氏で、見事にその役を果たされた。Paul Nurse氏と岸本忠三先生が招待講演を務められた。しっかりした大会の組織委員会と経験を積んだ支援組織のおかげで、会頭として私がなすべきことは少なかったが、無事に大会を終えることができた。その前後の数年、分子生物学会と生化学会の合同開催の議論が盛んに行われていた。日本の生物科学を代表する二つの大きな学会である生化学会と分子生物学会の大会の開催時期が近接しており、会員の重複も多く、大会のシンポジウムの内容も重複しているなどがその理由であった。しかしその後この件は、結局実らなかった。生化学と分子生物学の交流は生命科学の研究の発展から必然的だと考えて、私は合同開催に積極的に賛成していた。各々の独自性を担保しながら、諸外国のような一つの大きなFederationがあるべきだと考えていた。今や分子生物学抜きに生命科学の研究が成り立たないと同時に、タンパク質、脂質を始めとする生体分子に関する構造、動態の情報もまた研究を進める上で必須になっている。解析技術が進歩を遂げ、構造生物学、とりわけタンパク質の構造情報が飛躍的に進歩した今こそ、生化学と、分子生物学を志す研究者が議論を進める場が重要になるに違いないと思っている。細胞を考えると糖、脂質、さらには多彩な小分子の理解には分子生物学だけでは解明できない沢山の課題が残されている。
半世紀にわたる私自身の研究を振り返って見ると、私は、その大半を出芽酵母を材料に研究を続けてきたが、その出発点が、酵母の強みである遺伝学的な解析をあえて避けて、やはり生化学にあったことに思い至る。私の大学院生時代は酵素の精製といえば、大量の材料から出発するのが当たり前であった。私自身も研究室で、5リットルのフラスコを沢山並べて大腸菌を培養したのを思い出す。KornbergのDNA polymeraseの精製が大量の大腸菌を用いて進められた例や、膨大な量の牛の臓器、眼などを集めたことなど、当時の研究の苦労話には枚挙にいとまがない。
東大理学部で始めた酵母の研究、液胞膜の機能の解析もまた、2機のジャーファーメンターを使って、60リットルの培養をする作業が必要であった。得られた菌体をスフェロプラストにして、温和な条件で細胞を破壊し、超遠心機を用いて純度の高い液胞を単離する作業が必須で、そうして純度の高い液胞膜が少量得られた。そのためには結構高価な培地(Yeast Extract、Peptone)、液胞を単離するために細胞壁を分解してスフェロプラストにするのに必要な酵素(zymolyase)、破砕液の浸透圧を保つためのソルビトール、液胞を単離する超遠心分離に必要なFicollなど、結構お金が掛かる材料と作業工程であった。それが可能であった環境に、今はただただ感謝の気持ちを抱くのみである。このように液胞の単離、物取りが研究の原点であり、それなくしては液胞膜のアミノ酸やCa2+等の能動輸送系や新規のプロトンポンプ、V-ATPaseの発見もなかったに違いない。
これらの研究には、大容量の培養のためのジャーファーメンター、大容量の遠心機、大型の超遠心機が必須であった。今では当時の生化学に用いられた様々な大きさのカラムなどの機器が、研究室の隅に追いやられ、時には廃棄の対象になっている。体力生化学といった言葉もあったのが懐かしい。今日の研究室では、わずか10ミリリットルの培養で解析し、大型フラスコで物取りをする時代とは隔世の感がある。新しい分析機器の開発により、解析の検出感度が劇的に向上したお陰に違いない。感度の点で格段に優れていたこともあって、ラジオアイソトープの使用が必須で液体シンチレーションカウンターも頻用されたが、それも今は限定的になり、実験施設が縮小されるなど、思いもよらない変化の一つである。僅かな試料で膨大な質量分析の結果が得られることも驚くべき進歩である。しかし愚直な作業を繰り返す以外に方法がないことがある。このような単純作業をいとわない姿勢が時には大切であることを今の若い世代に知ってほしいと思う。
私が生化学会について感じる思いは、その裾野の広さと多様性である。その主役であるタンパク質研究の進歩は、驚異的といわざるを得ない。この成果は分子生物学、遺伝子操作技術の進歩、DNA解析技術などに支えられてきた。質量分析技術の進歩もまた研究に革命的な変化をもたらした。タンパク質の結晶構造解析の数々の輝かしい成果もAlphaFold2の登場によって、まさしく新しい時代に突入した。さらに顕微鏡の進化、細胞の可視化技術の驚異的な進歩により、細胞内での分子の空間的情報、その経時的変化を捉えることができることとなった。
一方で生体の重要な構成成分である脂質、糖、それに小分子に関してはその多様性ということもあり、まだまだ新しい解析法の開発が待たれる、それが生化学の魅力に違いないと思う。
(国立大学法人東京科学大学総合研究院細胞制御工学研究センター栄誉教授、自然科学研究機構特別栄誉教授、総合研究大学院大学名誉教授、基礎生物学研究所名誉教授、東京大学特別栄誉教授)

写真の左から(敬称略):深見博一、大隅良典、高崎洋三、島田一郎、前田章夫、今堀和友、篠沢孝雄。
生化学会役職歴
- 2002年・2003年度 常務理事
- 2008年度 第81回日本生化学会大会会頭
- 2012年・2013年度 監事


