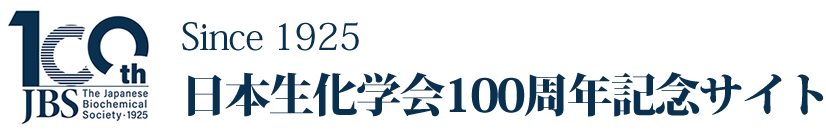生化学の創造的復興
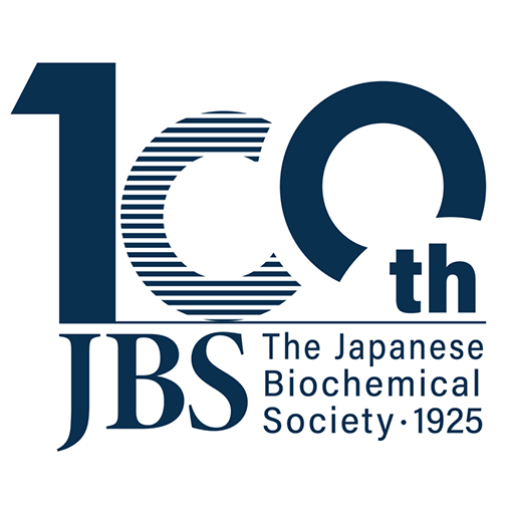

生化学の創造的復興
名誉会員 山本 雅之
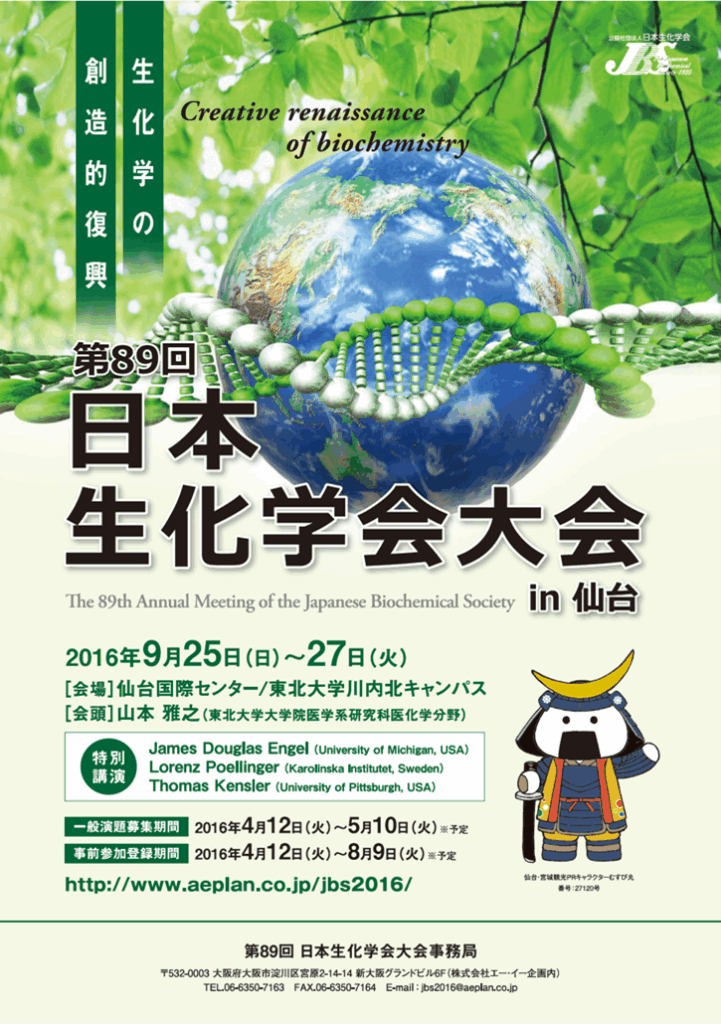
東日本大震災から5年という節目の年である2016年の9月25日より3日間、仙台で第89回日本生化学会大会を開催した。菊地吾郎先生が1981年に第54回大会を仙台で開催したときには、博士課程大学院生として、発表と準備・運営の両面で参加したが、それ以来、35年ぶりに私たち東北大学大学院医学系研究科の医化学分野が生化学会大会を主催することになり、昨今の学会運営事情の変化などに新鮮な驚きを感じながら、準備をした。また、仙台での開催も1995年の水野重樹会頭による第68回大会以来21年ぶりだったので、地方開催の魅力が感じられるような、手作り感のある大会運営を目指した。なお、同年4月14日に熊本地震が発生したため、被災地からの大会参加者を支援する取り組みも行った。
この第89回大会では、「生化学の創造的復興」をテーマに掲げた(図1)。「生物の環境応答」や「疾患の生化学」といった、古典的な研究テーマでありながら、近年大きな展開が見られる研究分野をクローズアップし、その発展を支える基盤となる生化学研究の重要性を再認識するとともに、「ビッグデータサイエンス」のような今日的なテーマへの取り組みもプログラムに大きく取り入れた。また、基礎科学を志す学生が少なくなってきている状況の中で、生化学研究をどうやって盛り上げていったら良いのか、ここにも大きな課題があると考えた。さらに、宮城県は東日本大震災からの復興フェーズにあったということもあり、これらを纏める意味で“創造的復興”をテーマとした。
特別講演として、Michigan大学のJames Douglas Engel教授とJohns Hopkins大学のThomas W. Kensler教授を招待した。両教授ともに、素晴らしい講演をしていただいた。Engel教授は、“Molecular Cloning”という遺伝子クローニングのバイブルのような教科書を書き、時代を切り開いたTom Maniatis教授の高弟であり、エンハンサーのルーピング仮説を実証した研究者なので、まさに生化学研究の歴史そのもののようなグロビン遺伝子研究の歴史と到達点について語っていただいた(図2)。また、Kensler教授は環境毒物・親電子性分子に対する生体応答メカニズム研究の第一人者である。20年以上にわたって中国上海近郊をフィールドに、アフラトキシンによる化学発がんとスルラファンによるその予防(化学発がん予防)の研究を展開してきている方であるが、本特別講演ではその壮大な研究について講演いただいた(図3)。たいへん残念なことに、本会名誉会員のKensler教授は、本年(2025年)8月に登山中の事故で急逝された。享年76歳であり、この場を借りてご冥福をお祈りしたい。


日本生化学会は、日本医学会を構成する団体でもあり、基礎医学系の中では最大規模の団体である。この大会では、日本医学会連合からご支援を頂くことができ、今回初めて、同じく日本医学会の構成団体である日本血液学会および日本糖尿病学会との共催シンポジウムを行った。このシンポジウムには、日本医学会連合の髙久史麿会長と清水孝雄副会長にご臨席いただき、挨拶を頂いた。また、活発な研究をされている高名な生化学会会員6名に、朝8時からのMeet the Expert講演をお引き受けいただいた。これは、最先端研究について、よりフランクに話をしてもらうことを狙ったものであり、参加者が間近で聴講し、交流を図れることを期待した企画であったが、たいへん好評であった。なお、企画シンポジウムは、なるべく裾野を広くしようということで、JST事業のCREST(戦略的創造研究推進事業)や文科省事業の新学術領域研究などとの共催シンポジウムを多数用意した。エピゲノムやオートファジー、酸素生物学、実験動物、ケミカルバイオロジー、創薬プラットフォーム、慢性炎症などをテーマにしたものがあり、生化学研究が様々な学術の基盤を支えていることを実感していただけたと思う。
私は医学部を卒業後、生化学の研究をするために直接大学院博士課程に進学し、その年(1979年)に日本生化学会に入会して、その後、長く本会で活動をしてきた。大学院2年次から生化学会大会に演題を出し始めたが、その頃はスライドを映写しながらの短い時間での口頭発表が多かったので、手作りのスライドを使って映写機で映しながら何度も練習をしたことが懐かしく思い出される。
前述のように、大学院在学中に、指導教授である菊地吾郎教授が会頭を務められて、第54回生化学会大会が東北大学教養部を利用して仙台で開催された。その頃と比べると、生化学会大会の運営はすっかり様変わりしている。なにより、現在では大きな会場を借り切って、専門性の高い学会支援企業の助けを借りて実施するケースが圧倒的である。実際にこの大会も、仙台国際センターをメイン会場に実施したが、地方都市の開催ということもあり、また、私が大学院学生だった頃の手作り感も醸し出したくて、さらに、経費の節約も狙って、東北大学川内キャンパスの教室を一部拝借して第2会場とした。ちょうど前年12月に、仙台市営地下鉄東西線が開通して、仙台駅から両会場までのアクセスもたいへん便利になったこと、また、国際センター駅から川内駅までは1駅で、地下鉄がシャトルバスの役割を果たしてくれたことは、大会の運営を大きく助けてくれた。両会場は徒歩圏内であり、また、近くに仙台市博物館や宮城県美術館があるので、参加会員の方々には、大会とあわせて仙台の文化も楽しんでいただけたのではないだろうか。
大会の開始に先立ち、前日9月24日には、日本宇宙航空研究開発機構(JAXA)の協力を得て、市民公開講座「復興からきぼうへ~震災と科学、そして宇宙へ」を開催し、249名の参加をいただいた。市民講座の第1部では、「震災復興と生化学」をテーマに、津波で大きな被害を受けた気仙沼地域の復興について、また、医療面からの震災復興について取り上げ、気仙沼在住のフリーアナウンサー岩手佳代子さんと私が、宮城県の様々な地域の人々や東北大学が震災からの復興に向けて、どのような活動してきたのかをお伝えした。第2部は、「復興からきぼうへ~宇宙がつくる生化学」をテーマに、国際宇宙ステーションに長期滞在した星出彰彦宇宙飛行士に、宇宙での生活や国際宇宙ステーション(ISS)が落ちない仕組みについて講演していただき、また、ISSの動く速度を体感できる動画を放映していただいた。さらに、JAXA研究者から、将来人類が宇宙に滞在するための研究や宇宙環境が生物に与える影響についての講演をいただいた。
私たちの研究チームは、2015年にJAXA宇宙マウス実験公募に応募し、幸い採択された。2018年にISSにNrf2遺伝子欠失マウスと野生型マウス計12匹を送り、1か月の宇宙滞在後、全頭無事に地上に帰還させた。これはまさに、宇宙マウスの時代、“Decade of Space Mouse”、の幕開けとなる実験であり、宇宙ストレスの防御にKEAP1-NRF2制御系が重要であることを実証した実験であるが、この市民公開講座はまさにその端緒となるものであった。
大会終了後の9月29日には、「東北から発信!個別化医療の実現にむけて」ミニセミナーと東北メディカル・メガバンク機構(ToMMo)の施設見学ツアーを実施した。ToMMoは2011年3月に発生した東日本大震災の被害から地域医療の復興と、大規模情報化に対応した新たな医療の構築のために、2012年に東北大学に設立した大規模バイオバンクである。2016年秋には、目標としていた15万人を上回る方々に参加登録いただき、その中の2000名を超える方々の全ゲノム解析を修了した。この頃は、1人の全ゲノムを解析するために長い時間と多くの費用を要したが、その後の技術革新があり、2024年には10万人の全ゲノム解析を達成して、世界の大規模ゲノムコホート・バイオバンクの一つに数えられるまで成長したことには特別の感慨を覚える。
なお、ToMMoの成果の一つとして、全ゲノム解析結果に基づく遺伝性乳がん卵巣がん症候群(HBOC)とリンチ症候群(LS)の遺伝的リスクを一般住民に回付するパイロット研究に成功したことがある。ToMMoは2024年に、これらの遺伝性がん発症の高いリスクの保有者111名に対して、遺伝的リスク解析結果を回付したが、そのうち78名がすぐに大規模医療機関を受診し、6名がリスク低減手術を受け、3名には無症状段階の早期がんが発見された。米国では、2013年に女優アンジェリーナ・ジョリーさんが、BRCA1遺伝子変異の保有と、乳房と卵巣の予防摘出手術を受けたことを公表して、大きな話題となった。一般住民を対象として、大規模にゲノム解析結果の回付を実施したのは日本では初めてである。これは、生化学研究を基盤とする遺伝性がんのリスク予測が、コホート調査に参加した一般住民の方々に還元された、極めて先駆的な個別化予防・医療につながる取り組みであり、生化学を基盤とするビッグデータ解析が社会に貢献していることが実感される。
ToMMo設立から13年が経過したが、この間の生化学の発展とともにToMMoのバイオバンク事業も発展してきた。設立当初は、ToMMoの趣旨を理解していただくことはたいへんであったが、今では多くの住民や研究者がバイオバンクの重要性を理解され、また、バイオバンクを利用する研究者も増えている。ToMMoは、より高度で使いやすいバイオバンクを目指し、引き続き努力をして行く所存である。研究や事業の達成面では課題はたくさんあるが、新しいことに挑戦できることは大きな喜びであり、挑戦し続けられること、新しい文化の創造に立ち会えることに感謝している。
最後に、第89回日本生化学会大会の準備や運営には、運営委員会のメンバー、日本生化学会事務局の皆様をはじめ、多くの方々の献身的なご助力を頂いた(図4)。深甚の感謝を申し上げる。
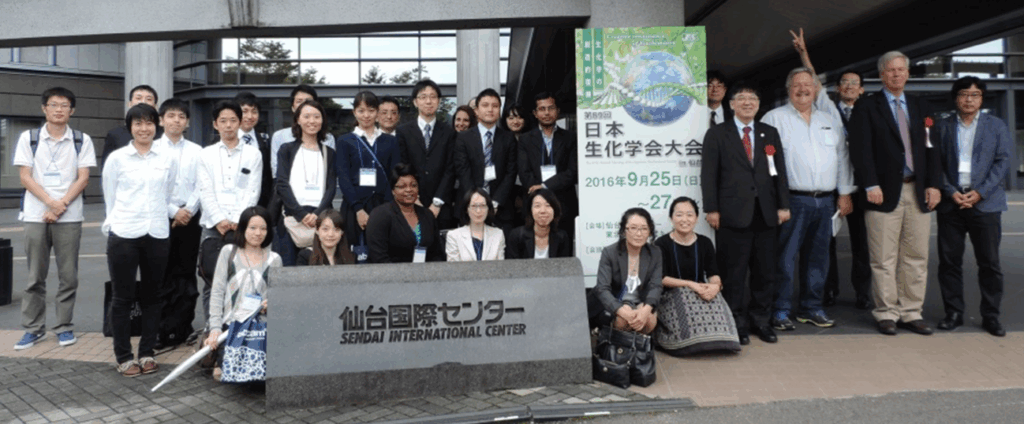
(東北大学東北メディカル・メガバンク機構 機構長)
生化学会役職歴
- 2006年・2007年度 理事
- 2012年・2013年度 副会長
- 2013年度 支部長
- 2014・2015年度 常務理事
- 2014・2015年度 支部長
- 2016年度 第89回日本生化学会大会会頭
- 2018・2019年度 会長
- 2020・2021年度 監事