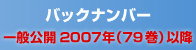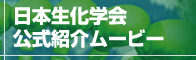** 日本学術会議ニュース ** No.935**
===================================================================
1.【開催案内】
日本学術会議主催学術フォーラム「米国科学技術政策の転換、その影響を考える」
2.【開催案内】
日本学術会議主催学術フォーラム「多層多軸連関で捉えて対策する心血管
・腎・代謝症候群」
3.【開催案内】
公開シンポジウム「地球的課題解決のための資質・能力を育成する地理教育
―小学校・中学校・高等学校までの一貫カリキュラムに向けて―」
■——————————————————————–
1.【開催案内】
日本学術会議主催学術フォーラム「米国科学技術政策の転換、その影響を考える」
——————————————————————–■
・日時:令和7年10月5日(日)13:00 ~ 17:00
・場所:日本学術会議講堂(ハイブリッド開催)
・主催:日本学術会議
後援:生物科学学会連合、日本宗教研究諸学会連合、日本地球惑星科学連合、
日本哲学系諸学会連合、科学技術社会論学会、日本天文学会、
日本物理学会、日本学術振興会, 国立研究開発法人科学技術振興機構、
宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所、高エネルギー加速器研究機構、
国立環境研究所、自然科学研究機構国立天文台
・開催趣旨:
米国の科学技術・学術政策は今年に入って大きく変動しています。環境政策、
保健衛生政策の変更に伴い、米国海洋大気庁(NOAA)などでのデータ配信の停
止や、米国衛生研究所(NIH)における研究の縮減、ファンディングの凍結が行
われました。アメリカ航空宇宙局(NASA), 米国国立科学財団(NSF)などで
の基礎研究予算の大幅なカットが政府から提案され、議会において審議が行われ
ています。人材育成支援や、海外の研究者の受け入れに消極的な方針が示され、
研究者の米国外への移動が今後本格化するかもしれません。
このような米国の政策の変化は、なせ起こり、我々はそこから何を学ぶことが
できるでしょうか。日本をはじめ世界の科学研究、さらに環境、安全にどのよう
な変化が起こるでしょうか。本シンポジウムでは、米国の科学技術政策のこれま
でを俯瞰した上で、日本と世界の科学技術・学術研究が受けるインパクトを洞察し、
日本の研究が備えるべき視点を考察します
・次第:https://www.scj.go.jp/ja/event/2025/386-s-1005.html
・参加費:無料
・要・事前申し込み:以下のURLからお申し込みください。
https://form.cao.go.jp/scj/opinion-0330.html
・問合せ先:
日本学術会議事務局企画課学術フォーラム担当 電話:03-3403-6295
■——————————————————————–
2.【開催案内】
日本学術会議主催学術フォーラム「多層多軸連関で捉えて対策する心血管
・腎・代謝症候群」
——————————————————————–■
・日時:令和7年9月13日(土)13:00 ~ 17:00
・場所:オンライン開催
・主催:日本学術会議
・開催趣旨:
代謝異常を基盤とする生活習慣病、慢性腎臓病、そして心血管病は、疾患と
しての連続性を有し、その根底に共通する病態、さらには治療・管理における
多臓器連関の重要性を反映し、心血管・腎・代謝症候群(Cardiovascular-Kidney
-Metabolic Syndrome)という包括的な概念のもとで捉えられるようになりつつ
ある。この概念は近年、急速に広まり、医学のみならず広範な領域において注目
を集めている。心血管・腎・代謝症候群(Cardiovascular-Kidney-MetabolicSyndrome)
を論じるにあたっては、単に個々の疾患を検討するに留まらず、多臓器が相互に
関連し合う複雑な機序、若年期から老年期に至る長いライフステージにわたる管理、
そして医療・福祉・公衆衛生の分野を超えて関わる多様な専門職種の役割を踏まえ、
多層的かつ多軸的な視点から議論を展開することが不可欠である。本フォーラム
においては、心血管・腎・代謝症候群(Cardiovascular-Kidney-Metabolic Syndrome)
の現状と未来を見据え、医学の専門家のみならず、産業界、行政、さらには社会学の
分野において第一線で活躍する識者を招聘し、学際的かつ実践的な議論を深めていく。
・次第:https://www.scj.go.jp/ja/event/2025/382-s-0913.html
・参加費:無料
・要・事前申し込み:以下のURLからお申し込みください。
https://form.cao.go.jp/scj/opinion-0323.html
・問合せ先:
日本学術会議事務局企画課学術フォーラム担当 電話:03-3403-6295
■——————————————————————–
3.【開催案内】
公開シンポジウム「地球的課題解決のための資質・能力を育成する地理教育
―小学校・中学校・高等学校までの一貫カリキュラムに向けて―」
——————————————————————–■
【主催】日本学術会議地域研究委員会・地球惑星科学委員会合同地理教育・ESD分科会、
公益社団法人日本地理学会地理教育専門委員会
【後援】地理学連携機構
【日時】令和7年(2025年)9月21日(日)9:00 ~ 12:00
【場所】弘前大学(青森県弘前市文京町一番地)日本地理学会秋季学術大会第1会場
【参加費】無料
【定員】100名程度
【事前申込み】
参加費無料・事前申込必要なしなので当日お越しください。ただし、公開シン
ポジウム以外の日本地理学会学術大会のプログラムに参加される場合は参加費
が必要となります。
【開催趣旨】
グローバル化や環境変化が急速に進む現代、地球的課題解決のための資質・
能力のさらなる充実は、世界共通の喫緊の課題である。学習指導要領では、思
考力・判断力・表現力といった資質・能力が特に重視され、学習指導要領解説
では、国際連合における持続可能な開発のための取り組みを参考に、生徒自身
が地球的視野で考え、様々な課題を自らの課題として捉え、身近なところから
取組み、持続可能な社会づくりの担い手となることにつながる教育をもとめて
いる。このような教育は、ESD(Education for Sustainable Development)、
つまりは持続可能な社会の創り手を育む教育といえ、学習指導要領でもESDが
求められているといえる。一方で、小学校から高等学校まで各教科等で段階的
に持続可能な社会づくりの能力を育成することが重要であるものの、効果的に
行われているとはいえず、学習指導要領などでも小学校から高等学校までの一
貫した持続可能な社会づくりの方略について示されていない。
そこで、こうした持続可能な社会づくりの能力の育成をめざすために、地理
教育において必要な教育内容を小・中・高までの一貫したカリキュラムを念頭
にして討論する。なお、本シンポジウムは、令和7年7月24日に開催された日
本学術会議地域研究委員会・地球惑星科学委員会合同地理教育・ESD分科会で
の環境学委員会環境思想・環境教育分科会委員長、ユネスコ国内委員会委員、
ESD学会の役員、国際理解教育の専門家を招いて議論した内容を踏まえての報
告となると同時に、意思の表出の内容を議論することも兼ねている。
【プログラム】https://www.scj.go.jp/ja/event/2025/387-s-0921.html
【問い合わせ先】
広島大学 由井義通
メールアドレス: yyui(a)hiroshima-u.ac.jp ※(a)を@にしてお送りください.
———————————————————————–
***********************************************************************
日本学術会議YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCV49_ycWmnfhNV2jgePY4Cw
日本学術会議公式X
***********************************************************************
***********************************************************************
学術情報誌『学術の動向』最新号はこちらから
***********************************************************************