Our homepage has been revamped.
Our homepage has been revamped.
Our homepage has been revamped.
JB編集委員長 菊池 章(大阪大学大学院医学系研究科)
私は、2014年からJournal of Biochemistry (JB;http://jb.oxfordjournals.org/)の編集委員長を務めます。JBの現状につきまして、生化学会会員の皆様に紹介させていただきます。JBは柿内三郎先生が東京帝国大学医科大学医化学講座教授に就任されてから、我が国の研究業績を世界の学界に発表する必要性を痛感され、「外字生化学雑誌」を個人で刊行されたことに端を発します(生化学 63, 1087‐1131,1991)。第1巻1号は1922年に創刊され、1945~1949年に第二次世界大戦の影響により一時休刊になったことはありますが、今日まで日本生化学会の英文機関誌として、我が国の研究を世界に発表する場となってきました。創刊の年は日本生化学会発足(1925年)よりも早く、我が国の最も古い英文学術論文誌の一つです。JBでは、伝統的な生化学領域に加えて、分子生物学、細胞生物学、バイオテクノロジーに関する幅広い生命科学領域の論文を掲載しています。
最近の4年間では年間300~400編のOriginal articlesの投稿があり、70~100編が採択されていますが、傾向としまして海外、特に中国、インド、韓国からの投稿が増加し、全投稿数の約半数は海外からのものになっています。論文投稿から最初の判定まで平均20日以内というスピードで査読が行われています。
生化学会の個人会員の皆様は、創刊号より無料で全文をダウンロードすることができます。そのためのUser NameとPasswordをご存じでない方は、JB編集部までメール (jb-jbs@jbsoc.or.jp) でお問い合わせ願います。会員以外の方々につきましても、出版社(OxfordUniversityPress)のご好意により、JBの優れた論文を読んでいただくために、毎月2編の論文をFeatured article として無料で配信しています。さらに、iPhoneやiPad、アンドロイド等のモバイル機器からも簡単にアクセスできるウエッブサイトも用意していますので、是非お気軽にJBをご覧になっていただきたいと思います。
レイアウト・表紙
インターネットを用いてのPC上で論文を読む機会が増えていますので、パソコンの画面でも読みやすいレイアウトを目指しています。前編集委員長の宮園浩平先生のご尽力により、表紙が大変美しくなりました。「Nature in Japan」では、日本の四季折々の美しい花々の写真を表紙としています。「Discovery in Japan」では、我が国の素晴らしい研究成果を表紙として掲載しています。掲載論文の中から表紙に相応しいFiguresがあれば、表紙として採用させていただくことも考えています。
JBのページとJB論文賞
会誌「生化学」では毎号(2014年からは隔月発刊となります)JBのページに論文ダイジェス卜が和文で掲載されていますのでご活用ください。また、JBに掲載された論文の中から、毎年JB論文賞が選出されており、2013年は10編の論文が選ばれました。選出された論文は日本生化学会大会会場で授賞式が行われるとともに、受賞論文1編につき、賞状と賞金(10万円)が贈呈されます。
Rapid communication
JBが掲載するOriginal articlesには、RegularpapersのほかにRapid communicationsがあります。Rapidcommunicationsにはインパクトが高く、速報性を要する論文を取り上げることになっていますが,現在は必ずしも十分に活用されていません。今後、Rapidcommunicationsを見直し、優れた論文をいち早く紹介するように改善していきたいと考えています。是非、会員の皆様方もRapid communicationsへのご投稿をお考えください。
Reviewarticles、Reflections and Perspectives、Commentary
Original articlesに加えて、JBでは主として我が国の生化学・生命科学分野における最新の優れた成果をReview articlesとして紹介してきました。2014年以降もReview articlesの掲載を継続するとともに、トピックス性の高い総説を2~3編集めた特集を組むことも考えています。Reflectionsand Perspectivesは、2009年から開始された企画で、我が国の卓越した研究者について研究内容やお人柄を含めて、ゆかりの深い方にご紹介していただいています。Commentaryは、2011年から企画されたもので、JBに発表された論文の中でインパクトの高いものを選んで、その内容について読者にわかりやすく解説します。これらの原稿執筆を、会員の皆様にお願いすることになりますが、是非ご協力賜りますようお願いいたします。
投稿数とImpact Factor
JBの編集上の問題点につきましても、会員の皆様と現状を共有する必要があるかと思います。先ほど、年間投稿数が300~400編と記載しましたが、実は年々減少の傾向にあります。競合する学術誌がこの数年間に創刊されたことも原因ではあるかと思いますが、投稿数減少が編集上の問題としてのしかかってきます。
Journalの評価の一つにImpact Factor (IF) があります。IFの功罪につきましては多々議論されるところではありますが、IFの低いJournalよりも高いJournalに掲載されたいと思うのは研究者の偽らざる気持ちだと思います。JBのIFは2009年の1.945から2012年の2.719に上昇しています。生化学系の学術誌のIFが下降傾向にある中でよく健闘しています。2009~2012年の高引用論文はJB2014年1月号に掲載していますので、ご覧下さい。
しかし、論文の質をIFに頼っていいのかという問題点も指摘されています。生化学会長の中西義信先生は会長便りで「DORAによる論文評価標準の提言」を紹介されています。JBの立ち位置が問われているのかもしれません。このようなJBの抱える問題点につきましても会員の皆様のご意見を頂戴できればと思っています。
生化学会員の皆様へのお願い
JBは、これまでも質の高い研究成果をOriginal articlesとして発表し、またReview articlesとして紹介してきました。会員の皆様方がJBに論文を投稿し、JBの論文を積極的に引用していただくことが、JBの発展に必須です。今後もJBの更なる発展のために会員の皆様の更なるご支援をお願いいたします。
日本生化学会会員のみなさん、
前号(Dec 2013)で紹介したように、DORAの宣言は“Journal Impact Factor(IF)値を使って個々の論文を評価することをやめよう”というものです。論文の優劣は内容の評価に基づいて判定されるべきですが、内容の理解が難しい場合や数値化判定が必要な時があります。そのような場面ではIF値を使わずにどうやって論文を評価したらよいでしょうか。DORAを支持する人たちもその方法を模索中のようです(EMBO Rep. 14:947)。
論文の評価をそれが掲載された学術雑誌(ジャーナル)のIF値に基づいて行うことが適切でないとする意見の根拠は、“高いIF値を持つジャーナルにも被引用頻度の低い論文が多く含まれる”ことです。何度も引用されることが優れた論文の証しだとすると、被引用回数を論文ごとに比べれば優劣が判明することになり、その数値はThomson Reuters社のWeb of Scienceを利用すると得られます。
その考えに基づくと、個々の研究者の論文業績は全発表論文の被引用回数の総和で評価できることになります。しかし、“ほとんどの論文は引用されていないが極端に被引用回数の多い論文が少しだけある”時に、その業績をどう評価できるでしょうか。例を挙げて考えてみましょう。ともに5編の論文を持つA氏とB氏を比較するとします。A氏の論文の被引用回数は115、2、1、1、1、一方のB氏では15、15、10、10、10です。被引用回数の総和はそれぞれ120と60であり、A氏がはるかに優勢です。しかし、A氏では1つの論文がたくさん引用されているために総数が大きいのに対し、B氏は総数ではA氏に劣るもののどの論文も10回以上引用されて一定の評価を受けているといえます。どちらの業績が優れているとみるかは意見の分かれるところでしょう。これを解決する手法が、米国のJ. E. Hirsch氏によって2005年に考案されています(Proc. Natl. Acad. Sci. USA 102:16569)。Hirsch氏が提案する「h index(エイチインデックス)」とは、“N回以上引用された論文をN編以上持つ時に、その研究者のh indexをNとする”というものです。前出のA氏とB氏のh indexはそれぞれ1と5に算定され、h indexに基づく評価ではB氏の業績の方が優れていることになります。ノーベル物理学賞の受賞者(2005年までの20年間)のh indexの平均値は40ほどだそうで、生化学などの生命科学分野ではh index値25~30が“優れた”論文業績の目安とされることがあります。近年ではh indexが使われる場面が増えており、これを教員の研究能力判定の指標のひとつにする大学もあるようです。
しかし、h indexによる論文業績の評価法も万全ではありません。まず、被引用回数は積算値なので公開後の期間の長い論文の方が有利です。また、総説や実験手法を記述する原著論文の被引用頻度は一般にこれら以外の論文よりも高い傾向にあります。さらに、内容が同レベルであっても専門領域が違えば論文の被引用頻度に差が生じるようです。こうなると、さまざまな補正をしなければ適切な数値は求まらないことになり、もはやHirsch氏オリジナルのh indexではなくなってしまいそうです。私は、被引用などの数値ではなく内容を見てくれ、と言い続けようと思います。
次号では、多様化が進むジャーナルの形態を考えます。
2014年1月
中西義信
日本生化学会会員のみなさん、
電子メールでお知らせしたように、これから毎月、私から会員のみなさんに宛てたメッセージ「会長便り」をウェブサイト上に掲載します。みなさんの研究やキャリアパスに役立つ情報を発信することを目的に、私が気になる世の中の出来事を記述します。
最初の数回は研究論文に関する話題を取り上げ、第一回目はSan Francisco Declaration on Research Assessment(DORA)による論文評価のやり方の提言を紹介します。
日々の実験で得られる研究成果は、学術雑誌(ジャーナル)上の論文として公表されます。その内容がすばらしければ、メディアで報道されたり別のジャーナルで紹介されたりして評価され、時には執筆者が讃えられます。しかし、論文の内容が優れているかどうかの判定は読む人によって異なるでしょう。研究成果の正しい評価はたいへん難しい課題です。
優れた内容の論文だけを掲載するジャーナルがあれば事は簡単ですが、そのようなものは存在しません。一方で、‘top-tier journal’とか‘high-impact journal’とよばれるジャーナルは存在し、Cell誌、Nature誌、及びScience誌がそれにあたることになっています。それらのジャーナルに論文が掲載されることで、ポジションを得たり研究費を獲得できたりすることが実際にあるようです(The Golden Club in Nature 502:291)。みなさんご存知のように、これらのジャーナルは高いJournal Impact Factor(IF)値を持ちます。IFは、Institute for Scientific Information社(現、Thomson Reuters社)を興したEugene Garfield氏によって1950年代に考案されました(「科学を計る–ガーフィールドとインパクトファクター」、窪田輝蔵著、インターメディカル、1996年)。以前よりIFの利用法はさまざまに議論されてきましたが、最近になって大きな動きがありました。それがDORAです。
http://www.ascb.org/dora/
DORAの宣言は、“個人/機関/地域の研究成果の評価はその内容に基づいてなされるべきであり、IFの誤った使い方に依ってはならない”というものです。全文の和訳もウェブサイトに掲示されているので、ぜひ読んでみてください。当初の署名人には一部のtop-tier journalの編集長、トップランクの研究機関、及び多くのノーベル賞受賞者が含まれており、今でもその数は増えつつあります。そこにはCell Structures and Functions誌(細胞生物学会)とGenes to Cells誌(分子生物学会)の編集長の名前もありますが、私たちのJournal of Biochemistryはまだ加わっていません。これについては学会としての対応を含めて今後に検討される予定です。
次回は、IF値を使わずに論文や研究者の評価をどうやって数値化できるのかを考えます。
2013年12月
中西義信
| 開催日 | 2014年10月15日(水)~18日(土) |
| 開催地 | 京都市(国立京都国際会館) |
| 大会会頭 | 米田 悦啓 (独立行政法人医薬基盤研究所) |
| 大会HP | http://www.aeplan.co.jp/jbs2014/ |
 大学院生の頃から生体膜に興味を持っていました。生体膜の機能はもちろん興味深いのですが、その機能を調べるために生体膜から部品を取り出し、組み立て直して、生体膜機能の一部を人工膜上に再現する「プロテオリポソームへの再構成」という単純明快な研究手法が気に入っていました。生体膜の持つしくみを単純な形で再現、予想通りに機能するかを検証し、他に未知の部品やしくみがあるかもしれないということを探る方法です。これまでいくつかの生体膜機能を再構成して解析してきましたので、この手法を使って研究を進めていくのは私の「芸風」と言えるかもしれません。その嗜好は今でも変わっておらず、現在は小胞輸送を研究の対象としています。
大学院生の頃から生体膜に興味を持っていました。生体膜の機能はもちろん興味深いのですが、その機能を調べるために生体膜から部品を取り出し、組み立て直して、生体膜機能の一部を人工膜上に再現する「プロテオリポソームへの再構成」という単純明快な研究手法が気に入っていました。生体膜の持つしくみを単純な形で再現、予想通りに機能するかを検証し、他に未知の部品やしくみがあるかもしれないということを探る方法です。これまでいくつかの生体膜機能を再構成して解析してきましたので、この手法を使って研究を進めていくのは私の「芸風」と言えるかもしれません。その嗜好は今でも変わっておらず、現在は小胞輸送を研究の対象としています。
私が小胞輸送の研究に足を踏み入れたのは、理化学研究所の中野明彦先生の研究室にスタッフとして在籍することが許されたのがきっかけです。当時、オルガネラ膜から輸送小胞が形成される過程で、低分子量GTPaseが必須であることが既に分かっており、小胞体からゴルジ体へ向かうCOPII小胞の形成過程ではSar1という低分子量GTPaseが機能していることが明らかになっていました。中野先生はこのSar1の発見者であり、そのため中野研究室ではセミインタクト細胞や分画した小胞体膜を用いたCOPII小胞形成の試験管内再構成系がいち早く構築され、精力的に分子メカニズムの研究が進められていました。しかしSar1に限らずどの輸送経路においても、輸送小胞の形成時における低分子量GTPaseの機能については多くのグループによる努力にもかかわらずはっきりとした答えが出ていませんでした。当時解析に使われていた実験系が完全に純化されたものではなかったからです。
有名なKornberg博士の「酵素研究の10の戒律」のひとつに“Do not waste clean thinking on dirty enzymes”とあります(この引用がここで適切かどうかは分かりませんが)。私は、COPII小胞の形成に必要な因子のみを取り出して試験管内で反応を再現すれば、反応過程におけるGTP加水分解の解析ができると考え、COPII小胞の形成に必要なすべてのコンポーネントを精製して人工膜小胞からCOPII小胞を形成させる実験系の構築を行うことにしました。再構成という手法自体は別段珍しいものではないのですが、実はあまり人が手をつけない手法という意味ではこれは無謀な挑戦だったのかもしれません。しかし、私はタンパク質科学を得意とする東工大資源研の吉田賢右先生の研究室で学位を取得した後、Kornberg博士のお弟子さんであるBill Wickner先生(米国ダートマス大)の研究室に留学して、やはり生化学的手法を中心に研究を行っていましたので、精製因子を用いて実験を行うことが染みついていたことと、膜と聞けば条件反射的に再構成したくなる性分から、私にとってこの流れはごく自然なものでした。
実験系に必要な因子には膜タンパク質や精製がやっかいなタンパク質も含まれ、それらをすべて一人で揃えるのは大変な作業でしたが、なんとか解析に使える実験系を調えることができました。その結果、Sar1はGTP加水分解による活性化と不活性化を繰り返すことによって、不適切な積み荷を輸送小胞から排除する「校正能」を発揮するとともに、積み荷タンパク質の濃縮も同時に行っているということが明らかになりました。その後、この制御メカニズムは他の小胞輸送経路で機能する低分子量GTPaseについても共通している可能性が示唆されるようになっています。この研究は、私の「芸風」を生かせたとても気に入っているものです。
これまでの研究によって、必要最小限のシステムで働く輸送小胞の形成反応については随分と分かってきました。しかし、細胞内に組み込まれたこのシステムの仕組みは、それほど単純ではないということも同時に分かってきました。今後は、新たな二歩目を踏み出すとともに、自分で運営するようになった研究室のメンバーそれぞれが自分の「芸風」を磨いて発信していけるようサポートしていくことも同時に行っていきたいと思っています。最後に、自分の興味のままに研究が行える環境を与えて下さいました中野明彦先生には、心から感謝申し上げます。
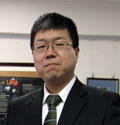 「分子生物学から先に入った奴は、蛋白質の扱い方が雑だ。でも蛋白質(生化学)から入った奴は、分子生物学の実験も丁寧にやれる。」そう先輩に言われたのが、大学院博士課程の時でした。今にして思うと乗せられた瞬間だったのかもしれません。(注:分子生物学も蛋白質の扱いも両方丁寧な方は沢山いらっしゃいますので上記は事実ではありません。)私の研究の根っこは、熊本大学薬学部の環境で培われて、その修士時代、癌転移に関係するあるプロテアーゼの精製に時間を費やしていました。逆に言うと私にはそれしか出来なかった訳ですが、癌転移と糖鎖の研究がやりたくて博士課程は、大阪大学大学院医学系研究科生化学研究室の門戸を叩き、谷口直之先生のご指導を仰ぎました。生化学とは、生命科学を研究する上ではなくてはならない基礎であり、必要となる分野です。蛋白質しか扱った事のなかった私が、当時冒頭の言葉でどんな分野の研究でも上手くやれるかもしれないと錯覚し、生化学的手法を武器に、難治性疾患の研究をライフワークにしたいという思いが芽生えたのもこの頃だったと思います。
「分子生物学から先に入った奴は、蛋白質の扱い方が雑だ。でも蛋白質(生化学)から入った奴は、分子生物学の実験も丁寧にやれる。」そう先輩に言われたのが、大学院博士課程の時でした。今にして思うと乗せられた瞬間だったのかもしれません。(注:分子生物学も蛋白質の扱いも両方丁寧な方は沢山いらっしゃいますので上記は事実ではありません。)私の研究の根っこは、熊本大学薬学部の環境で培われて、その修士時代、癌転移に関係するあるプロテアーゼの精製に時間を費やしていました。逆に言うと私にはそれしか出来なかった訳ですが、癌転移と糖鎖の研究がやりたくて博士課程は、大阪大学大学院医学系研究科生化学研究室の門戸を叩き、谷口直之先生のご指導を仰ぎました。生化学とは、生命科学を研究する上ではなくてはならない基礎であり、必要となる分野です。蛋白質しか扱った事のなかった私が、当時冒頭の言葉でどんな分野の研究でも上手くやれるかもしれないと錯覚し、生化学的手法を武器に、難治性疾患の研究をライフワークにしたいという思いが芽生えたのもこの頃だったと思います。
阪大でもプロテアーゼとは切っても切れない研究テーマを頂き、学位修了後の進路を模索していた時に、現所属のチームリーダーである西道隆臣先生の講演を聴き、「プロテアーゼしか知らない自分でもアルツハイマー病(AD)の、更には脳の研究ができるかもしれない」と、雑多なバックグランドを抱えて、AD研究に参戦することになりました。このように新たな分野へ飛び込み、異分野の要素を持ち込んだ事が、一つのブレイクスルーに繋がった気がしています。
ADは、多くの病理学的解析と家族性遺伝子変異の発見から、アミロイドβペプチド(Aβ)の蓄積が、発症の原因の一つであると考えられています。Aβには、アミノ酸40個からなるAβ40と更に疎水性アミノ酸が2つ長く、神経毒性が高いAβ42の2種類が知られており、この2つのAβ種についての研究が主流となっていました。しかし近年、アミノ酸の長さが異なるAβ亜種が発見されてきました。そんな折に、Aβ43がこれまでのAβ42やAβ40よりも毒性が高く、AD患者の病理形成に重要な役割を果たしていることを明らかにすることが出来ました。たった一つアミノ酸しか違わないのに!という主観的な視点も、物性としては大きな変化であり科学という視点からは必然の変化であるということを再認識することが出来ました。こういう頭の中だけで想像できないような現象を一つ一つつぶさに見て、難治性疾患を克服するために必要なエビデンスをこれからも積み重ねて行きたいと思っています。そして、細分化された現代科学の中で、自分だけの道を突き詰めると共に、他分野との橋渡しを進めていければと強く思っています。
末筆になりましたが、日本生化学会奨励賞という大変名誉ある賞を頂き、またそのお陰で、ここに自分を振り返る機会も頂けました。学会関係者並びにこれまでお世話になった多くの先生方にこの場をお借りして厚く御礼申し上げます。この賞の名を汚さぬよう、今後も研究に邁進して行きたいと思います。
 この度は、私のようなものに栄えある賞をいただきまして、誠にありがとうございます。これまで御指導くださいました地神芳文先生(産業技術総合研究所)、木下タロウ先生(大阪大学)をはじめ、多くの皆様に深く感謝申し上げます。
この度は、私のようなものに栄えある賞をいただきまして、誠にありがとうございます。これまで御指導くださいました地神芳文先生(産業技術総合研究所)、木下タロウ先生(大阪大学)をはじめ、多くの皆様に深く感謝申し上げます。
私は田舎生まれのため、子供の頃から近くの山野を駆け回っておりました。そんな中で、自分や生き物の体(細胞)で今何が起きているのか、どんな反応が起こっているのかを知りたいと興味を持つようになりました。もともと高校の教員になりたいと思っておりましたが、学部4年の時に神坂泰先生(産業技術総合研究所)にお世話になり、リン脂質代謝に関わる酵素の精製をはじめると実験が面白くなってきました。大学院で地神先生の研究室に配属されてからは、グリコシルホスファチジルイノシトール(GPI)アンカーと呼ばれる糖脂質について学び始めました。GPIアンカーはタンパク質に修飾されるため、糖鎖・脂質・タンパク質を一度に研究できる非常に魅力な(後に非常に手強いと分かるのですが、)研究テーマに思えました。
当時、GPIアンカーの研究は哺乳動物細胞や出芽酵母の変異株の解析から、GPIの生合成に関わる20種類以上の遺伝子が次々と同定され、生合成経路のほとんどのステップに関わる遺伝子が決定されておりました。しかし構造学的な解析から、タンパク質に修飾される前と修飾後の細胞表面に局在するGPIアンカーではその構造に違いがあることが明らかになっておりました。このことからタンパク質に修飾された後、GPIは構造変化を受けることが示唆されておりました。幸運にも、そのうちのGPIの脂肪酸を入れ替える反応に関わる遺伝子を同定することができ、それがGPIアンカー型タンパク質の脂質ラフトとの会合に重要な役割を果たすことを示すことができました。またGPI糖鎖部分の構造変化が修飾タンパク質の小胞体からの効率的な輸送に必要であることを示すことができました。
よく「GPIはどうしてあんなに複雑な構造をしているのですか?」と聞かれます。確かに細胞膜にタンパク質を繋ぎ止めるだけであれば、もっと単純な形で良い気がします。これについては明確な答えを持っておりませんが、その構造の一つ一つに何らかの意味があるのではないかと思っております。今後、GPIアンカー構造の普遍性と多様性について、その機能の一端を明らかにできたら大変嬉しいです。私はまだまだ未熟であり、自分に自信を持てておりませんが、1つ1つの現象に正対して、基礎的な土台をしっかりと築きながら本質を学ぶ姿勢を大切にしていきたいと考えております。
 私は学生時代の6年間、東大薬学部の佐藤能雅先生の研究室で蛋白質結晶学の基礎を学びました。この期間が私の研究者としての基礎であり、とても貴重な時間であったと確信していますが、当時は強い危機感も抱いていました。そのころは構造生物学という言葉が使われ始めたころですが、多くの日本の結晶学者は生物屋というよりも化学屋で、酵素反応は分かっても生命現象がわからない、すなわち生物学的なセンスがない人がほとんどだったと思いますし、私もまさにその典型例でした。学位取得後、北海道大学薬学部の稲垣冬彦先生率いるNMRのラボにポスドクとして参加させていただきましたが、結晶学のラボとの文化の違いに驚き、多様なバックグランドのラボメンバーの中にいるうちに知らず知らずのうちに化学屋から生物屋への転換がはかれたと思っています。そして何よりも、オートファジーという大変刺激的なテーマに出会えたことが、その後の私の研究の方向性を決定付けました。
私は学生時代の6年間、東大薬学部の佐藤能雅先生の研究室で蛋白質結晶学の基礎を学びました。この期間が私の研究者としての基礎であり、とても貴重な時間であったと確信していますが、当時は強い危機感も抱いていました。そのころは構造生物学という言葉が使われ始めたころですが、多くの日本の結晶学者は生物屋というよりも化学屋で、酵素反応は分かっても生命現象がわからない、すなわち生物学的なセンスがない人がほとんどだったと思いますし、私もまさにその典型例でした。学位取得後、北海道大学薬学部の稲垣冬彦先生率いるNMRのラボにポスドクとして参加させていただきましたが、結晶学のラボとの文化の違いに驚き、多様なバックグランドのラボメンバーの中にいるうちに知らず知らずのうちに化学屋から生物屋への転換がはかれたと思っています。そして何よりも、オートファジーという大変刺激的なテーマに出会えたことが、その後の私の研究の方向性を決定付けました。
オートファジーは言うまでもなく、現在東京工業大学フロンティア研究機構の大隅良典先生が世界のパイオニアとして分野を開拓されましたが、大隅先生からは研究以外にも多くのことを学ばせていただいております。「若いうちに偉くならない方が良い。」飲み会などの席で大隅先生が良く口にされる言葉ですが、ポスドク時代はその意味がまったくピンと来ませんでした。しかし歳を重ね、ポストに就き、自身で実験できる時間が徐々に減少し、さらには研究のことを考える時間さえも限られてくると、その言葉の意味が重くのしかかってきます。幸い、私は二年前から教育負担のない研究所に着任したため、大学時代では想像できないほど研究のことだけを考え、自身で手を動かせる恵まれた環境にいます。若いころは当然のことが年を取るにつれできなくなる、そのことを肝に銘じて、今の時間を大切に、偉くなる誘惑を断ち切ってできるだけ長く研究を楽しみたいと思います。
 この度は、異化的硝酸還元系(嫌気呼吸系の一種)の蛋白質電子伝達反応に関わる一連の研究成果におきまして、日本生化学会奨励賞という大変名誉ある賞を頂戴し、学会関係者各位ならびに諸先生方に厚く御礼申し上げます。また、身の引き締まる思いでいっぱいです。本ページでは、これまでの研究内容というよりは、どんな気持ちで研究を進めてきたかを簡単に述べることで、生化学分野に足を踏み入れたばかりの大学院生の方々に、少しでも参考になれば幸いです。
この度は、異化的硝酸還元系(嫌気呼吸系の一種)の蛋白質電子伝達反応に関わる一連の研究成果におきまして、日本生化学会奨励賞という大変名誉ある賞を頂戴し、学会関係者各位ならびに諸先生方に厚く御礼申し上げます。また、身の引き締まる思いでいっぱいです。本ページでは、これまでの研究内容というよりは、どんな気持ちで研究を進めてきたかを簡単に述べることで、生化学分野に足を踏み入れたばかりの大学院生の方々に、少しでも参考になれば幸いです。
「構造生物化学」という言葉が、私の現在の専門分野を説明する際に最も適しております。というのも、主としてX線結晶構造解析法を用いた酵素蛋白質の高分解能立体構造解析と、ストップトフロー等を用いた高速反応速度論解析とを二本の柱として、生体内で起こる様々な生化学反応を“化学”的に理解しようとしているからです。このような「構造生物化学」も広い視野で見るとその根底には「生化学」があります。
今から16年前になりますが、修士学生時代に何気なく手に取った一冊の学会誌『生化学』(当時、この世にこんな面白い雑誌があるのかと感動した事を思い出します)に出会い、その後すぐに日本生化学会へと入会させていただいた事が現在の私の研究に繋がっていることは言うまでもありません。
私のバックグラウンドは結晶構造解析や化学等ではなく文字通りの「生化学」を主体とした研究で修士・博士の学位を取得しております。もちろん、当時から結晶構造解析や化学的な解析についての基礎知識や興味はある程度保持しておりましたが、まだ学生であった私にとってはとても敷居(ハードル)の高い2つの研究領域でありました。それが何故、そこに足を踏み入れることができたのか‥今思うとそれは、おそらく私自身の心の中で何物にも勝る「知りたい!」という好奇心と、人一倍のポジティブ思考が、そうさせたのではないかと推測します。具体的には、ある1つの酵素蛋白質において様々な変異体を作成して、酵素活性や基質結合能などの生化学的解析をしているうちに、その変異体も含めた酵素蛋白質の立体構造やそれが基質と相互作用している様子(できれば触媒反応中間状態も)を、どうしても自分の目で見てみたくなった!というのが、正直な気持ちです。そんな私がとった手段は、自ら立体構造解析できるようにスキルアップすることであり、ポスドク時代にX線結晶構造解析へと足を踏み入れることになります。
X線結晶構造解析で立体構造が見えた後、「どういった立体構造が機能へと結びつくのか?」に関して新たな疑問が次々と出て来て、さらにそれを実験ならびに理論的に証明したくなってきます。私の場合は、生体内の何れの反応においても「“分子内の電子の振る舞い”や“溶媒等も含めた多分子運動(動力学)”などの化学的要素が蛋白質固有の立体構造によってどのように影響し合い、各反応ステップに貢献するか?」を知る事が様々な反応機構の本質的理解に繋がると考えるようになり、どうしてもさらに“化学”の知識を取り入れたくなり、もちろん、生化学もX線結晶構造解析も継続しつつ、現在に至っております。
新たな研究領域に進む(自分のスキルに取り入れる)事は大変勇気のいることだと思います。「本当に自分がその道に進む事が正しいのか?」また「本当に自分はその分野で頑張れるのか?結果を残すことが出来るのか?その分野に自分は向いているのか?」など様々な不安が脳裏をよぎることは至極、当然のことのように思います。しかしながら、そういった不安は、その道に進んでみるととても小さなことだったと感じることが多いです。実際には、そんなことよりも「そこで自分に出来る事は何なのか?自分は何をするべきなのか?」を第一に考え行動することがとても重要で、それが異分野に迷い込んだ子羊にならずに、その道を突き進む秘訣(コツ)となります。
学生時代に、「生化学」に出会っていなければ今の私はありません。もっと言えば、当時の生化学的な実験・解析で「不思議だな、何故だろう?」と感じたその瞬間に、私の現在に至るまでのレールは敷かれていたように思います。
それ故、生化学に足を踏み入れたばかりの若い方々には、その実験や解析中に、「面白いなぁ」と感じたその瞬間を是非、忘れずにいてもらいたい。そして、自分の気持ちに素直に行動してもらいたい。「どうして?」「何故だろう?」などの感情が自然に湧き出てきたら、とことんまで調べてみてほしい。何故なら、その知的好奇心が全てのパワーの源となって、この先どんな苦難に遭遇しても必ずや乗り越えられるはずですから。
 子供の頃から、動物に興味があり、主に昆虫を捕まえては動き回る様子や食ったり食われたりする様子をずっと眺めていました。今思い返すとひどいことをしていたものですが、これが現在の研究興味の根源だったとも思われます。私は培養細胞を用いた分子シャペロンの研究で学位を取得した後、哺乳動物を用いた発生学研究をしたいと思い、京都大学ウイルス研究所の影山龍一郎先生の研究室で博士研究員として神経分化、体節形成の研究を行い、ダイナミックな発生現象の面白さに魅了されました。発生学に傾倒するうち、形態の形成から機能の発達に直結した発生現象に興味が広がり、2003年にミシガン大学のJohn Y. Kuwada先生の研究室に留学して以来、脊椎動物がどのように運動機能を獲得し発達させるかを明らかにすべく、ゼブラフィッシュを用いた運動発達の研究を行っています。
子供の頃から、動物に興味があり、主に昆虫を捕まえては動き回る様子や食ったり食われたりする様子をずっと眺めていました。今思い返すとひどいことをしていたものですが、これが現在の研究興味の根源だったとも思われます。私は培養細胞を用いた分子シャペロンの研究で学位を取得した後、哺乳動物を用いた発生学研究をしたいと思い、京都大学ウイルス研究所の影山龍一郎先生の研究室で博士研究員として神経分化、体節形成の研究を行い、ダイナミックな発生現象の面白さに魅了されました。発生学に傾倒するうち、形態の形成から機能の発達に直結した発生現象に興味が広がり、2003年にミシガン大学のJohn Y. Kuwada先生の研究室に留学して以来、脊椎動物がどのように運動機能を獲得し発達させるかを明らかにすべく、ゼブラフィッシュを用いた運動発達の研究を行っています。
観賞用熱帯魚でもあるゼブラフィッシュは発生が早く、研究室レベルで変異体スクリーニングが可能な脊椎動物です。胚期は体が透明なので、また成魚でも皮膚の色素を欠く成魚系統が作製されたことで、ライブイメージングが可能な脊椎動物として認知されつつあります。ゼブラフィッシュは受精から17時間後にヒトの胎動に相当する自発的運動をはじめ、21時間までに侵害刺激に対する逃避運動、さらに36時間までに泳動能を獲得します。私はこれら初期の運動に異常のあるゼブラフィッシュ変異体をスクリーニングし、運動の獲得、発達に関わる遺伝子の同定を試みました。得られた変異体には感覚ニューロンの異常、中枢ニューロンの異常、神経筋接合部の異常、筋の異常とさまざまなものがありました。硬直するような異常運動をする変異体が複数得られましたが、あるものは中枢ニューロンの異常であり、また別のものは筋の異常であることを見いだし、見た目による直感的な判断では運動を理解できないことを知り、運動システムの複雑さに驚くとともに、ますます惹きつけられていきました。運動発達の異常はヒトの進行性の運動障害とも関係し、ゼブラフィッシュの変異体の研究はヒト疾患の原因遺伝子同定、ゼブラフィッシュを疾患モデルとした運動障害の治療実験にも発展しました。グリシン作動性シナプスに異常のある変異体は個人的に一番思い入れのあるものですが、この研究はグリシン作動性シナプスが遺伝的プログラムだけで形成されるのではなく、神経活動に依存して形成されるという発見にも行き着き、これはシナプス形成の研究へと展開しています。
研究は何を見いだすかによって思いがけない方向に発展するもので、研究の方向性をきっちり定めて研究を進めても、3年後にどういう方向に展開しているかは予想できません。これまでの経験則から、研究が見通しの立たない混沌とした中にあっても自分が面白いと思うことを常に追求していれば、必ず道は開け、研究はよい方向へ発展するようです。今回の受賞を励みに、今後も自分の好奇心と真摯に向かいあい、研究を楽しんでいきたいと思っています。最後にこれまでのアドバイザーである永田和宏先生(現、京都産業大学)、影山龍一郎先生(京都大学)、John Y. Kuwada先生(ミシガン大学)、小田洋一先生(名古屋大学)、川上浩一先生(国立遺伝学研究所)にこの場をお借りして御礼申し上げます。また、これまでの研究室でお世話になった先輩、後輩の皆様、一緒に研究をしてくれた研究チームのメンバーに心より感謝いたします。生化学会の先生方には今後もご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
 生命の基本現象の神秘を化学で見てみたい、という漠然とした思いを抱き、学部4年生の時に、阪大蛋白研の崎山文夫先生の研究室に入室しました。データに高い質を求められる厳しい研究室でした。修士2年に上がる頃に与えられたテーマが「植物自家不和合性の分子機構の解明」。植物の受精なんて特殊な生命現象の一つに過ぎないとか、この研究でタンパク質の分子認識の一般原理までたどりついてみたいとか、勝手に思ったことを思い出します。科学研究の広大な荒野の上に立ったものの、片隅の細い道を歩き始めた、というイメージでした。ともかく自家不和合性に関わるS-RNaseの同定、精製、化学構造解析と生化学研究を進めました。担当の乗岡茂巳先生が私の性質を知ってか、放任してくださったのが幸いして、実験を独自にデザインすることを覚え、研究が楽しくなり始めました。そこでS-RNaseの糖ペプチド断片の質量分析から、N-結合型糖鎖にN-,N’-ジアセチルキトビオースがあることを発見します。N-結合型糖鎖の最小単位がトリマンノシルコア構造であるという常識が邪魔をして、当初は質量をアサインできずに困っていました。発見には固定観念を脱ぎ捨てる必要がありますが、その難しさを体験した一コマです。阪大理学部の長谷純宏先生のご指導を仰ぎ、糖鎖の蛍光標識法を用いてキトビオース構造を確かめました。道半ばだけれど、歩んだ道の傍らに可憐な一輪の花(路傍の花)を見つけた、という発見です。
生命の基本現象の神秘を化学で見てみたい、という漠然とした思いを抱き、学部4年生の時に、阪大蛋白研の崎山文夫先生の研究室に入室しました。データに高い質を求められる厳しい研究室でした。修士2年に上がる頃に与えられたテーマが「植物自家不和合性の分子機構の解明」。植物の受精なんて特殊な生命現象の一つに過ぎないとか、この研究でタンパク質の分子認識の一般原理までたどりついてみたいとか、勝手に思ったことを思い出します。科学研究の広大な荒野の上に立ったものの、片隅の細い道を歩き始めた、というイメージでした。ともかく自家不和合性に関わるS-RNaseの同定、精製、化学構造解析と生化学研究を進めました。担当の乗岡茂巳先生が私の性質を知ってか、放任してくださったのが幸いして、実験を独自にデザインすることを覚え、研究が楽しくなり始めました。そこでS-RNaseの糖ペプチド断片の質量分析から、N-結合型糖鎖にN-,N’-ジアセチルキトビオースがあることを発見します。N-結合型糖鎖の最小単位がトリマンノシルコア構造であるという常識が邪魔をして、当初は質量をアサインできずに困っていました。発見には固定観念を脱ぎ捨てる必要がありますが、その難しさを体験した一コマです。阪大理学部の長谷純宏先生のご指導を仰ぎ、糖鎖の蛍光標識法を用いてキトビオース構造を確かめました。道半ばだけれど、歩んだ道の傍らに可憐な一輪の花(路傍の花)を見つけた、という発見です。
その後、長谷先生の研究室の助手に採用され、この一輪の花の周りを歩き始めます。キトビオースを生成し得る酵素の探索です。学生と一緒に失敗を重ねながら、4年間に渡る基質選び、酵素精製の末(これぞ生化学の泥臭さ)、エンド-β-マンノシダーゼを発見します。この酵素の基質特異性がユニークで、既知の別酵素の基質特異性と相補的になっていて、パズルのピースが埋まるように、植物N-結合型糖鎖の分解経路の全体像が表れました。最初に見つけた一輪の可憐な花の周りに別の花があったのです。次いで、エンド-β-マンノシダーゼが探し求められていた植物細胞壁を分解するα1,2-フコシダーゼと複合体を形成していることを見つけます。また別の花を見つけたわけです。さらにエンド-β-マンノシダーゼ遺伝子の発現制御植物体を解析すると、どうも単純に解釈できない現象が起こっています。糖鎖分解の機能以外の、当初望んだ生命の基本現象的なことが見つかる予感がしています。まだ周りに花がありそうです。今回の受賞対象の研究の過程を振り返ると、路傍の花を見つけ、それが一面の美しい花の群れの一輪にすぎなかったと知る過程だったように思えます。
「路傍の花」。独創的な研究の芽を指して、江上不二夫先生が、阪大蛋白研においては佐藤了先生が、よく語られていた言葉だと聞いています。阪大理学部では長谷純宏先生からよく聞いた言葉です。阪大蛋白研・理学部には、人を惹きつけるおもしろい研究だけでなく、路傍の花(雑草ではダメなのですが)を見つけたような研究も良しとする雰囲気がありました。阪大生化学の伝統なのだと思いますが、誰も手をつけていない研究をやれ、と幾度となく言われました。こういう雰囲気の故だったのだと思います。主流になった太い道を行く研究は言うまでもなく面白い。細い道の研究は困難が多く、最初は面白みに欠けるけれど、花に出会うという研究の醍醐味を味わえる確率が高く、それは面白い。路傍の花が見えたら、その花のかすかな香りをたよりに一面の花の群れに出会うことも、つまり、生命の基本現象を解き明かすこともあるのだ。そんなふうに思うようになりました。(大学院生への語りかけということで、何かしらの参考になればと思い、体験談を書かせていただきました。)
最後になりましたが、このような研究環境を与えてくださったこと、花を見つける科学研究の醍醐味を経験させてくださったことに、長谷先生をはじめ、指導してくださった先生方に、この場をお借りして感謝申し上げます。そして一緒に研究を行った学生の皆さんの力添えに感謝申し上げます。奨励賞受賞はたいへん光栄ですが、身の引き締まる思いでおります。目的地に向かって道を歩む研究だけでなく、この路傍の花を見つけた感覚を忘れずに、一輪でも花に出会ったときに味わえる研究者特有の満足感を大学院生に伝えていくことにも微力を注ぎながら、教育・研究に邁進して行きたいと決意新たにしております。
 この度は、糖転移酵素の機能に関する一連の研究成果に関しまして、日本生化学会奨励賞を授与頂きまして、日本生化学会の関係各位に厚く御礼申し上げます。私が10年来従事しております糖鎖研究は、これまで生化学会を率いて来られた多くの諸先生方の偉大な研究成果に立脚したものであり、研究を始めるきっかけをお与え頂いた古川鋼一教授を始めとする多くの関係研究分野の諸先生方に感謝申し上げます。
この度は、糖転移酵素の機能に関する一連の研究成果に関しまして、日本生化学会奨励賞を授与頂きまして、日本生化学会の関係各位に厚く御礼申し上げます。私が10年来従事しております糖鎖研究は、これまで生化学会を率いて来られた多くの諸先生方の偉大な研究成果に立脚したものであり、研究を始めるきっかけをお与え頂いた古川鋼一教授を始めとする多くの関係研究分野の諸先生方に感謝申し上げます。
私が糖鎖研究を始めた1990年代の後半は、糖転移酵素による糖鎖合成経路の全容が明らかにされつつある時代でした。糖鎖は、100種類以上の異なる酵素(糖転移酵素)が逐次、糖転移を行なうことで、組み立てられるため、糖転移酵素の遺伝子機能を知ることで、糖鎖機能を分子レベルで追求することができます。当時、古川研究室においても、糖脂質に関連した主要な糖転移酵素遺伝子が、発現クローニングやデータベース検索により次々と同定され、糖脂質糖鎖の合成経路の全容が解明に向かう状況で、このようなホットな時期に糖鎖研究に参加できたのは、非常に幸運だったと思います。また、糖脂質の各種抗体や酵素活性に必要な基質などが、日本国内の諸先生方の研究室において整備されていたことが、一連の糖転移酵素の同定を成功に導く上で非常に重要な要素であったのは間違いなく、日本における糖鎖研究の層の厚さの重要性を再認識致しました。
その後、留学先での研究をきっかけに、上皮成長因子ドメインに見出される、特殊な糖鎖修飾の機能に関わる研究を続けて現在に至っております。本研究においても、生化学的な研究基盤となったのは、日本の生化学分野における先駆的な研究成果でした。80年代の後半に、長谷先生や岩永先生を始めとする研究グループが、血液凝固因子の上皮成長因子ドメインにO-フコース型糖鎖やO-グルコース型糖鎖といった風変わりな糖鎖修飾を発見されております。発見当時は、その奇妙な糖鎖構造の機能的意義について充分な認識をされるには至りませんでした。しかしながら、その後、Notch受容体に同様な構造が見つかり、その生理機能の重要性の理解が進むなかで、古くて新しい風変わりな糖鎖修飾が再び注目されつつあります。
最近、私たちの研究グループもO-GlcNAcで始まる上皮成長因子ドメインの新規の糖鎖修飾の同定に成功致しました。今後も、伝統的な糖質科学研究を一段と発展させると同時に、これから糖鎖研究を目指す若き生化学者の興味を引くような新たな研究領域を開拓し、次世代の糖質科学研究の発展に貢献できるよう、微力ながら努めて参りたいと考えています。
 金子みすゞさんの「星とたんぽぽ」と題する詩にある上記の文句は、私の座右の銘です。今回の生化学会奨励賞を頂くことになった「細胞分裂軸」の研究は、まさにこの言葉を発端としています。私がこの研究を始めたのは8年ほど前ですが、その頃の細胞分裂軸の研究は、線虫や酵母、ハエといった遺伝学的解析のできるモデル生物を用いて特に非対称分裂を中心に進められていました。私は大学院生の時からずっとHeLa細胞を用いて細胞周期の研究をしていたのですが、HeLa細胞は簡単に細胞周期を分裂期に同調できるし、siRNAも効率良く効くし、世界中で使われている細胞だし、何とかしてHeLa細胞を使って分裂軸の解析が出来ないものかと思っていました。しかしながらHeLa細胞は極性がありませんし、非対称分裂もしないので、この細胞の分裂軸に方向性はあるのかしら?どうみたら良いのかしら?と日々顕微鏡を覗き込んでは首を傾げながら分裂期紡錘体を眺めていました。
金子みすゞさんの「星とたんぽぽ」と題する詩にある上記の文句は、私の座右の銘です。今回の生化学会奨励賞を頂くことになった「細胞分裂軸」の研究は、まさにこの言葉を発端としています。私がこの研究を始めたのは8年ほど前ですが、その頃の細胞分裂軸の研究は、線虫や酵母、ハエといった遺伝学的解析のできるモデル生物を用いて特に非対称分裂を中心に進められていました。私は大学院生の時からずっとHeLa細胞を用いて細胞周期の研究をしていたのですが、HeLa細胞は簡単に細胞周期を分裂期に同調できるし、siRNAも効率良く効くし、世界中で使われている細胞だし、何とかしてHeLa細胞を使って分裂軸の解析が出来ないものかと思っていました。しかしながらHeLa細胞は極性がありませんし、非対称分裂もしないので、この細胞の分裂軸に方向性はあるのかしら?どうみたら良いのかしら?と日々顕微鏡を覗き込んでは首を傾げながら分裂期紡錘体を眺めていました。
ある時、ダメを承知で何らかの遺伝子(EB1だったように思います)をsiRNAでノックダウンすると、それまで紡錘体の両極は必ず同時にフォーカスがあっていたものが、どうもフォーカスがずれる、つまり通常の細胞では紡錘体は細胞ー細胞外基質面に平行になるが、EB1をノックダウンするとZ軸に沿って傾くことに気が付きました。その時、私の脳裏にすぐに浮かんだのが上記の金子さんの詩のフレーズです。「ああ、私は何て盲目だったのだろう。」と顕微鏡の暗室で一人卒然としました。もともと中学の時から空間図形は苦手だったのですが、それにしてもこれほど毎日顕微鏡を覗いていながら、こんな簡単な方向性の存在に気がつかなかったとは、と自分を情けなく思いました。一度「見える目」を持つと、あとは分子機構の解析を楽しく進め、細胞接着やリン脂質の重要性などの新規機構の存在を明らかにすることが出来ました。細胞周期の研究から細胞分裂軸の研究に移行するまでの約3年間、ほとんどデータらしいものが出ておらず、私は完全にスランプに陥っていました。この間、私がラビリンスに入り込んで陳腐な実験に取り組もうとする度に一生懸命引きとめて下さり、また分裂軸の方向性から研究の方向性を見出すまで根気よく待って下さった恩師の西田先生には感謝の念がつきません。
細胞分裂軸の研究は、これからが本番です。HeLa細胞の簡単な系を利用してsiRNAライブラリーによるスクリーニングを行えば、新期の分裂軸制御因子を同定できます。これをマウスで解析すれば、これまで難しかった哺乳類発生過程における分裂軸の分子機構や組織構築における役割を明らかにすることが出来ます。また面白いことにスクリーニングの結果、どうやら分裂軸の決定には代謝制御が絡んでいることも分かってきました。ですので、私の研究室のメンバーは今更ながら「ストライヤーの生化学」や「ボートの生化学」を紐解いては代謝マップを頭に叩き込んでいます。今まさに生化学、細胞生物学、発生生物学の融合が必要であることは、最近のがん研究の動向を見ても明らかです。この融合過程には沢山の「見えぬけれどもある」ものたちがきっと存在しています。彼らを見いだせる目を持つよう努め、彼らを「見えるものたち」にするよう日々精進していきたいと願います。
 私は、京都府立大学農学部農芸化学科の鈴木讓先生の研究室において、当時助手であった渡部邦彦先生の指導の下、プロリン残基導入による酵素の耐熱化に関する研究に携わりました。今にしてみれば、この時期に、生化学的手法を用いた酵素研究の魅力に引き込まれたように思います。学部を卒業後に、縁あって京都大学大学院の左右田健次先生の研究室(京都大学化学研究所)に修士課程の学生として移り、今回の受賞対象となったセレンおよび硫黄を含むアミノ酸の代謝に関する研究テーマに出会いました。それ以来17年以上に渡り、含硫黄補因子やセレンタンパク質の生合成に関する生化学研究を行ってきました。
私は、京都府立大学農学部農芸化学科の鈴木讓先生の研究室において、当時助手であった渡部邦彦先生の指導の下、プロリン残基導入による酵素の耐熱化に関する研究に携わりました。今にしてみれば、この時期に、生化学的手法を用いた酵素研究の魅力に引き込まれたように思います。学部を卒業後に、縁あって京都大学大学院の左右田健次先生の研究室(京都大学化学研究所)に修士課程の学生として移り、今回の受賞対象となったセレンおよび硫黄を含むアミノ酸の代謝に関する研究テーマに出会いました。それ以来17年以上に渡り、含硫黄補因子やセレンタンパク質の生合成に関する生化学研究を行ってきました。
左右田研で最初に着手したのは、セレノシステインリアーゼという哺乳動物由来酵素の精製とcDNAクローニングであり、当時助教授の江﨑信芳先生、当時助手の栗原達夫先生の指導の下で研究を開始しました。修士課程の間は実験が思うように進まず、日々地道な実験の繰り返しでした。一つの転機が訪れたのは博士課程に入って間もなくの頃でした。それは、やっと解析することの出来たセレノシステインリアーゼの部分アミノ酸配列が、窒素固定細菌のNifSタンパク質(システインデスルフラーゼ)に類似していることが判明した時です。NifSはニトロゲナーゼの補因子である鉄硫黄クラスターの形成に関わると考えられておりましたが、その相同遺伝子が窒素固定細菌以外にも見出されたことから、これらのNifS相同遺伝子が全ての生物の鉄硫黄クラスター形成に関与する可能性があるのではないかと考え、当時ゲノム配列解読が進行中であった大腸菌の酵素について解析を行うことにしました。もちろん、それらの相同遺伝子がセレノシステインリアーゼと関連する可能性も期待してのことです。今振り返ると、随分と乱暴な思いつきでしたが、江﨑先生(教授にご就任)と栗原先生の後押しもあり、好きなように実験を展開することができました。主として、一つ一つ酵素を精製しその諸性質や構造を詳細に明らかにする、という生化学の基本に忠実な研究でしたが、その後の含硫黄補因子やセレンタンパク質の生合成へと発展し、本分野における新たなパラダイムの構築を支える研究の一端程度にはなったのではないかと思っております。
研究室では実に多くの事を学びましたが、私にとって特に印象深いのは、「とことんまで考え抜く」こと、「違う視点で物事の本質を捉える」こと、「自分が本当に面白いと思う研究をする」ことの重要性です。まだまだ教えていただいた事のわずかしか実践できていませんが、これらを身をもって教えて下さった先生方に心より感謝申し上げます。今後は、これまでの経験を活かしながら、自らが運営を開始した研究室のメンバーと共に、生化学の発展のために努めていきたいと考えております。日本生化学会会員の皆様には今後もご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
 私が九大三原研で大学院生としてミトコンドリアの研究を始めてから15年以上になる。博士研究としてミトコンドリアの生化学研究手法を学んだ後に、岡崎の基礎生物学研究所の大隅良典先生の研究室にポスドクとして参加させていただき、膜の生合成、ダイナミクスに強く興味を持つようになった。ちょうどその当時、大隅先生の研究蓄積を元にしてオートファジーの分子基盤の理解が飛躍的に進展していく時期であり、新しい研究領域が形成されていく過程を身近に経験できたのは私にとって幸せなことだった。大隅先生のされたように、「新しいこと、誰もいないところで面白いことを自ら開拓する」ことを自分でも実践したいと考えていた。そこで九大で新しくミトコンドリア研究を始めるにあたり、まだ哺乳動物では未開拓であったミトコンドリアの融合と分裂のダイナミクスに注目して研究を開始した。同時に、三原先生の「生化学的手法で、新規因子を同定することこそ真のブレイクスルーになる」との言葉を信じて研究を進めてきた(が、未だ期待通りの展開を果たせておらず、残念に思っている)。当時、酵母でいくつかの遺伝子が単離・解析されていたことを手がかりにして、哺乳動物での解析系を構築し、関連因子を同定し解析を行い、自分達の手でほぼすべての研究を立ち上げていった。ありがたいことに、先の見えない立ち上げ研究であるにもかかわらず、多くの優秀な学生が参加してくれた。それらの研究成果は現在のミトコンドリア研究に重大な貢献をしてきたと自負している。今回、日本生化学会奨励賞を戴く栄誉を受けたが、これは多くの共同研究者を代表して戴いたものだと考えている。今回の受賞を契機に本研究をさらに飛躍的に展開・発展させていくことが私に課せられた使命であると考えている。
私が九大三原研で大学院生としてミトコンドリアの研究を始めてから15年以上になる。博士研究としてミトコンドリアの生化学研究手法を学んだ後に、岡崎の基礎生物学研究所の大隅良典先生の研究室にポスドクとして参加させていただき、膜の生合成、ダイナミクスに強く興味を持つようになった。ちょうどその当時、大隅先生の研究蓄積を元にしてオートファジーの分子基盤の理解が飛躍的に進展していく時期であり、新しい研究領域が形成されていく過程を身近に経験できたのは私にとって幸せなことだった。大隅先生のされたように、「新しいこと、誰もいないところで面白いことを自ら開拓する」ことを自分でも実践したいと考えていた。そこで九大で新しくミトコンドリア研究を始めるにあたり、まだ哺乳動物では未開拓であったミトコンドリアの融合と分裂のダイナミクスに注目して研究を開始した。同時に、三原先生の「生化学的手法で、新規因子を同定することこそ真のブレイクスルーになる」との言葉を信じて研究を進めてきた(が、未だ期待通りの展開を果たせておらず、残念に思っている)。当時、酵母でいくつかの遺伝子が単離・解析されていたことを手がかりにして、哺乳動物での解析系を構築し、関連因子を同定し解析を行い、自分達の手でほぼすべての研究を立ち上げていった。ありがたいことに、先の見えない立ち上げ研究であるにもかかわらず、多くの優秀な学生が参加してくれた。それらの研究成果は現在のミトコンドリア研究に重大な貢献をしてきたと自負している。今回、日本生化学会奨励賞を戴く栄誉を受けたが、これは多くの共同研究者を代表して戴いたものだと考えている。今回の受賞を契機に本研究をさらに飛躍的に展開・発展させていくことが私に課せられた使命であると考えている。
ミトコンドリアの研究分野が最近本当に面白くなってきた。ミトコンドリアはその重要性から古くから多くの研究が行われているが、一方ミトコンドリア自身の形成、特に哺乳動物のミトコンドリアについての分子理解は長らく残されたままであった。今回の受賞対象であるミトコンドリアの融合と分裂の膜ダイナミクスは、ミトコンドリア自身の特性を変えてしまう反応である。分裂には小さく独立したミトコンドリアの数を増やし、逆に融合により細胞内のミトコンドリアがほぼ1つに繋がっていく。この融合・分裂のバランスが変化することにより、ミトコンドリアが関与する多くの生命現象に影響を与える可能性が考えられるようになった。面白くて役に立つ、不思議なミトコンドリアの世界を、今後もじっくりと眺め続けて楽しんでゆきたいと考えている。
 私が理学部4年生だった1990年代の前半、生命科学の分野ではいわゆる「細胞内情報伝達」の研究が隆盛期を迎え、実験医学の特集号に毎月のように取り上げられるほどの「花形」研究分野となっていました。大学院での研究室を探していた私は、当時医科学研究所から学部の講義に来られた竹縄忠臣先生が、チロシンキナーゼ情報伝達に関与するSH2、SH3ドメインや、竹縄研で新たに同定されたアダプター蛋白質であるGrb2(竹縄研ではAshと命名)などについて熱く語るのを聞き、たちまちこの「花形」研究分野に魅了されてしまいました。「ミーハー根性」に突き動かされたと言ってもいいと思います。気がつくと早速医科研まで押し掛けて行き、大学院から受け入れて頂く約束を取り付けていたのでした。翌春、晴れて所属することとなった竹縄研ではGrb2下流分子の同定が着々と進んでおり、中でもN-WASPやWAVEファミリーの相次ぐ発見は細胞外情報がアクチン細胞骨格を制御する仕組みを初めて明らかにするもので、同じ研究室に身を置く一人として非常に興奮しながら「傍観」することとなりました。傍観…そうです。今流行りの研究をしたいと飛び込んだ研究室でしたが、実際の自分自身の研究テーマはそこからどんどん離れて行き、気がつくとなんだか古くさい(と当時の私には思えた)「リン脂質代謝」になっていたのです。元来、竹縄研の伝統的な研究テーマは「イノシトールリン脂質代謝」であり、当時も助手の深見希代子先生(現東京薬科大教授)を中心に数人で細々と(?)続けられていました。花形であるN-WASPグループに参加できなかった私は、今にして思えば「仕方なく」このリン脂質グループに加わったような気がします。
私が理学部4年生だった1990年代の前半、生命科学の分野ではいわゆる「細胞内情報伝達」の研究が隆盛期を迎え、実験医学の特集号に毎月のように取り上げられるほどの「花形」研究分野となっていました。大学院での研究室を探していた私は、当時医科学研究所から学部の講義に来られた竹縄忠臣先生が、チロシンキナーゼ情報伝達に関与するSH2、SH3ドメインや、竹縄研で新たに同定されたアダプター蛋白質であるGrb2(竹縄研ではAshと命名)などについて熱く語るのを聞き、たちまちこの「花形」研究分野に魅了されてしまいました。「ミーハー根性」に突き動かされたと言ってもいいと思います。気がつくと早速医科研まで押し掛けて行き、大学院から受け入れて頂く約束を取り付けていたのでした。翌春、晴れて所属することとなった竹縄研ではGrb2下流分子の同定が着々と進んでおり、中でもN-WASPやWAVEファミリーの相次ぐ発見は細胞外情報がアクチン細胞骨格を制御する仕組みを初めて明らかにするもので、同じ研究室に身を置く一人として非常に興奮しながら「傍観」することとなりました。傍観…そうです。今流行りの研究をしたいと飛び込んだ研究室でしたが、実際の自分自身の研究テーマはそこからどんどん離れて行き、気がつくとなんだか古くさい(と当時の私には思えた)「リン脂質代謝」になっていたのです。元来、竹縄研の伝統的な研究テーマは「イノシトールリン脂質代謝」であり、当時も助手の深見希代子先生(現東京薬科大教授)を中心に数人で細々と(?)続けられていました。花形であるN-WASPグループに参加できなかった私は、今にして思えば「仕方なく」このリン脂質グループに加わったような気がします。
しかし、実際にイノシトールリン脂質代謝酵素の同定や性状解析を進めていくうち、これらの脂質代謝経路が極めて多彩な生命現象に関わることが不思議に思えて来ました。細胞膜を構成する小分子に過ぎないイノシトールリン脂質が特定の機能を発現するには、「特異的な蛋白質との相互作用」を介しているはずです。そこで、個々の機能を担うイノシトールリン脂質結合蛋白質を同定しようとあれこれ試行錯誤を繰り返しましたが、ありふれた疎水性の蛋白質が採れてくるばかりでなかなかうまく行きません。丁度その頃ヒトゲノムが解読され、多くの蛋白質が進化上保存された一次構造上の機能単位である「ドメイン(モジュール)」から成り立つことが分かっていました。ある日データベースを眺めていた私は、一次構造上保存された「ドメイン」として定義されながら、生化学的な機能が分かっていないものが実に数多く存在することに気がつきました。リン脂質との相互作用が生命にとって重要な機能であるならば、それを担うドメインもまた進化上保存されているはずです。早速ありとあらゆる機能不明ドメインをピックアップし、それらが脂質結合活性を持つのかを一つ一つ調べて行きました。すると、エンドサイトーシス関連蛋白質に保存された「ENTHドメイン」と呼ばれる領域がイノシトールリン脂質に強く結合することが分かったのです。
この発見を端緒にして、私の研究はエンドサイトーシスにおける細胞膜の形状変化を担う「生体膜変形ドメイン」へと展開し、今日に至っています。リン脂質は確かに生体膜を構成する小分子に過ぎませんが、脂質分子が二次元的に集合した生体膜は生命秩序の創出と維持にとって必須の構造体です。細胞質蛋白質と脂質との可逆的な相互作用が生体膜の二次元平面を三次元曲面へとダイナミックに変換し、細胞内小胞輸送や細胞分裂、細胞運動などに深く関わることに気づかされ、日々わくわくしながら研究を進めています。大学院生の頃「仕方なく」始めたリン脂質研究ですが、これほどまでに奥の深い研究テーマを与えて下さった竹縄先生には感謝の思いでいっぱいです。
近年、発生生物学やゲノム科学、システムズバイオロジーといったマクロかつ俯瞰的な研究領域が「花形研究分野」として注目を集めています。それに対して「生化学」という言葉は、むしろ近視眼的な古くさいイメージで捉えられているように思います。確かに、個々の生体分子がシステムとして振舞う挙動は生命の理解に不可欠ですし、個体レベルでの生理的解析もなくてはならない作業です。しかし、一つ一つの生体分子の物性を「より正確に」理解し、それらが組み上げる精巧な分子メカニズムを再構成することは生命科学の根幹であるとも思います。私はこれからも生化学を基盤にした「奥の深い」研究を目指して行きたいと思っています。
 この度は平成21年度の生化学会奨励賞に御採択頂きありがとうとうございます。大変光栄であり、今後この賞に恥じぬよう研究を進めて参りたいと思います。
この度は平成21年度の生化学会奨励賞に御採択頂きありがとうとうございます。大変光栄であり、今後この賞に恥じぬよう研究を進めて参りたいと思います。
私は東京大学大学院医学系研究科細胞情報学教室で清水孝雄教授の御指導の下、脂質生化学の研究に携わっています。生体膜リン脂質生合成や生理活性リン脂質(血小板活性化因子、PAF)生合成を研究しています。生体膜の主成分であるリン脂質は組織や状態によって組成が異なり非常に多様です。このリン脂質生合成の最終ステップはリゾリン脂質アシル転移酵素(LPLAT)によって触媒されることが1950年代に示唆されましたが、約50年間分子同定には至っていませんでした。近年になりようやく10種類のLPLATが同定されました。私達はそのうち6種類を発見しました。
10年前、私はPAFの定量や生合成酵素の精製をテーマとして清水研究室に入りました。PAFは強力な生理活性を持つリン脂質であり、その生合成酵素のリゾPAFアセチル転移酵素(lyso-PAFAT)は先ほどのLPLATと似た反応を示し、同じグループに属します。この酵素は膜タンパク質であり、過去に様々なグループが精製に挑戦していましたが成功していませんでした。私もブタ脾臓から膜画分を調整し、可溶化、カラム精製と進めましたが、活性はどんどん減りました。大学院生とポスドク時代を含めて約6年間試みていましたが、同定に至りませんでした。もちろんこの間に酵素の活性化調節を調べるなどの精製以外の実験も進めていましたが、6年間かけた精製のテーマでは当然ながら論文を書けませんでした。
その後、清水教授からの指示もありlyso-PAFATを含むLPLATをターゲットとしてゲノムデータベース探索を始めました。似た反応を触媒するアシル転移酵素を鋳型に未知遺伝子を約15種類クローニングし、順番に酵素活性を放射ラベルされた基質を用いて測定しました。すると、ある遺伝子で今までの実験で見たことの無いようなカウントが表示されました。最初は測定機器の故障か?自分のミスか?と疑いましたが、再現するにつれ自信を持ちました。これがlyso-PAFAT遺伝子(後にLPCAT2と命名)の発見でした。精製を6年間試みて同定できず、データベースでは4ヶ月で見つけたことになります。しかし、精製を試みていた期間は無駄ではなく、lyso-PAFATの扱いなど教科書にも論文にも無い情報がいつの間にか身に付いていました。さらに、詳細は割愛しますが、同時に見つけたLPLAT(LPCAT1)の活性検出や、その後見つけた新しいアシル転移酵素ファミリー(MBOATファミリー)の解析にも大きな好影響を与えました。これらは研究室の大学院生や技術職員と共に進めていきました。
私は研究経験の早い段階でタンパク質精製に携わったこと自体、運が良かったと思います。今回のlyso-PAFATの精製では成功しませんでしたが、この時の経験は研究を続ける上で大きな財産となっています。未知のタンパク質精製にはその方法に教科書は無く、何をしても間違いではありません。馬鹿げているような試みも大事で、うまくいけばそれが正解の一つなんです。この考えがあり数年成果が無くても楽しく研究できました。それをできる研究環境にいられたことも運が良かったことであり、清水教授やラボメンバー、OBの先生方に感謝しています。もちろん、しっかり調べて考えることは大事ですが、それに縛られて動けなくなるのはダメです。経験を積む程、良くも悪くもこの試し実験ができなくなります。また、これらを楽しめるかどうかも大事で、うまくいかなくても落ち込まないことです。結果や環境に不平不満を持っても先に進めません。このコーナーの趣旨でもあります後輩へのメッセージ(偉そうなことを言える立場ではありませんが)としては、「安定した精神的タフさを維持し、できることはどんどん試してみる」です。成果が出るに越したことは無いですが、大学院生時代は色々経験することも大事だと思います。私自身もこの感覚を忘れずに研究経験を積んで、微力ながら生化学に貢献できるように進めていきたいと思います。
 深く考えずに行った選択が良い結果を招くことは幸運以外の何ものでもありませんが、京都大学薬学部で市川厚先生の主宰する衛生化学研究室(現在の薬学研究科生体情報制御学分野)に参加したことは、まさにそうした幸運でした。当時は、ヒスタミン合成酵素と、種々のプロスタグランジン受容体のcDNAクローニングが相次いで行われていた時期で、研究室には心地よい緊張感が満ちていました。初めのうちは夜になるとお役ご免で帰宅していたのですが、少しでも研究室に残っていたいような気持ちにさせる(実際は邪魔をしていたのですが)不思議な魅力がありました。週1回、全員が集合する研究報告会と文献紹介があったのですが、これは経験の程度により生じる垣根をできるだけ作らない、自由闊達なものでした。ひたすら厳しい研究報告会は後にたくさん見てきましたが、市川研では厳しい意見が出ようとも最後は常に建設的な提言で終わり、院生のやる気をそぐようなことは殆どなかったように記憶しています。そうした雰囲気の中、博士課程の先輩や、助教授、助手といったスタッフの方に、実験ノートを持って行ってはいろいろ相談したことは印象に残っています。当時はそうしたことは研究室では当たり前のことと考えていましたが、研究室を出て外を見ると必ずしもそうではないことを知りました。大学院生の皆様は強面のスタッフ、先輩に無理やりにでも突撃することで、新しい風を吹き込んでみてはいかがでしょうか。
深く考えずに行った選択が良い結果を招くことは幸運以外の何ものでもありませんが、京都大学薬学部で市川厚先生の主宰する衛生化学研究室(現在の薬学研究科生体情報制御学分野)に参加したことは、まさにそうした幸運でした。当時は、ヒスタミン合成酵素と、種々のプロスタグランジン受容体のcDNAクローニングが相次いで行われていた時期で、研究室には心地よい緊張感が満ちていました。初めのうちは夜になるとお役ご免で帰宅していたのですが、少しでも研究室に残っていたいような気持ちにさせる(実際は邪魔をしていたのですが)不思議な魅力がありました。週1回、全員が集合する研究報告会と文献紹介があったのですが、これは経験の程度により生じる垣根をできるだけ作らない、自由闊達なものでした。ひたすら厳しい研究報告会は後にたくさん見てきましたが、市川研では厳しい意見が出ようとも最後は常に建設的な提言で終わり、院生のやる気をそぐようなことは殆どなかったように記憶しています。そうした雰囲気の中、博士課程の先輩や、助教授、助手といったスタッフの方に、実験ノートを持って行ってはいろいろ相談したことは印象に残っています。当時はそうしたことは研究室では当たり前のことと考えていましたが、研究室を出て外を見ると必ずしもそうではないことを知りました。大学院生の皆様は強面のスタッフ、先輩に無理やりにでも突撃することで、新しい風を吹き込んでみてはいかがでしょうか。
市川研ではヒスタミン合成の調節機構について研究を進めてきましたが、そのうちヒスタミンを貯留している「マスト細胞」への関心が高まってきました。マスト細胞は全身の様々な組織に分布する免疫細胞で、免疫系、神経系、代謝系に由来する様々な刺激に応答し、多様なメディエーターを産生することが知られています。こうした細胞の性質を考慮すると、マスト細胞は生体内の優れたセンサーとしてはたらくことが予想されるのですが、従来の研究では即時型アレルギーや、寄生虫感染といった限られた範囲での機能が主に取り上げられてきました。日本生化学会奨励賞では、IgEとの関わりや分化に伴う変化についての研究を評価していただきました。今後の展開として、マスト細胞のあっと驚くような生理機能を見いだすことができないかと作戦を練っているところです。
この原稿を書いているさなか、行政刷新会議の仕分け作業が大変な熱気の中進んでいます。学術振興会特別研究員制度や、科研費の若手研究などが仕分け対象として俎上にあり、果たして将来はどうなるのだろうと不安を覚えている方もたくさんいらっしゃると思います(私もこうした制度に支えられた研究者として文科省に意見を送りました)。一方で、たくさんの優れた研究者や、本会を含む多数の学会、大学から数々の力強い反論、意見が提出され、研究活動の価値とは何かといった本質的な議論も起こっています。大変な危機であることは間違いありませんが、こうした議論のおかげで、私たちがどうして研究をするのかという大事なことを考える良い機会にもなっています。生化学では現象と物質との関係が重視されます。薬と身体という意味で私が所属する薬学ではもちろんのことなのですが、その他にも生命科学の幅広い分野において、生化学的なセンスはきらりと光るヒントを与えてくれます。「生化学」誌に掲載されるバラエティ豊かな研究成果を見ても、生化学の技術や志向が様々な領域に広がりを持つことが理解できます。タンパク質の時代、遺伝子の時代を経て、分析技術の発展と共に、再び生体内の様々な「物質」が注目を集めています。本欄をお読みになっている大学院生の皆様には、私のようにたまたま生化学の世界に足を踏み入れた方も多いと思うのですが、実は私たちは生命科学のこれからの発展に、「生化学」というコアの部分で貢献できるチャンスを持っているのです(そんな気持ちでタイトルを付けました)。
博士課程をはじめとした若い研究者へのメッセージと言うことで、些か僭越なことも述べました。日本生化学会会員の皆様には今後もご指導ご鞭撻を賜ることと存じますが、微力ながら生化学の発展に力を尽くしたいと考えております。宜しくお願い申し上げます。
 DNAが積極的に分解される。不思議な話に思えませんか?DNAは遺伝情報の原本で、半保存的複製によって合成されるため、RNAやタンパク質とは異なり、細胞内で代謝、分解されることはありません。しかし、細胞の死、アポトーシスではDNAが分解されます。私が修士課程の大学院生として、長田重一先生の研究室の門を叩いた時、ちょうどそこでは細胞が死ぬ際に活性化されるDNA分解酵素の同定がなされたところでした。細胞死の引き金の引かれた細胞抽出液と単離核を混合し、DNA分解をin vitroで再構成する系の構築に始まり、大変な労力のタンパク精製の末の輝かしい成果で、生化学の威力、美しさがとても目映く見えました。一方で、DNA分解がおきなくても細胞は無事(?)死ぬことができるとわかり、DNA分解の意義が不思議に思えました。私は、アポトーシスでのDNA分解の生理作用を明らかにするという興味深いテーマに従事するチャンスを頂き、一貫して研究を続けて来ました。その道のりは苦、楽、驚に満ちており、貴重な経験を得ながら、大変充実した研究生活をおくってきました。研究室の素晴らしい先行研究のもと、長田先生を始めとする研究室の方々に御指導を頂き、一緒にサイエンスを行えたことが何より幸運であったのは明白で、言葉に尽くせぬ感謝の思いです。
DNAが積極的に分解される。不思議な話に思えませんか?DNAは遺伝情報の原本で、半保存的複製によって合成されるため、RNAやタンパク質とは異なり、細胞内で代謝、分解されることはありません。しかし、細胞の死、アポトーシスではDNAが分解されます。私が修士課程の大学院生として、長田重一先生の研究室の門を叩いた時、ちょうどそこでは細胞が死ぬ際に活性化されるDNA分解酵素の同定がなされたところでした。細胞死の引き金の引かれた細胞抽出液と単離核を混合し、DNA分解をin vitroで再構成する系の構築に始まり、大変な労力のタンパク精製の末の輝かしい成果で、生化学の威力、美しさがとても目映く見えました。一方で、DNA分解がおきなくても細胞は無事(?)死ぬことができるとわかり、DNA分解の意義が不思議に思えました。私は、アポトーシスでのDNA分解の生理作用を明らかにするという興味深いテーマに従事するチャンスを頂き、一貫して研究を続けて来ました。その道のりは苦、楽、驚に満ちており、貴重な経験を得ながら、大変充実した研究生活をおくってきました。研究室の素晴らしい先行研究のもと、長田先生を始めとする研究室の方々に御指導を頂き、一緒にサイエンスを行えたことが何より幸運であったのは明白で、言葉に尽くせぬ感謝の思いです。
遺伝子欠損マウス作製の立ち上げに試行錯誤の2年近くが過ぎ去るなど、研究が思うように進まなかったことは数え挙げればキリがありません。しかし、待望のマウスが作製でき、このマウスの細胞は、細胞死を誘導してもDNAがまったく分解されない結果を示す電気泳動の写真を目にした時の感動は忘れられません。その後、生体内ではもう1つのDNA分解経路が存在する事がわかり、私達の道程はさらに遥かなものになりましたが、その過程で、DNA分解が起きるのは何もアポトーシスに限らないと気づくに至りました。私達の研究は、生体内でのDNA分解という広いテーマに発展したのです。赤血球が成熟する際に脱核された核、レンズ細胞の分化過程で失われる核のDNAも分解されます。DNA分解酵素は、そのいくつかが同定され生化学的性状の解析が先行していましたが、生体内での働きは不明でした。私達は遺伝子欠損マウスの解析により、生体内では、局面ごとにそれぞれの酵素が、他では代替出来ない形でDNA分解を担っていることを証明しました。そして、これらDNA分解が妨げられると、致死性貧血、関節リウマチ、リンパ球発生異常、白内障などの疾患をもたらすことを見出し、DNA分解が重要な生理作用であることを明らかにしました。さらに、DNAは完全に自己の分子でありながら、分解されずに蓄積すると、自然免疫を過剰に活性化してこれら疾患を引き起こすこともわかりました。このように多くの予想外の結果、驚きが私達に訪れました。“DNAは重要な分子である一方、分解されるべき局面で分解されないと生体に害を及ぼす危険な分子であるかもしれない” 私達はこの新規の結論に今到達しています。
まだまだ駆け出し研究者の私ですが、これまでの研究を通じて、研究の奥深い魅力を実感するようになったと同時に、苦しさも感じるようになりました。与えられた問題を解き、巻末の解答頁をめくれば正誤が判明した頃は何と気楽だった事か。誰もが正答を知らない問いに対して自分の出した結論は本当に正しいのか?各実験において、ましてや、得られた結果を集大成して世に発信する時には限りなく不安がつきまといます。さらに、自分は何を明らかにしたいのかと自らに問うて決断を下したり、新規の問題を着想したり、勇気と開拓精神も試されます。けれども、この難しさにもかかわらず、大いなる楽しさが存在するから研究に惹かれてしまうのでしょう。私の場合それは、自分の知らない事を知りたいという好奇心、そして志を同じくする多様な人々の集うコミュニティの存在だと思います(生化学会もその一例でしょう)。個性豊かな人々が、様々な生命現象に興味と愛着を抱き、多彩な手法で謎に迫っています。他の研究者の見事な発見に感嘆し、日進月歩の知見を共有しながら、自分の興味の対象については(願わくば)自分の手で(同志と協力しつつ)真理を発見したいと心躍らせ研究を行う。この社会的活動の楽しさがあるからこそ、研究は魅力に輝いているのだと思います。加えて忘れてはならないのは、日々の実験に一喜一憂する楽しみでしょうか。仮説の真偽に決着をつける大実験でなくとも、plasmidが大量にとれれば嬉しいし、材料が調製できたかの確認westernでノンスペなく期待のバンドが出れば美しいと感じます。それで一日幸せでいられたりするのです。この道の前途、困難は考えれば考える程多いのですが、このかけがえのない楽しさを楽しむためにも日々厳しく精進していきたいと、決意を新たにしています。
 この度は日本生化学会奨励賞を授与頂きまして身に余る光栄であるとともに大変身の引き締まる思いです。選考委員の先生方をはじめ、日本生化学会の関係各位に厚く御礼申し上げます。今回の受賞対象は、高井義美先生の研究室(高井研)に入室してから現在に至るまで一貫して取り組んできた小胞輸送制御タンパク質トモシンに関する研究です。
この度は日本生化学会奨励賞を授与頂きまして身に余る光栄であるとともに大変身の引き締まる思いです。選考委員の先生方をはじめ、日本生化学会の関係各位に厚く御礼申し上げます。今回の受賞対象は、高井義美先生の研究室(高井研)に入室してから現在に至るまで一貫して取り組んできた小胞輸送制御タンパク質トモシンに関する研究です。
トモシンとの出会いは、高井研に入室した平成9年2月から始まります。その頃の高井研では、ほとんど全ての大学院生がHPLCやFPLCを使って、タンパク質の精製をしておりました。その当時使用していたフラクションコレクターがたまに誤作動を起こして貴重なサンプルを失うことが起こるので、フラクションコレクター前に座って、チャート用紙にフラクションナンバーをつけながら待機しておりました。ここから、トイレに行くのも気が気でない研究が始まりました。先輩からも精製中にトイレに行くとうんが落ちるから行くなよとよく言われておりました。本当にトイレとの関わりが深い研究室でした。
さて、本題ですが、この研究で一番苦労したのは、トモシンのリコンビナントタンパク質が可溶化されないことでした。様々な可溶化剤を用いましたが、ほとんど不溶性画分にいってしまいました。このままでは結合実験などの生化学実験ができないままに終わるのではないかという状況でした。その状況をセミナーで報告した時に、高井先生が「アホやな、お前は。オーバーレイ(ニトロセルロース膜にタンパク質を移してその膜上で結合を見る実験)でやったらええやんか。」と言われました。そのとおり、どんなに浮かないタンパク質でもSDSでは可溶化され、またSDS-PAGEにより分離できます。そこから、実験が動き出しました。感謝、感謝でした。また、このトモシンの細胞内局在を調べるため、ラット大脳を使ってsubcellular fractionation(シナプス小胞やシナプス膜を分画する実験)をしました。「Recovery(回収効率)はいくらや?」と聞かれ、「30%です。」と答えると、「それではfractionationになっていない。どこかでロスしているはずや。チューブの壁についたのもしっかり回収するんや。」と言われ、繰り返ししているうちに、実験の精度が上がり、80%、そしてついに120%というありえない数字をはじき出すまでになりました。この大学院生の頃は、毎朝、高井先生に実験プロトコルを確認して頂き、2~3時間程discussion(説教を1時間含む)を受け、実験に向かう日々を繰り返していました。また、毎夜、先生が帰る頃に、その日の実験結果であるウエスタンのフィルムを持って廊下を歩いているところをつかまえて頂き(廊下の端に私の姿が見えると大きな声で呼びつけられました)、その場でレーン構成と結果を説明致しました。そして、翌日の朝一まで(その日のうち)に改善したプロトコルを先生の机の上に置くということを繰り返しておりました。このマンツーマン指導というよりもゾーンプレス指導(discussion中、実際、高井先生は1人なのですが、あまりにもするどい指摘が多いため、私には15人くらいに感じておりました)により、私はトレーニングを受けました。こうしたトレーニングを受けることにより、物質やその物質が持つ物性の重要性を理解できるようになりました。そして、物質で勝負することを決心し、生化学を志すようになりました。このように高井先生との出会いが、私の方向性を決めたと感じております。
生化学の研究は、物質をとらえるところから入るため、本当にその物質が生理的に重要なのか、なかなか分かりません。そのため、物質の精製中はつまらないと感じることが多いと思います。ヨガの世界に「座っている10m下に、宝石が埋もれている。」という格言があります。最初から信じない人、1m掘って飽きる人、9m掘って諦める人、それらは皆、何一つ得ることができません。弱い自分を正当化し、何度もやめて楽になろうという誘惑と闘いながら、愚直にも10m穴を掘り続けた人だけが、真実という、宝石を発見し、手にすることができます。生化学の研究テーマは困難なものがほとんどです。困難と思われるテーマを研究する中で、弱い自分と対話し、闘い、信念とあきらめの狭間に揺れながら、荒波を乗り越えていくことによって、物質の奥底に潜む、真の事実、真実を発見することができます。そしてその原動力は、たった一つ、自分を信じることです。だめだと思った時、“おまえなら、きっとできるよ”ともう一人の自分にささやき続けることです。生化学はあと一歩が重要です。限界を感じた時、厳密に言えば、諦めきった時、その時に一歩、前に踏み出せるかどうかです。現在生化学をしている大学院生、これから生化学を始める大学院生には、つまらないと思っても、是非とも最後の最後まで(物質の真実をつかまえるまで)諦めずに頑張って頂きたいと感じております。
最後に、今回の受賞は、高井先生をはじめ、これまでご指導頂いた先生方ならびに一緒に研究を行った数多くの大学院生のお力添えによるものです。この場をお借りして心より御礼申し上げます。また、これまでの経験を生かし、生化学の研究と教育に微力を尽くすつもりです。特に教育においては、高井研で授けていただいた以上のことを大学院生に尽くし、研究の楽しさを伝えて行くつもりです。今後とも、尚一層の日本生化学会の先生方のご指導ご鞭撻を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
 「答えのわかっている問題しか解いたことがないので、どうなるかわからないものを研究するのは不安です」 これは研究室見学に来た一人の学生が発した言葉であった。私は「わからないことを明らかにしていく」ことこそが研究の醍醐味であり、最大の魅力だと思っていたので正直驚いた。
「答えのわかっている問題しか解いたことがないので、どうなるかわからないものを研究するのは不安です」 これは研究室見学に来た一人の学生が発した言葉であった。私は「わからないことを明らかにしていく」ことこそが研究の醍醐味であり、最大の魅力だと思っていたので正直驚いた。
私が小胞体タンパク質の局在化に興味を持ったのは大学4年生の時であった。“小胞体に局在化するチトクロムP450の膜貫通領域近傍にあるプロリンに富む領域の生理的意義を調べる”というテーマを頂き、卒業研究を行ったのが始まりであった。この際、分泌経路において小胞体、ゴルジ体、そして細胞外へと輸送される分泌タンパク質の流れに抗して、小胞体やゴルジ体のタンパク質はどのようにしてそこに留まるのかという問題に興味を持ち、どうしてもその分子機構が知りたいという衝動が湧き上がってきた。そこで、当時ご指導いただいた九州大学の大村恒雄先生に相談にのっていただき、東京大学の中野明彦先生が遺伝学的アプローチのできる出芽酵母を用いて分泌経路の研究をされていると教えていただいた。早速、中野研を訪問して直接お話を伺ったところ、なんと小胞体膜タンパク質の局在化機構の研究を開始し、もう変異株を分離しているとのことだった。なんとか院試を突破し、晴れて中野研の一員となった。そこで出会ったのが rer1 変異株である。その当時、小胞体局在化機構としては小胞体可溶性タンパク質に見られる KDEL シグナルと膜タンパク質のC末端に存在する KKXX シグナルを介した局在化メカニズムが明らかとなりつつあったが、実はこれらのシグナルを持たない小胞体膜タンパク質も数多く存在し、その局在化機構については全くわかっていなかった。Sec12タンパク質 (Sec12p) も既知の小胞体局在化シグナルを持たない小胞体膜タンパク質であり、rer1 変異株ではこの小胞体局在性が異常となる。そこで、この原因遺伝子を突き止めるというのが私のテーマとなったのであるが、当初遺伝学的マッピングで予測された第三染色体の領域にはこの変異を相補する遺伝子はみつからず、結局出芽酵母の第三染色体の遺伝子をひたすらクローニングしては rer1 変異株に導入するというノーデータの日々が一年以上続いた。どうも遺伝学的マッピングでうまく予測できなかったのは rer1 遺伝子が遺伝学的位置の特定が難しいセントロメアの真横の遺伝子であったからであった。晴れてクローニングした RER1 遺伝子は酵母からヒトまで高度に保存されているが、既知の遺伝子とは全くホモロジーのない新規膜タンパク質をコードしていた。一次構造からは何の手がかりもなかったので、考えられうる実験を生化学、遺伝学、分子生物学的視点から徹底的に行った。その結果、RER1 遺伝子産物 (Rer1p) はゴルジ体に局在し、ミスソートされた一群の小胞体膜タンパク質をゴルジ体から小胞体へ送り返すことによって局在化させる新しいタイプの分子選別装置であること、またその基質の認識は膜貫通領域間の相互作用によるものであることが明らかとなった。 さらに、鉄輸送体やϒ-セクレターゼのような複合体形成後に小胞体から細胞膜へと輸送される膜タンパク質が単独で存在する際にそれらに結合し、小胞体に送り返すことによって複合体形成を調節していることも明らかとなってきた。 Rer1p は当初なんだかよくわからない因子ではあったが、真正面から取り組むことによって最初の疑問であった「小胞体タンパク質の局在化機構」の一端を解明することができたことを嬉しく思う。現在は線虫 C. elegans に研究材料を移して多細胞生物における細胞内膜ダイナミクスの研究を進めているが、安易な方向に流されず、新しい生命現象の分子機構を一歩一歩解明していきたいと思う。
 タイトルを読むとなんだか難しい研究のように思われます。私もちょうど5年前までそう感じていました。私は、大学院では生化学・分子生物学を専攻し、それをベースにして博士研究員のときに分子薬理学的な研究をしてきました。したがって、具体性がない表現ですが、神経の研究をしたいと思ってもなかなかその分野に入るきっかけがつかめなかったことを覚えています。つまり、私は決して若くない年齢で神経を対象とした生化学研究に転身しました。そのため、日々出版され、ウェブサイトに載るような内容の研究は、自分には遠い存在であると思い、私でも研究できる比較的競争がない研究領域を探しました。しかし、時流に流されやすい私は、当時、現実味を帯びてきたさまざまな「組織の再生」に関する研究に興味を抱き、その方向で何かできることはないかと考え始め、思い切って、神経‘系’をin vitroで再構成してみようと思いました。周知のように、神経組織は、神経細胞だけではできていません。神経細胞よりも大量に存在するグリア細胞の存在なしでは、おそらくその機能を充分に発揮できないはずです。特に、有髄(グリア細胞由来のミエリンを有する)神経ではグリア細胞の役割が顕著で、無髄神経と比べて神経信号の伝達速度に大きな違いがあります。しかし、この有髄神経ができる分子メカニズムに関して、今でもほとんど明らかになっていないのが現状です。それは、この分野の研究が現在でも遺伝子改変動物の作出とその性状解析に比重をおき過ぎる傾向にあることが挙げられるからだと思います。しかし、ここ数年間の飛躍的な研究情報の蓄積と技術革新を背景に、多くの種類のグリア細胞と神経細胞を各々高純度に精製し、その後in vitroで共培養し再構成してから有髄神経をつくることが可能になってきました。そして、共培養下でもぞれぞれの細胞に特異的に遺伝子を導入することができるようになりました。その結果、有髄神経の形成を制御する、いくつかの新しい分子を、生化学的に同定することができました。また、これらは、同じ研究室の共同実験者や他の研究機関の同世代の共同研究者と共に勉強しながら、最新の情報を交換できる機会に恵まれたからだと思っています。しかし、未だに真の意味での有髄神経を再構成するということや、長期間に渡る神経発生の時間空間的な分子メカニズムを明らかにするということにはほど遠く、今後、この現象に関与するシグナル伝達因子をひとつひとつ明らかにし、その全容解明に向けて日々研究を継続していこうと思っております。以上、思いつきで始めた研究とその経緯に関して述べたものですが、この文章がすこしでも今後の研究の方向性を選択する際にお役に立てれば幸いです。ありがとうございました。
タイトルを読むとなんだか難しい研究のように思われます。私もちょうど5年前までそう感じていました。私は、大学院では生化学・分子生物学を専攻し、それをベースにして博士研究員のときに分子薬理学的な研究をしてきました。したがって、具体性がない表現ですが、神経の研究をしたいと思ってもなかなかその分野に入るきっかけがつかめなかったことを覚えています。つまり、私は決して若くない年齢で神経を対象とした生化学研究に転身しました。そのため、日々出版され、ウェブサイトに載るような内容の研究は、自分には遠い存在であると思い、私でも研究できる比較的競争がない研究領域を探しました。しかし、時流に流されやすい私は、当時、現実味を帯びてきたさまざまな「組織の再生」に関する研究に興味を抱き、その方向で何かできることはないかと考え始め、思い切って、神経‘系’をin vitroで再構成してみようと思いました。周知のように、神経組織は、神経細胞だけではできていません。神経細胞よりも大量に存在するグリア細胞の存在なしでは、おそらくその機能を充分に発揮できないはずです。特に、有髄(グリア細胞由来のミエリンを有する)神経ではグリア細胞の役割が顕著で、無髄神経と比べて神経信号の伝達速度に大きな違いがあります。しかし、この有髄神経ができる分子メカニズムに関して、今でもほとんど明らかになっていないのが現状です。それは、この分野の研究が現在でも遺伝子改変動物の作出とその性状解析に比重をおき過ぎる傾向にあることが挙げられるからだと思います。しかし、ここ数年間の飛躍的な研究情報の蓄積と技術革新を背景に、多くの種類のグリア細胞と神経細胞を各々高純度に精製し、その後in vitroで共培養し再構成してから有髄神経をつくることが可能になってきました。そして、共培養下でもぞれぞれの細胞に特異的に遺伝子を導入することができるようになりました。その結果、有髄神経の形成を制御する、いくつかの新しい分子を、生化学的に同定することができました。また、これらは、同じ研究室の共同実験者や他の研究機関の同世代の共同研究者と共に勉強しながら、最新の情報を交換できる機会に恵まれたからだと思っています。しかし、未だに真の意味での有髄神経を再構成するということや、長期間に渡る神経発生の時間空間的な分子メカニズムを明らかにするということにはほど遠く、今後、この現象に関与するシグナル伝達因子をひとつひとつ明らかにし、その全容解明に向けて日々研究を継続していこうと思っております。以上、思いつきで始めた研究とその経緯に関して述べたものですが、この文章がすこしでも今後の研究の方向性を選択する際にお役に立てれば幸いです。ありがとうございました。
「国立成育医療センター」HP:
http://www.nch.go.jp/pharmac/index.html
「東工大生命」HP:
http://www.bio.titech.ac.jp/bs_j/seitaisystem_009.html
![h21_5[1]](https://www.jbsoc.or.jp/seika/wp-content/uploads/2013/05/h21_51.jpg) 私は1993年4月、学部4年の卒業研究の時に東工大資源研の吉田賢右先生の研究室に配属になり、大学院生、学振PDとして計10年間、吉田研究室で研究を続けた。PD終了後、当時東大生産研にいた、研究室の先輩でもある野地博行さん(現阪大産研)の部屋で1年間PDとしてお世話になった。その後、今の所属である立教大学理学部に移り独立し、今に至っている。現在に至る研究は4年生から修士課程に上がるときに始めたもので、かれこれ14,5年は続けていることになる。私の研究のような、割と地味な研究が今回評価して頂けたことの一つの理由としては、このようにコツコツと続けてきたということもあるのかなと思っている(ドカンと一発ストレートではなく、ジャブの積み重ねという感じか?)。人事の流動性、いろいろな環境での経験などの重要性は認識しているし、新しいことに取り組んでいくのももちろん大切だが、しつこく同じことを続けるというのもアリじゃないかと思っている。(研究者なら誰でもそうかもしれないが)自分が今やっていることについては日本一、いや世界一詳しいと自信を持っていえる。
私は1993年4月、学部4年の卒業研究の時に東工大資源研の吉田賢右先生の研究室に配属になり、大学院生、学振PDとして計10年間、吉田研究室で研究を続けた。PD終了後、当時東大生産研にいた、研究室の先輩でもある野地博行さん(現阪大産研)の部屋で1年間PDとしてお世話になった。その後、今の所属である立教大学理学部に移り独立し、今に至っている。現在に至る研究は4年生から修士課程に上がるときに始めたもので、かれこれ14,5年は続けていることになる。私の研究のような、割と地味な研究が今回評価して頂けたことの一つの理由としては、このようにコツコツと続けてきたということもあるのかなと思っている(ドカンと一発ストレートではなく、ジャブの積み重ねという感じか?)。人事の流動性、いろいろな環境での経験などの重要性は認識しているし、新しいことに取り組んでいくのももちろん大切だが、しつこく同じことを続けるというのもアリじゃないかと思っている。(研究者なら誰でもそうかもしれないが)自分が今やっていることについては日本一、いや世界一詳しいと自信を持っていえる。
私自身の研究の中では2003年に発表(Kato-Yamada, Y., and Yoshida, M. (2003) J. Biol. Chem. 278, 36013)した「ATP合成酵素のεサブユニットへのATP結合の発見」がとても印象に残っている。分子量50万程度の巨大な膜タンパク質であるATP合成酵素の活性調節を担っている、εサブユニットという分子量わずか14,000程度の小さなサブユニットにATPが結合する事を見つけたというものである。
この発見はささやかなものかもしれないが、私からすれば大きな感動であった。ATPの結合を見るためにHPLCのオートサンプラを仕掛けて帰って、翌朝には大慌てでチャートをざっと見て、これは間違いなくATPが付いているという確信を得た。そのときの感覚は大げさかもしれないが、こんな感覚が10年に一度くらいでも味わえたらうれしいなあというようなものだった。
εサブユニットはATP濃度などに依存したATP合成酵素の活性調節に関与していることがわかっていたので、当然このATP結合が活性調節の直接の引き金になっているというストーリーを考え、それを確かめる実験を行った。いつもなら昼食の時にペラペラとしゃべっていたのだが、あまりに突拍子ない話だったので、ある程度様子がわかるまで(ちょうど1ヶ月後くらいにセミナーの発表にあたっていたのでそれまで)は吉田先生には黙っておこうと、(今にして思えば失礼な話であるが)内緒で実験を行った。果たして、どうやらεサブユニットへのATP結合は、活性調節におけるεサブユニットの構造変化の直接の引き金ではないということがわかった。この結果は非常に残念で、私は一気にトーンダウン。セミナーでも淡々と「こんな現象を見つけたけれど、どうやら活性調節とは関係の無いもののようなのであまり面白くなさそうだ」といった報告をした。しかし、吉田先生は「ATP結合に非常に高い特異性があるからきっと何か意味があるはずだ」といい、引き続き調べてみるのがいいのではないかと助言をしてくれた。結局さらに3年ぐらいかけて、活性状態が変化した後にεサブユニットへのATP結合が起こり、それが活性調節に関係しているということがわかった。私が一人でやっていたらここまでやる前に放り出してしまっていたかもしれない。センスの違ういろいろな人の意見を聞きながら研究を進めていくというのは大切なことだと改めて思う。
そんなこんなで、私の感動体験からもかれこれ5,6年たってしまったので、10年に1度それを味わうには、そろそろ種を蒔いて、芽を見つけたいと思っている。狙って得られるものかはわからないが、これからも研究を続けていき、またあんな感覚を味わってみたいと思っている。
吉田先生には、すばらしい研究環境を与えていただき、本当に自由に研究をすることができ、大変感謝している。また、時には適当な(もちろんいい加減という意味ではなく、properという意味で私の好きな言い回し)助言を与えてくれたこともとてもありがたく、私自身もそんな風に研究室を運営していきたいと思っている。
| 開催日 | 2013年9月23日(月)~27日(金) |
| 開催地 | |
| 集会名称 | 第49回X線分析討論会・第15回全反射蛍光X線分析法(TXRF)国際合同会議 (大阪市立大学杉本キャンパス学術情報総合センター) |
| URL | |
| 主催者団体名 | |
| URL | |
| 氏名 |
| 開催日 | 2013年8月1日(木)~2日(木) |
| 開催地 | |
| 集会名称 | 千里ライフサイエンス技術講習「生体2光子励起イメージング」(大阪大学免疫学フロンティア研究センター |
| URL | |
| 主催者団体名 | |
| URL | |
| 氏名 |
| 開催日 | 2013年6月19日(水)~21日(金) |
| 開催地 | |
| 集会名称 | 日本ケミカルバイオロジー学会第8回年会(東京医科歯科大学M&Dタワー) |
| URL | |
| 主催者団体名 | |
| URL | |
| 氏名 |
| 開催日 | 2013年6月15日(土)~16日(日) |
| 開催地 | |
| 集会名称 | 第8回トランスポーター研究会年会(熊本大学薬学部・宮本記念館) |
| URL | |
| 主催者団体名 | |
| URL | |
| 氏名 |
| 開催日 | 2013年6月15日(土) |
| 開催地 | |
| 集会名称 | 第15回日本医学会公開フォーラム:高齢者の疾患-生活の質の向上のために(日本医師会館大講堂) |
| URL | |
| 主催者団体名 | |
| URL | |
| 氏名 |
| 開催日 | 2013年6月7日(金)~8日(土) |
| 開催地 | |
| 集会名称 | 第40回生体分子科学討論会(大阪大学吹田キャンパス銀杏会館3F) |
| URL | |
| 主催者団体名 | |
| URL | |
| 氏名 |
| 開催日 | 2013年5月30日(木)~31日(金) |
| 開催地 | |
| 集会名称 | 第8回日本分子イメージング学会学術集会(横浜赤レンガ倉庫1号館) |
| URL | |
| 主催者団体名 | |
| URL | |
| 氏名 |
| 開催日 | 2013年5月27日(月)~30日(木) |
| 開催地 | |
| 集会名称 | 第16回国際定位・機能神経外科学会(ホテル日航東京) |
| URL | |
| 主催者団体名 | |
| URL | |
| 氏名 |
| 開催日 | 2013年5月27日(月) |
| 開催地 | |
| 集会名称 | 千里ライフサイエンスセミナー「メタボローム研究の疾患への応用を目指して」(千里ライフサイエンスセンタービル) |
| URL | |
| 主催者団体名 | |
| URL | |
| 氏名 |
| 開催日 | 2013年5月23日(木)~25日(土) |
| 開催地 | |
| 集会名称 | 2013年国際骨代謝学会・日本骨代謝学会第2回合同国際会議(神戸国際会議場ほか) |
| URL | |
| 主催者団体名 | |
| URL | |
| 氏名 |
| 開催日 | 2013年5月23日(木)~25日(土) |
| 開催地 | |
| 集会名称 | 日本薬剤学会第28年会(愛知県産業労働センター ウインクあいち) |
| URL | |
| 主催者団体名 | |
| URL | |
| 氏名 |
| 開催日 | 2013年5月23日(木)~24日(金) |
| 開催地 | |
| 集会名称 | 第30回希土類討論会(北九州国際会議場) |
| URL | |
| 主催者団体名 | |
| URL | |
| 氏名 |
| 開催日 | 2013年5月22日(水) |
| 開催地 | |
| 集会名称 | 食品ハイドロコロイドセミナー2013(東京海洋大学白鷹館多目的スペース) |
| URL | |
| 主催者団体名 | |
| URL | |
| 氏名 |
| 開催日 | 2013年4月26日(金) |
| 開催地 | |
| 集会名称 | 酵素工学研究会第69回講演会(名古屋大学野依記念学術交流館) |
| URL | |
| 主催者団体名 | |
| URL | |
| 氏名 |
| 開催日 | 2013年4月20日(土) |
| 開催地 | |
| 集会名称 | 第3回名城大学薬学部研究・大学活性化を目的とした学生フォーラム(名城大学キャンパス) |
| URL | |
| 主催者団体名 | |
| URL | |
| 氏名 |
| 開催日 | 2013年9月11日(水)~13日(金) |
| 開催地 | 横浜市 (パシフィコ横浜) |
| URL | http://www.aeplan.co.jp/jbs2013/ |
| 大会会頭 | 宮園 浩平(東京大学大学院医学系研究科) |
 栃木県のとある古書店で一冊の本をやっと見つけた。僕が産まれた年に刊行された「生化学の諸切片」という教科書である*。実はこの副題に僕は心がひかれた。副題は 「硫酸、硝酸、核酸」である。 私は学生のころから今に至るまで硫酸、特に糖鎖の硫酸基修飾を対象に研究を行っている。硫酸が核酸より順位が上ということは当時硫酸が核酸よりも重要だと認識されていたのではないかと勝手に思い込んでしまった。今でも硫酸の潜在機能に心を躍らせ研究を進めている。 糖鎖の構造は何万通りにもなり非常に複雑なのかもしれないが難解なものほどヒトをよく引きつける。シンプルな実験系とごくわずかな図で硫酸化糖鎖の生物機能の説明ができるようになりたい。上記教科書の刊行から40年たった今どんな教科書が書けるか楽しみである。 私は大学院生時代に新規な糖鎖硫酸転移酵素遺伝子の発見とクローニングおよび命名に携わることができた。その後当該遺伝子ノックアウトマウスの作製および解析に従事し、多くの糖鎖硫酸化の生物機能を明らかにすることができた。中でも、 細胞表面セレクチンリガンド糖鎖の合成におけるGlcNAc6位硫酸化反応の重要性およびそのリンパ球の血管内皮細胞上におけるローリング速度の規定をあきらかにできたことは非常にうれしかった。切磋琢磨している同分野の研究者の方々に自分が受入れられた気がして至上の喜びであった。私は幸運に恵まれている。恩師、また多くの同僚に支えられた研究環境に恵まれている。硫酸研究における生化学と生物学の重要性を教示くださった村松喬先生、門松健治先生、神奈木玲児先生、スティーブン ローゼン先生、 硫酸研究の出会いをくださった羽渕脩躬先生、木全弘治先生にこの場をお借りして感謝申し上げます。
栃木県のとある古書店で一冊の本をやっと見つけた。僕が産まれた年に刊行された「生化学の諸切片」という教科書である*。実はこの副題に僕は心がひかれた。副題は 「硫酸、硝酸、核酸」である。 私は学生のころから今に至るまで硫酸、特に糖鎖の硫酸基修飾を対象に研究を行っている。硫酸が核酸より順位が上ということは当時硫酸が核酸よりも重要だと認識されていたのではないかと勝手に思い込んでしまった。今でも硫酸の潜在機能に心を躍らせ研究を進めている。 糖鎖の構造は何万通りにもなり非常に複雑なのかもしれないが難解なものほどヒトをよく引きつける。シンプルな実験系とごくわずかな図で硫酸化糖鎖の生物機能の説明ができるようになりたい。上記教科書の刊行から40年たった今どんな教科書が書けるか楽しみである。 私は大学院生時代に新規な糖鎖硫酸転移酵素遺伝子の発見とクローニングおよび命名に携わることができた。その後当該遺伝子ノックアウトマウスの作製および解析に従事し、多くの糖鎖硫酸化の生物機能を明らかにすることができた。中でも、 細胞表面セレクチンリガンド糖鎖の合成におけるGlcNAc6位硫酸化反応の重要性およびそのリンパ球の血管内皮細胞上におけるローリング速度の規定をあきらかにできたことは非常にうれしかった。切磋琢磨している同分野の研究者の方々に自分が受入れられた気がして至上の喜びであった。私は幸運に恵まれている。恩師、また多くの同僚に支えられた研究環境に恵まれている。硫酸研究における生化学と生物学の重要性を教示くださった村松喬先生、門松健治先生、神奈木玲児先生、スティーブン ローゼン先生、 硫酸研究の出会いをくださった羽渕脩躬先生、木全弘治先生にこの場をお借りして感謝申し上げます。
*講談社サイエンティフィックより刊行。編者および執筆者に鈴木旺先生、江上不二夫先生ら蒼々たる先生が名をつらねている。
(写真:マチュピチュ遺跡は普段住んでいる場所からはまったく見えないが視点を変えると一望できる。今後も硫酸という視点で私は研究を遂行していきたい。)
 私は現在、細胞の形態や運動性を制御する分子メカニズムについて、Rhoファミリーの低分子量G蛋白質を介したシグナル伝達を中心に研究を行っています。私が“研究”ということに携わるようになったのは大学の学部四回生の始めに行われた研究室への配属からですが、配属された当時は生理活性物質であるプロスタグランジンの受容体の研究をしていました。やはり最初は右も左もわからず、先生や大学院生の先輩方の指導の下、とにかく実験は一生懸命やっていたことは覚えています。ある時、当時神経細胞のモデル細胞としてよく用いられていたPC12細胞を使って、あるプロスタグランジン受容体サブタイプを特異的リガンドで刺激したところ、PC12細胞の神経突起が短時間でみるみる退縮していくことを偶然見つけました。この時からRhoファミリーG蛋白質の研究に魅力を感じて現在に至っているのですが、やはり当時研究室の主流とは全く違う分野に踏み込むことに私自身少しためらいもありました。それでもここまで研究を進めることが出来たのは、全く違う分野にも関わらず私の研究に対して真剣に向き合って頂き、その後現在に至るまであらゆる場面で非常に適格なアドバイスをして頂いた指導者の存在が大きかったと思います。今振り返ってみると、実際に手を動かして実験を行い、その結果を直接目にするのは自分自身であり、その積み重ねの中で、ある時おもしろい現象を見つけることが出来るかどうかはやはり自分自身に寄るところが大きいと思います。それに加えて、価値ある研究成果を残すためには、適切な方向へと研究を導いて頂く良き指導者に巡り会うことが必要であることも強く感じており、今後は私自身が良き指導者としてこれから研究者を目指す人たちに対して少しでも力になれるよう努力していきたいと思います。
私は現在、細胞の形態や運動性を制御する分子メカニズムについて、Rhoファミリーの低分子量G蛋白質を介したシグナル伝達を中心に研究を行っています。私が“研究”ということに携わるようになったのは大学の学部四回生の始めに行われた研究室への配属からですが、配属された当時は生理活性物質であるプロスタグランジンの受容体の研究をしていました。やはり最初は右も左もわからず、先生や大学院生の先輩方の指導の下、とにかく実験は一生懸命やっていたことは覚えています。ある時、当時神経細胞のモデル細胞としてよく用いられていたPC12細胞を使って、あるプロスタグランジン受容体サブタイプを特異的リガンドで刺激したところ、PC12細胞の神経突起が短時間でみるみる退縮していくことを偶然見つけました。この時からRhoファミリーG蛋白質の研究に魅力を感じて現在に至っているのですが、やはり当時研究室の主流とは全く違う分野に踏み込むことに私自身少しためらいもありました。それでもここまで研究を進めることが出来たのは、全く違う分野にも関わらず私の研究に対して真剣に向き合って頂き、その後現在に至るまであらゆる場面で非常に適格なアドバイスをして頂いた指導者の存在が大きかったと思います。今振り返ってみると、実際に手を動かして実験を行い、その結果を直接目にするのは自分自身であり、その積み重ねの中で、ある時おもしろい現象を見つけることが出来るかどうかはやはり自分自身に寄るところが大きいと思います。それに加えて、価値ある研究成果を残すためには、適切な方向へと研究を導いて頂く良き指導者に巡り会うことが必要であることも強く感じており、今後は私自身が良き指導者としてこれから研究者を目指す人たちに対して少しでも力になれるよう努力していきたいと思います。
最後に、やはりいい仕事をしていい論文を発表すると、自ずと同じ分野を研究する知り合いが増え、そのような人たちとさらに親睦を深めることで、中には本当に信頼し合える人とのつながりを築くこともできました。自分にとって貴重な財産となっている人とのつながりをこれからも大事にしながら、今後もさらにいい研究をしてこのつながりを広げていきたいと思います。