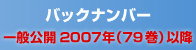会長だより
会長便り第14号:To make women visible
日本生化学会会員のみなさん、
今号では男女共同参画の取組みについて考えます。
平成11年に「男女共同参画社会基本法」が定められ、内閣府の「男女共同参画局」が中心となり、さまざまな場面で“女性の参加比率を大きくする運動”が展開されています。本会においても「男女共同参画推進委員会」が活動しています。男女共同参画は社会構造に性の多様性を求めることを意味しており、生物学的な性が二つに分類されてきた経緯から“男女”となっているに過ぎません。さらに、真の意味で社会全般における多様性あるいは機会均等を実現させるのであれば、性別だけでなく人種・国籍・宗教・心身のハンディキャップの有無などへの適用も必要です。
多様性達成度の検証では“当該社会構造の母集団における割合を反映した数値”が目標にされることが多いです。しかし、このやり方は抽出時の判定基準となる適性や能力が母集団間で同程度の場合には成り立ちますが、どちらかの母集団で適性や能力の高い人の割合が高ければ抽出された時の割合も違ってくるでしょう。適性や能力が客観的に判定できる場面ではどちらの母集団も納得する抽出が可能ですが、主観により判定が違ってくる余地がある時には不公平が生じる可能性があります。男女共同参画の取り組みでは、多くの社会構造が男性優位にある現状で起こりうる不公平の解消のため、“適性や能力が同程度であれば女性を優先する”ことがしばしば行われます。
学術集会に関わる男女共同参画活動の目的のひとつに、シンポジウムなどでの世話人(オーガナイザー)や講演者における女性の比率を高めることがあります。海外の集会では、女性の割合が一定以上でないと集会そのものの開催が許可されない場合があります。この目的を達成させるために、世話人や招待講演者の候補となる女性研究者を集めたリストを活用することが提案されています(Invisible woman? Trends Cell Biol. 25:437)。この記事では、米国細胞生物学会が手がける「Women in Cell Biology」という活動の一環で作成されたリスト(http://ascb.org/wicb-committee/)が紹介されています。他にも、米国National Science Foundationの支援を受けて設立された合成生物学分野の活動が提供する女性招待講演者候補のリスト(http://www.synberc.org/diversity/speaker-suggesions)や、さまざまな研究分野での“優秀な女性研究者”を集めたAcademiaNet(http://www.academia-net.org)およびRaise Project(http://www.raiseproject.org)というのも紹介されています。さらに、招待を受けた女性研究者のとるべき行動として、まず可能なかぎり受諾するよう努め、どうしてもそれがかなわない時には代わりの女性研究者を推薦するように、と書かれています。
本会の状況に目を向けてみます。女性会員の割合は22%ほどであり、研究領域や地域(支部)の間で大きな違いはありません。その一方、年齢が低いほど女性比率が高くなる傾向が顕著であり、正規ポジションに就く女性が少ないことを反映しているのかもしれません。今月には本会の執行部構成が新しくなりますが、女性の割合は代議員で10%(全171名)・理事で13%(全24名)です。多分野に渡る54の学会が加盟する「男女共同参画学協会連絡会」という組織があります。本会はこれから1年間にわたりその組織の幹事学会を務めることになっており、男女共同参画を含めた“多様性を受け入れるための活動”が強化されそうです。7月のScience誌で女性研究者の割合を増大させるための“数値目標”の有効性について内閣府の「総合科学技術・イノベーション会議」において検証がなされると紹介されており(7月10日号349:127)、性の多様性だけでもその実現のための方策とあるべき姿が見えてこないのが現実です。
男女共同参画は男と女が同じ役割を担うことを必ずしも意味しておらず、男女で一致する部分と違う部分を理解したうえで、それぞれの科学への携わり方を考えるべきではないでしょうか。おりしも、同性パートナーや夫婦別姓が話題となっています。私は、これまでのように“男女比の数値”だけでなく、もっといろんな観点から性の多様性をとらえることが、どちらの集団にとっても好ましい男女共同参画活動の有り様を導くことにつながると思います。
私の会長としての任期は今月で満了するので「会長便り」は今号で終了します。2年間お読みくださりありがとうございました。
2015年11月
中西義信
会長便り第13号:Lip-sync conference
日本生化学会会員のみなさん、
今号では学術集会のあり方について考えます。
最近のEMBO Reports誌に「Lip sync conferences」というタイトルの記事が掲載されました(EMBO Rep. 16:1051, 2015)。‘lip sync’とは、いわゆる‘くちパク’を意味します。この記事の著者は、“学術集会に招待される講演者の顔ぶれはいつも同じで、しかも講演内容の大部分は以前の繰返しである”と指摘しています。さらに、“招待講演者の多くは自分の発表が終わるとすぐに帰ってしまう”とも言っています。また、口頭発表における討論のやり方の改善を提案しています。
「いつも同じ顔ぶれ」は私も時々感じることがあります。ただ、毎年同じ集会に参加するわけではない人にとっては、論文でしか名前を知らない人の講演を聴く機会が得られるという良さはありますね。「発表内容に新しいデータが少ない」と感じている方はいるのではないでしょうか。招待講演に限らず、まだジャーナルに掲載されていないデータを発表することが理想なのですが、内容の全てが未発表の講演にはなかなかお目にかかれません。いろんな事情があるでしょうが、“未発表データを話すと他の研究者に横取りされてしまう”ことを恐れる研究者が多いのは事実でしょう。なお、学会発表もジャーナルでの論文発表と同様に、同一内容を同じ集会で繰返して発表すると‘研究成果の重複発表’とみなされて不正扱いになる可能性があります(本会の「倫理規程」を参照してください)。「招待講演者がすぐに帰ってしまう」もよく目にすることですが、これは集会の主催者の考え方や講演者の姿勢に帰する問題ですね。
情報技術の発達した今の時代では、発表と討論のやり方にも改善の余地があると思います。口頭発表での映写の際に、発表者が自分のPCを演壇に運ぶシーンをまだ見かけますし、少しましでも映写ファイルを保存したメモリースティックを備え付けPCに差し込むくらいがせいぜいです。使うデータを集会のサーバーに提出しておき、発表時にPCに取込むことで片付きそうに思います。ポスター発表においても、印刷したポスターを大きな筒に入れて会場まで運びボードに貼付けるのではなく、あらかじめ登録したポスター形式の発表データを会場で映写すれば事足りるしょう。既にこのようなやり方を取り入れている学会もありますが、経費がかさむこととデータ漏洩の防止措置が課題のようです。一方、討論の形態について、前出の記事では質問を‘ツイート’で行うことが提案されています。「聴衆が小型端末を使い無記名で送信した質問がスクリーンに映し出され、座長が内容ごとにそれらをまとめて講演者に答えてもらう」というやり方です。二つの利点が挙げられており、ひとつは座長がまとめることで統合的な質問にできること、もうひとつは質問者が特定されないので率直な質問が発せられることです。ただし、この討論形式では、複数の質問をうまくまとめる能力が座長に求められます。このように考えてくると、研究成果の発表と討論のためだけだったら会員が一堂に会する必要はないのではという意見も出てきそうです。そうはいっても、face-to-faceの議論でのみ得られることの大切さは、みなが理解するところでしょう。
学術集会にとどまることなく、これを開催する学会自身のあり方も変わるべきかもしれません。かつては、多くの学会がその研究領域での科研費の審査員を抱えていて、学会に所属することが研究費獲得において重要な意味を持つ時代もありました。また、学会が刊行するジャーナルに論文を掲載する際の割引が会員特典のひとつであることは、今もよく見かけます。学会の役員などを務めることは、大学教員や研究者にとっては所属組織における評価のポイントを稼ぐことにつながります。他方、学生にとっては、学会の学術集会で発表することが奨学金の受領、奨学金の返還免除、就職活動などにおいて有利に働きます。しかし、このような‘直接には学問に関連しない’目的のみで会員が存在することは、学会の本来のあり方とは違うはずです。学会の活動が、会員の研究活動の発展に資するようでなければなりません。本会を含めた各学会には、今こそ、年次学術集会のあり方を含めた新しい組織の姿を提示することが求められています。
2015年10月
中西義信
会長便り第12号:URA
日本生化学会会員のみなさん、
今号では、研究機関における二つの新しい職業、ラボマネジャーとURA、について考えます。
ラボマネジャー(Laboratory Manager)
海外の大学の研究室でラボマネジャーということばをよく耳にします。実験材料の分与を依頼した時などに“ラボマネジャーのSteveが対応するから”のように言われ、お手伝い的な雑用係と思っている人もいるのではないでしょうか。しかし実際はそうではなく、ASBMB Today誌の2013年10月号に掲載された‘How to become a good lab manager’という記事では、“ラボマネジャーはPIであるラボヘッドとは別に研究室のきりもりに責任を持つ正式な職”と紹介されています。米国の就職支援ウェブサイトAcademic Investにはこの職業の説明文があり、“ラボマネジャーは、研究室(所)がうまく機能するために、室員のスケジュール管理・研究室の安全性の確保・研究のための機器や材料の管理・予算の管理・ラボヘッドと研究員との関係調整、などの業務を担当する”と書かれています。
従来は、研究者自身やベテラン技術者がラボマネジャーに求められる仕事の多くをこなしてきました。ラボマネジャーの登場で、彼らはこれらの業務から解放され、研究費獲得と研究遂行に集中できるようになったという訳です。ラボマネジャーは個々の研究室で採用される場合が多いですが、大学や研究機関が募集することもあるようです。
URA(University Research Administrator)
みなさんの所属機関でこのようによばれる人を見かけませんか?これまで教育職員と事務職員の二つの職階だけが存在した大学に、URAという‘第三の職’が出現しました。URAは教育職員と事務職員の間に位置付けられ、研究にまつわるさまざまな仕事を効率的に進める役割を担います。海外ではサイエンスマネジャー(Science Manager)ともよばれます。私が勤務する大学では、既存部局とは独立した組織に所属するURAが、研究費の申請から獲得後の手続き・研究成果の国内外メディアへの発信・産学連携と知的財産に関係する手続きなどを支援しています(http://www.o-fsi.kanazawa-u.ac.jp/about/section/ura/)。
“研究の立案や実施よりもその調整や支援業務の方が好き”や“政府組織などで科学政策の立案に関わるよりも研究現場に近い所で仕事をしたい”のように思う人は以前からいたはずです。URA職はそのような人たちの活躍の場と言えるでしょう。しかし、この職が各大学に定着してうまく機能するためには、解決しておかねばならない課題が残っています。すなわち、URAの業務が大学間で統一されて第三の職として正式に定められるとともに、給与体系・キャリアパス・評価システムを整える必要があります。URAを含めたResearch Administrator(RA)に関するさまざまな事項を検討する組織「RA協議会」が2015年3月に設立され、9月初めに最初の集会が開かれました。今後の活動に期待したいと思います。
ラボマネジャーの職に就くには当該分野の学士は必要ですが博士の学位はなくてもよく、米国での給与は5〜7万米ドルだそうです(Academic Invest)。既に日本でも、いくつかの大学や研究所ではラボマネジャーの募集が行われています。一方、URA職には博士の学位が求められる場合が多く、給与は職位や経験などにより決まるようです。大学での職として定着しつつあるURAはさらに拡大してゆくでしょう。そして、近いうちに両職とも大学や研究機関に欠かせない正規職として確立するはずです。ラボマネジャーやURAが本会会員の希望する大学・公的研究機関や企業での職業になる時代はもうすぐそこに来ています。
2015年9月
中西義信
会長便り第11号:Thinking in Japanese
日本生化学会会員のみなさん、
今号では研究における言語について考えます。
昨年末に、会員のみなさんから“大会のあり方”についてウェブ上で意見をいただきました。使用言語に関する設問への回答では「発表と討論での言語は自由にする」が大多数であり、自由記述では“日本語で発表して日本語で討論する”との意見が大半を占めていました。ほぼすべての会員は英文で論文を書いているはずであり、この調査結果は“学会発表は日本語・論文発表は英語”を意味しています。日本語での学会発表を支持する理由として、“英語でまともな討論のできる会員は少ない”や“大学院生などの若い会員には英語での発表は敷居が高い”など、英語力の稚拙さを挙げる人が多くみられました。それでは、私たちの英会話力さえ上がれば、英語で発表と討論を行う大会にできるのでしょうか。そんなに単純なことではないかもしれません。
みなさんは論文原稿を作る時に、どのように思考していますか。私は、まず書きたいことの要点を日本語で考えて和文で箇条書きにし、次にそれに沿って(たぶん)あまり頭を使わずに英文を作ってゆきます。私にとって、論文の内容を初めから英語で考えることは難しく、論理的な思考では母国語である日本語が優勢です。
このように“やっぱり日本人は日本語で思考するんだな”と思っていたところ、新聞の書評で「日本語の科学が世界を変える」という本(松尾義之著、筑摩選書、2015年1月)を知りました。松尾氏は東京農工大学工学部卒で「日経サイエンス」の副編集長を務めた方です。この本で松尾氏は、日本での科学は日本語で育まれてきた、科学に関する外国語の単語や記述を日本語へ翻訳する過程で付加価値が生まれる、オリジナリティーに乏しい内容の英語論文を書くくらいなら概念を説く論文を日本語で発信しよう、などといった主張を展開しています。
文部科学省は、“国際化”を“グローバル化”と言い換え、大学での教育の英語化を進めようとしています。教員には英語での授業、学生には英語検定試験受験や在学中の海外留学などが義務化されてゆきます。採用時にTOEICなどの点数で応募者を足切りする企業も増えてきました。私たち大学教員は、“英語を使えないと国内企業にさえ就職できない”と学生を指導する一方、“英語ではまともな議論にならない”と学会では日本語での発表と討論を続けています。公式な場で日本人が英語を使うと、“本田選手は記者団の質問に英語で応じた”のように、“英語で”という但し書きが付け加えられます。日本人にとっての英語、特に英会話は、黒船来航のトラウマかもしれません。
英語で発表と討論を行うとまともな議論にならないのは、英会話ができないからではなく、日本人の頭脳は日本語で考える構造になっているからではないでしょうか。私たちは、英語を使う能力と英語で思考する能力を区別して扱わないと、英語は使えるが論理的思考のできない学生ばかりを作ってしまいかねません。
そうは言っても、国際的な学術集会では英語での発表と討論をやらねばなりません。ITC技術の進歩が「ウェアラブル瞬時通訳装置」を登場させてくれるまでは、英語で思考する力を養うべく頭の構造を変える努力を続ける必要があります。
2015年3月
中西義信
会長便り第10号:Author’s Responsibility
日本生化学会会員のみなさん、
今号では論文著者の責任について考えます。
近頃は、論文あたりの著者がひと昔前よりも多い傾向にあります。これは研究の完成に異分野間の共同研究が必要になったことや、解析対象となるデータの規模が大きくなったことが要因に挙げられますが、これとは別に“不適切な著者”の増加が指摘されています(「会長便り第5号」でも少し触れました)。ほぼすべてのジャーナルでは著者としての責任と義務を定めており、さらに各著者の貢献を具体的に論文原稿に記述すること(Contribution Statementなどとよばれます)が求められる場合もあります。私たちのJBでは、投稿時に「Authors’ Responsibility and Conflict of Interest Form」の提出が必要であり、すべての著者がその研究の企画、実施、あるいはデータの解析と解釈、ならびに論文原稿の作成に貢献したことを示す書類に署名することを求めています。“不適切な著者”とはこのような責任と義務を実際には果たしていない著者のことを表し、英文では“guest, honorary, or ghost authorship”のようによばれます。それでは、なぜ“不適切な著者”がいるのでしょうか。それは、その存在が“本来の著者”を益する場合があるためであろうと推測されます。たとえば、著名な研究者が共著者に名を連ねると論文原稿がジャーナルに採択されやすくなる、“本来の著者”が研究費獲得や人事(採用、昇進など)において“大物”の共著者に便宜をはかってもらえる、あるいは学生や部下が著者となる論文を作ることで指導者としての責任を果たせる、などといった動機があるのかもしれません。つまり、“本来の著者”が意図的に“不適切な著者”を作っていることになります。
一方、不適切とまではゆかなくても、先ほどとは別の理由で本来の責任と義務を果たしているとは言えない共著者がうまれることがあり、その多くは共同研究の実施に適切さを欠くために起こります(EMBO Rep. 15:914)。共同研究者の間では「知識・技術面の適切性(epistemic integrity)」と「倫理面の適切性(moral integrity)」の両方が満たされることを確認することが必要であるとされています。しかし、教育・研究面の上下関係の存在や専門分野の隔たりのために、実際にはこれが実行されていない例があるようです。このような場合には、一部の著者による研究不正があったとしても、他の著者がそれに気づかずに研究成果が公表されてしまう可能性があります。過去に話題にのぼった研究不正の多くでは、不正の実行に直接的には関わっていない共同研究者は責任を問われていません。これは、不正が特定個人により実行され、専門性の異なる他の共同研究者はそれに関わることができなかったとみなされるからです。つまり、不正への責任が及ばないことで、共同研究が適切に実施されなかったことが図らずも露呈しているのです。EMBO Rep.誌の記事では、共同研究者が導きだす成果が“何か変だ”とか“完全過ぎる”と感じられる場合にはより慎重にその信憑性を確認するべきだとする一方で、“自己の課題設定や作業仮説が証明されることの誘惑”がその確認を妨げる場合の多いことも指摘しています。
不適切かどうかにはかかわらず、著者が多くなる背景として著者数が論文の価値や本来の著者へのクレジットに影響しないことがあります(かつてProc. Natl. Acad. Sci. USA誌が論文あたりの著者数の上限を定めていた時期があるように記憶します)。著者数の大小は論文の内容の良し悪しに関係ないかもしれませんが、bibliometricsへの影響を指摘する声があります(EMBO Rep. 15:1104)。これは、著者の多い論文が引用されると多数の研究者のh index(「会長便り第2号」を参照ください)が上昇するために、著者の少ない論文との間に不公平が生じるというものです。この問題を解消するための方策として、ひとつの論文の被引用で生じるクレジットを一定にしてそれを著者間で按分することや、著者の貢献度に応じて按分比率を変えることも提案されています。
さらには、上記のような“不適切な著者”がいるくらいなら論文原稿の審査員を共著者に加える方がまし、とまで言う人もいます(EMBO Rep. 15:1106)。“真の著者だけがいる論文”にするためには、私たち自身が著者としての責任と義務を果たすように努めるしかありません。
2015年1月
中西義信
会長便り第9号:Reviewer Experiment
日本生化学会会員のみなさん、
ジャーナルに投稿された論文原稿の査読(Peer Review:会長便り第7号)について、問題点を挙げてその解決策を考えます。
会員の多くが経験していると思いますが、審査員の要求に応じて原稿を改訂するには多大な労力と長い時間を費やすことが必要です。これはおもに、審査員が過大な追加実験を求めるからであり、その程度はJournal Impact Factorの数値に比例する傾向にあるようです。また、苦労の末にようやく再投稿しても、さらなる改訂が求められたり、掲載を断られてしまうこともあります。著者を困らせる追加実験は「それは必要ないだろう」と「それは無理だよ」というものにわかれ、原稿に記述された研究の結論にさほど影響しないものが含まれる場合も少なくありません。このような追加実験は、審査員が論文自体を判定するのではなく記述された研究を発展させようと思いつくと考えられ、よく“Reviewer Experiment”とよばれます(Science 321:36; Nature 472:391)。さらに、“Supplementary Information”の制度が束のような追加実験の要求に拍車をかけています。Reviewer Experimentの問題点は、重要な発見の公知が遅れることに加え、科学者がジャーナルの求めるデータを出すことをめざすために独自の発想に基づく研究が乏しくなってしまうことにあります。さらには、著者がReviewer Experimentの回避のために実験結果を発展的に考察することをやめてしまい、論文の質が低下してゆくと指摘する人もいます(EMBO Rep. 15:818)。
論文原稿の査読はジャーナルへの掲載の可否を判定するために行われますが、審査員が著者とやりとりする過程で原稿の質が高まるという効果もうみだされます。上記の問題は、本来ならば編集委員による調整で回避されるはずですが、“各審査員の意見を精査して妥当なものだけを著者に通知する”のような交通整理をやってくれる編集委員にお目にかかるのはまれです。さらに、Peer Reviewなので審査員も著者として論文原稿を投稿することがあるはずなのですが、いったん審査にあたると逆の立場になる場合のあることを忘れてReviewer Experimentを要求してしまうようです。
この現状を問題視するジャーナルが「改善策」を講じており(eLife 2:e00799; EMBO Rep. 15:817)、要点は次のようなものです。
1. 編集委員が選別した採択の可能性の高い原稿を審査員による査読に供する。
2. 採択された論文について審査過程(審査員と著者の間のやりとり)を公開する。
3. 編集委員が審査員の意見を統合した判定結果を作成して著者に通知する。
さらに、審査員間で判定のための話し合いを行う、審査員意見の適切性を検討する制度を設ける、追加実験は適宜な時間・手法・労力で可能なものにする、詳細な査読に供した論文は原則として採択する、ことなども検討されているようです。EMBO J.誌やeLife誌などは既にこれらの多くを実行しています。また、このような手順を導入すると編集委員の仕事量が増大するため、他の多くのジャーナルとは異なり(会長便り第8号)、eLife誌では編集委員に報酬を与えるようにしています。
私たちのJBでも、論文原稿査読の方針や手順について考える必要があるかもしれません。
2014年10月
中西義信
会長便り第8号:Rubriq Scorecard
日本生化学会会員のみなさん、
ジャーナルに投稿された論文原稿のpeer review(会長便り第7号)に関する課題について、今号では審査員にかかる負担を取り上げます。
論文審査を引き受けると、2週間ほどの間に原稿を査読してジャーナル編集部にその結果を報告しなければなりません。ひとつの原稿の査読には数時間ほどが費やされ、その間は本来の業務はできません。しかも、出版社はジャーナルを発行することで利益を得ているにもかかわらず、審査員には賃金が支払われません。多くの場合、編集委員長や編集委員も無料奉仕しています。
昨年のASBMBの会報誌に‘Reviewing is a business transaction’と題する記事が載りました(ASBMB Today, August 2013, page 16)。執筆者はトロント大学の教授で、投稿論文の審査は報酬をともなうべきだと主張しています。この人は年に300件ほどの審査にあたっていて、それに費やす時間を計算すると週の1~2日を占めることになるそうです。それなら審査を断ればよいのではとなりますが、“自分の論文の審査を最適の人が断った時のことを考えると”なかなかそうはできません。彼は、原稿あたり100~200ドルの報酬が相応で(市場経済的には400ドルに値するという分析もあります)、これを出版社または著者が負担するのがよいと言っています。著者が出版社に支払う論文掲載料(会長便り第3号)を考えると、この額はけっして法外ではありません。
私は通常のpeer reviewでの審査員が報酬を得る例を知りませんが、ジャーナルとは独立にpeer reviewを行って審査員に賃金を与える企業があります(Nature 494:1621)。Rubriq(http://www.rubriq.com/)という名称のこの組織は、“論文審査に要する時間と費用を軽減させる”ことを目的として2013年に設立されました。著者は、ジャーナルに投稿する前の原稿をRubriqに送って審査を受けます。料金は500~650ドルの範囲で、適用される作業項目の数によって異なります。基本作業は3名の審査員による査読で、Rubriq Scorecardとよばれる判定結果が2週間以内に著者に届きます。査読の形式はジャーナルが行う審査とほぼ同様で、原稿改訂の案も提示されます。650ドルのコースでは、基本作業に加えて「盗用」の有無が調べられ、さらに複数の投稿先ジャーナルの候補が「採択確率」の数値とともに示されます。なお、審査員は登録制で、学位を持ち大学や研究機関での常勤であれば誰でも応募できるようです。報酬は1件につき100ドルです。著者は、ジャーナルへ論文原稿を投稿する時にRubriq Scorecardを添付します。ジャーナル側が独自のpeer reviewを行う際にRubriqでの審査結果を参考にすることで、迅速に採否決定が導かれるという仕組みです。さらに、客観的に採択の可能性が高いとされたジャーナルが投稿先になる場合が多いため、投稿から採択までの時間が短縮されることが期待されます。
Rubriqによる「投稿前査読」がどのくらい利用され、論文採択にどの程度の効果を与えているかはまだ公表されていません。無報酬の仕事は責任感の欠落をまねく可能性があるため、私はpeer review業務に対する賃金は歓迎すべきことだと思います。
次号でも引き続きpeer reviewを扱い、その公平性について考えます。
2014年7月
中西義信
会長便り第7号:Peer Review
日本生化学会会員のみなさん、
今号と次号とで、ジャーナルに投稿された論文原稿の審査にまつわる課題について考えます。今号では、その前提である論文審査過程の基本的な流れを確認します。
論文原稿がジャーナルの編集部(editorial office)に届くと、編集委員長(editor-in-chief)が審査統括にあたる編集委員(editor)を研究の専門領域などに基づいて割り振ります。多くのジャーナルでは、まず編集委員長と編集委員とで原稿を詳細な審査(in-depth review)に供するかどうかを判定します。それに値しないとされれば、この時点で掲載が拒否されます。詳細な審査に移行する時には、ジャーナルの常任審査員会(editorial board)のメンバーやそれ以外の研究者から編集委員が2~3名の審査員(reviewer)を選びます。審査員は当該論文の内容に通じた研究者である場合が多いことから、この審査形態はピアレビュー(peer review、専門家仲間による審査)とよばれます。
論文審査の依頼は、担当の編集委員から電子メールなどで届けられます。依頼文には論文原稿の要約部分が添えられています。依頼を断る時には、その理由を示し(研究領域が異なり適切な審査ができない、著者は共同研究者であり公平性が保たれない、など)、多くの場合、代わりの審査員候補を推薦します。審査員を引き受けると、審査用のウェブサイトから原稿全体をダウンロードできるようになり、それを受け取って査読を行います。審査期間は2週間ほどに設定されているジャーナルが多いですが、より短く10日以内としているものもあります。ウェブサイト上で行う審査結果の報告では、著者に通知される論文内容の評価に加えて、採択の可否や論文体裁の適切さについての意見が求められる場合が多く、編集委員への伝言もできます。「論文内容の評価」(reviewer’s comments to authors)では実験結果の不足や解釈の誤りなどを伝えます。「採択の可否」の判定には採択(accept)・改訂(revision)・却下(reject)のいずれかを提示し、さらに改訂が軽微(minor)と大幅(major)に分けられているジャーナルもあります。審査の最終判定は編集委員に委ねられますが、実際には“参考意見”を求められる場合が多いです。「編集委員への伝言」(confidential comments to editor)には、“すぐれた研究成果なのですぐに採択すべき”や“研究課題が当該ジャーナルにそぐわない”などの意見を書きます。これらに加えて、原稿の長さ、文章のわかりやすさ、統計処理の適切さ、採択された場合に宣伝に値するか、などへの意見を述べます。審査員は匿名が原則ですが、著者に氏名を伝えるかどうかを選べるジャーナルもあります。
編集委員は審査員の意見に基づいて最終判定を下し、各審査員による「論文内容の評価」とともに責任著者(corresponding author)に通知します。責任著者はほかの著者に結果を知らせ、採択判定以外の時には対応を考えます。初回の審査では、“追加実験の結果を盛り込んで原稿を改訂すればもう一度審査する”という判定が多く見られます。そして、これに沿って書き直された“改訂稿”(revised manuscript)が、審査員意見への著者の返答(authors’ response to reviewers’ comments)とともに再投稿されます。著者はこの時に、審査員評価への反論(rebuttal)を編集委員に伝えることもできます。原稿修正の期間はジャーナルごとに定められていますが(多くは3ヶ月ほど)、適切な理由があると認められればそれを越えることが許されます。改訂稿は、原則として同じ審査員により二度目の査読を受けます。この作業を繰返して(改訂回数が定められているジャーナルもあります)、論文がジャーナルに掲載されるかどうかが決まります。
次号ではピアレビューにおける問題点について考えます。
2014年6月
中西義信
会長便り第6号:Reproducibility Initiative
日本生化学会会員のみなさん、
今号では、学術論文にかかわる不正とはどんなことを意味するのか、そしてそれをなくすことが可能なのかを考えます。
学術論文での科学上の不正(scientific misconduct, scientific fraud)は、ねつ造(fabrication)、改ざん(falsification)、盗用(plagiarism)の3種類に分類されます。許容範囲を越えた“データの加工”と“既存記述の再使用”は、それぞれ改ざんと盗用にあたります。なお、自分のデータや記述を複数の論文で使うことは自己盗用(self-plagiarism)とされます。論文のねつ造については、研究自体が完全な作り話だった「Mark Spector氏によるATPaseの実験」が有名です。1980年代の初めに、“ATPaseの活性化に関わるタンパク質リン酸化カスケード”を報じる複数の論文がごく短期間のうちにJ. Biol. Chem.に掲載されました。当時大学院生であった私は、その論旨とデータの明快さに感心したことを記憶します。
大学を含む研究機関に対して、論文不正を防ぐ手段を講じるよう国が強く指導しています。そのひとつが、“コピー&ペースト”の存在を調べるコンピューターアプリケーションの導入です。これを使うと、調査対象論文に占める既存記述の割合がたちどころに算出されます。しかし、その数値に基づいて「不正」の有無を判定することは難しく、効果のほどはまだわかりません。なお、私たちのJBでも投稿された論文原稿の審査にあたりこの作業がすでに実施されています。国からの不正防止の指導は教育面にも及び、Collaborative Institutional Training Initiative(CITI)などの教育プログラムを使う授業の実施が推奨されています。CITIは医療倫理を学ぶ教材を開発し提供する機関として2000年に米国で組織されたもので、その後に対象が研究全般に広げられました。2013年にはCITI Japan Program(http://www.jusmec.org/defaultjapan.asp?language=japanese)が設立され、この組織が提供するeラーニング教材を使って研究倫理の授業を行う大学が増えています。
学術論文には、上記の「不正」とは別に“実験結果の再現性”という課題があります。ある期間に発表された生物医学分野の論文を調べてみると、結果が再現されたものは1割ほどに過ぎなかったという報告があります。論文として公にされる実験結果は、著者によって再現性が確認されているはずです。しかし、ほとんどの場合、それは著者が所属する研究室内で繰返し得られた結果であることを意味し、必ずしも他の研究者による再現実験が実施されている訳ではありません。真の意味での再現性を保証するためには、投稿前に第三者が追試実験を行う必要があります。これを実現するために、Reproducibility Initiative(http://validation.scienceexchange.com/#/reproducibility-initiative)が2012年に米国で設立されています(Science 337:1031)。この組織は、論文原稿の著者から追試実験が依頼されると、その実施を“advisory board”メンバーの所属研究機関に委託します。実験結果が再現されれば「認定証」が与えられ、さらに創業当時にはほぼ無条件でPLoS ONEに掲載されることになっていました(現在は少し事情が異なるようです)。もちろんこれには費用がかかり、当初では、その研究全体に要した額の1割を著者が支払うと説明されていました。この仕組みがうまく働けば再現性の問題は解決されるのでしょうが、費用だけでなく、研究成果が漏洩される可能性や発表時期が遅れてしまうという課題もあります。今のところ、このような煩雑なステップを投稿条件に盛り込むジャーナルは出てきていないようです。
実験科学の学術論文が成り立つ最低要件は、「適切な実験手法」、「結果の再現性」、「正当な結果提示」、及び「適切な結果分析」です。論文原稿を審査する過程でも、これらのすべてが満たされていることを判定するのは容易ではありません。ましてや、“偽りの記述”を見抜くのは至難の業です。さらに、上述した対策にも限界があるでしょう。学術論文の不正防止は、研究を実施して論文を発表する者自身の倫理感を高めることにつきると思われます。
次号ではジャーナルに投稿された論文原稿の審査について考えます。
2014年5月
中西義信
会長便り第5号:Sham journal
日本生化学会会員のみなさん、
今号と次号では学術論文にまつわる種々の問題を取り上げます。
ジャーナルに投稿した論文が採択されて刊行された後でも、著者はその内容の一部を変更することができます。ただしこれは、その変更が論文の結論に影響しない場合に限られます。文字や数値の修正、図表の微細な変更、著者情報の訂正、などがその例です。著者がジャーナル編集部に依頼して承認されれば、変更内容が“erratum”や“corrigendum”としてジャーナルに掲載されます。一方、結論が変わってしまうような大きな誤りが判明した時には論文内容の変更では済まず、多くの場合は論文そのものが取り下げられます(retraction)。撤回された論文は存在しなかったものとされ、その論文に基づいて授与された学位があればそれも取り消されることになります。2013年には、世界中で発表された約100万篇の論文のうち500篇ほどが撤回されたそうです(Retraction Watchというウェブサイトには論文の撤回や訂正に関する記事が載っています)。論文の撤回はそのジャーナルで公知され、それに至った経緯などが説明されます。撤回された論文の著者は信用を失うことになりますが、誠実に対処することでそれを最小限に留めることができるようです(Nature 507:389)。なお、論文撤回の原因がなんらかの科学的不正による場合は、著者は所属機関や学協会から制裁を受けることもあります。ちなみに、変更や撤回の記事には対象論文が引用されるため、そのたびに当該ジャーナルのImpact Factor値が大きくなります。
また一方、近年では学術論文にまつわる構造的な不正が問題視されており、そのいくつかを紹介します。まず論文著者の売買です。昨年11月に、論文著者の売買を行う企業(組織)があると報じられました(China’s publication bazaar. Science 342:1035)。その仕組みとは、ジャーナルに採択された論文原稿を買い取り、筆頭著者や責任著者の「権利」を売るというものです。「料金」は、co-first authorとco-corresponding authorのどちらかひとつで15,000 USドル、両方では「割引」が適用されるらしく25,000 USドルほどだそうです。このようにして、研究にまったく携わっていない新たな「著者」が追加された論文が発表されるのです。次の例は、偽のジャーナルウェブサイトの存在です。昨年3月に、実在するジャーナル名を語る架空サイトから投稿/掲載料をだまし取られる事件が報じられています(Sham journals scam authors. Nature 495:421)。利用されたジャーナルはウェブサイトを持っておらず、‘料金を払ったのに論文がまだ掲載されていない’という編集長への問合せが多発して発覚に至ったそうです。最後に紹介するのは、営利目的第一のオープンアクセスジャーナルです。今年の1月に、ウェブサイトScholarly Open Accessに“List of predatory publishers”というタイトルの記事が載りました。そこには、投稿/掲載料を払い込ませることを主たる目的とするとみられる出版社やジャーナルの名称が記されています。その数は477にのぼり、年々増加しているそうです。この記事の執筆者は、これらのジャーナルについて論文原稿の投稿、編集委員等への就任、論文の審査などを行わないようにとよびかけています。
このように、学術論文の存在自体を揺るがしかねないさまざまな問題が存在しています。次号では“論文における不正をなくする手だて”を考えます。
2014年4月
中西義信
会長便り第4号:Negative data論文
日本生化学会会員のみなさん、
前号に引き続き、学術雑誌(ジャーナル)の形態の移り変わりについて考えます。ここでは、新しい編集方針を持つ三種類のジャーナルを取り上げます。
最初は、“publish first, judge later”をうたうPLoS ONEについてです。これは前号で紹介したPLOS journalsのひとつで、2007年に創刊された電子版のみのopen accessジャーナルです。このジャーナルの特徴は投稿された論文原稿の採択基準(Publication Criteria)にあり、審査員は「研究成果の重要性」は考慮せずに「方法論の正当性」のみを判定します。つまり、標準的な手法で実験操作と結果の解析が行われ、妥当な解釈に基づいた結論が記述されてさえいれば、論文原稿が採択されます。そして、論文内容の評価は掲載後に読者によってくだされるのです。ウェブ上で論文ファイルを開くと上部に「Comments」のバナーがあり、そこからコメント欄に入って意見を書き込むことができます。創刊時の編集者は“このジャーナルでは論文掲載は研究の終点ではなくディスカッションの開始点である”と述べています。掲載後の論文の内容や意義がウェブ上で盛んに議論されるのであれば、このような編集方針のジャーナルは存在価値を持つのかもしれません。
二つ目は、ネガティブデータを記述した論文を掲載するジャーナルの登場です。ここでのネガティブデータとは、“適正に実施された実験において作業仮説が否定されることが判明した”場合などの結果を指します。ネガティブデータの公表は他の研究者による不必要な実験を省くとともに定説の覆しに寄与することにあるという考え方のもとに、複数のジャーナルが創刊されています。それらにはJournal of Negative Results in Biomedicine、The All-Results Journals: Biol、Journal of Pharmaceutical Negative Resultsなど生化学関連分野のものが含まれ、編集方針に基づけば前出のPLoS ONEもこの仲間に入ります。
最後は、投稿前の論文原稿を載せるジャーナルです(serverと称されているのでジャーナルに含めるのは適切でないかもしれません)。物理学の分野に、1991年に開設されたarXiv(アーカイブ)というopen accessのサーバーがあります。これは「preprint server」とよばれ、研究者は作成した論文原稿をまずこのサーバーに登録(掲示)します。すると、その内容についてウェブ上で読者による議論が行われ、著者は出された意見などに基づいて原稿を改訂してゆきます。ある物理学者のウェブサイトには、“まずarXivに登録してその後にジャーナルに投稿することが一般的”と書かれています。多くの出版社はarXivでの論文原稿の掲示を「出版」とはみなさいため、著者は議論を踏まえて最終化された原稿をジャーナルへ投稿することができるのです。arXivには毎月5000にのぼる原稿が新しく登録されているそうです。物理学の分野では、解決されるべき課題が限定されており、かつ純粋に研究内容だけが評価の対象とされるため、このような研究成果公表のやり方が可能なのかもしれません。そして、生命科学分野でも同じような仕組みとして、Cold Spring Harbor Laboratoryが運営するbioRxiv(バイオアーカイブ)が2013年11月に登場しました。このサーバーに登録された論文原稿はまだ多くないようですが、将来はこれがarXivのような役割を担い、生命科学の分野でも論文原稿の「bioRxivへの登録→ウェブ上での議論→改訂→一般ジャーナルへの投稿」が通常のプロセスになるかもしれません。
このようなジャーナル形態の移り変わりを俯瞰すると、研究成果公表のあり方が“実験データをウェブサーバーにデポジット(登録)する”方向に進んでいるように感じられます。今のところは、新しい形態(編集方針)のジャーナルもデータに基づく結論を著者が主張する形式をとっています。しかし将来は、“個々の研究者はデータを登録するだけ”で、別の人たちがそのデータを多面的かつ広い視野から解釈して結論が導かれるようになるかもしれません。そこにはもはや、インパクトファクターはおろか論文の著者すらも存在しないでしょう。個々の研究者の評価はどうなるのかという問題はありますが、科学と技術の発展は人類の繁栄のためにあるのだとすれば、これこそが理想的なジャーナルの姿なのかもしれません。
次号では、ジャーナルでの論文掲載にまつわる問題に触れます。
2014年3月
中西義信
(追記)
本学会のウェブサイトにさまざまな変化が生じつつあります。この「会長便り」の掲載に続き、「JB編集委員長より」が載り、今月初めには生化学誌の電子版が掲載されました。また、トップページの左側にある「企業広告」のバナーにお気づきでしょうか(学会財政健全化対策のひとつです)?そして近々、「学会掲示板(仮称)」が設けられます。これは、会員間で意見のやりとりを行うもので、学会執行部への会員からの要望なども書き込むことができます。自由な意見交換も行われますが、“本学会のDORAへの署名(会長便り第1号を参照)”や“大会運営のありかた”など、話題を限って討論することにも利用したいと思っています。どうかご期待ください。
会長便り第3号:Open-accessジャーナル
日本生化学会会員のみなさん、
今回と次回とで、私たちが研究成果を公表する主要な場である学術雑誌(ジャーナル)のありようについて考えたいと思います。
生命科学の分野では、ほぼすべてのジャーナルが電子化されて久しく、冊子体の発行をやめて電子版のみになったものも多く見られます。生化学系ジャーナルの老舗Journal of Biological Chemistryの冊子体もなくなりました。“電子ジャーナル”は迅速かつ効率的な検索を可能とし、自分が望む内容の論文を瞬く間に探し出すことができるのはもちろん、自分の研究分野に近い論文の出版を電子メールで知らせてくれるサービスもあります(Science 343:14)。論文をチェックする方法はこの20年ほどの間に、「雑誌をぱらぱらめくる」から「PCで最新号の目次を見る」→「最新号をキーワード検索する」となり、さらに「“論文見つかりアラート”がスマートフォンの端末に届く」のように変化しました。もはや“少し離れた領域の論文を読んでアイデアがひらめく”ことは望むべくもありません。論文の発表と閲覧の電子化は、さまざまな手間や時間・費用を軽減する効果を与えたものの、マイナス面も生み出していることを頭におく必要があるかもしれません。
ジャーナル購読の形態にも大きな変化が起こりました。個別に発行されていたジャーナルを大手の出版社が傘下に収める動きが広まり、多種類・多数のジャーナルを持つ“メガ出版社”が誕生しました。ElsevierやSpringerがその代表であり、私たちのJournal of Biochemistryも現在はOxford University Pressが刊行するジャーナルのひとつになっています。メガ出版社は“パッケージ商品”を販売します。これは、複数のジャーナルをグループ化して一括販売する仕組みで、そこに含まれるジャーナルの個別購読料の総額よりも低いパッケージ価格が設定されています。パッケージにはあまり利用されないジャーナルも含まれる場合が多いのですが、購読契約したジャーナルの数を競う大学の図書館はこぞってこのパッケージを買い、その結果としてジャーナル購読に充てる費用が大きく膨らみました(私の勤務先では年に数億円がこれに投じられています)。年々増大する購読料に困った大学は図書館が連携する組織などを通じて対策を講じようとしており、広まりつつある大学での研究成果リポジトリー(大学職員が発表した論文の最終原稿などを公開する制度)はその例と言えるでしょう。米国NIHは納税者のために、自身が提供した研究費により得られた成果を記述する論文を無料公開して欲しいと要望していますが、大手の出版社がこれに応じる気配はないようです。
一方で、open-accessジャーナルとよばれる、購読料を支払わなくても論文を読むことができる電子ジャーナルも存在します。2002年に登場したBioMed Central(BMC)は、幅広い学問領域をカバーするopen-accessジャーナル群を刊行しています。翌2003年にはPublic Library of ScienceがPLoS Biologyを創刊し、その後に他の学問領域のジャーナルが加わりPLOS Journalsとなりました。2012年には、Randy Schekman氏を編集長としてeLifeが鳴りもの入りで創刊されました。eLifeの前にはProceedings of the National Academy of Sciences of U. S. A.の編集長であったSchekman氏は、2013年にNovel Prize Physiology or Medicineを受賞し、昨年12月にはNature、Science、Cellの3つのジャーナルを取りあげて“私は商業主義にはしるこの3誌にはもう論文原稿を投稿しない”と発言して話題になりました。それでは、なぜopen-accessジャーナルの論文は購読手続きなしに読めるのでしょうか。それは、読者ではなく著者が閲覧に要する代金を負っているからです。著者がジャーナルに支払う費用はかなり高額で、BMCとPLOSでは2,000 USドル前後を要します。さらに、Elsevier傘下のCell Pressが最近に創刊したopen-accessジャーナルCell Reportsの掲載料は5,000 USドルに設定されています。eLifeは米国のHoward Hughes Medical Institute、ドイツのMax Planck Society及び英国のWellcome Trustのスポンサーシップを受けており、掲載料は取らないとされています。全体がopen accessでなくても掲載された論文のいくつかが無料公開になっているジャーナルも増えています。著者は採択された論文をopen accessにするかどうかをジャーナル側からたずねられ、これを選択した場合の費用もおおむね高額です。たとえば、Journal of Biochemistryでの無料公開の費用(Open Access charge)は3,000 USドルです。Open accessが広まれば大学などの研究機関の経済的な負担は軽くなりますが、出版社が懐を痛めるわけではなく、論文を投稿する研究者への負荷が大きくなる仕組みができあがっているのです。
研究費申請の際には論文投稿に要する費用を計上することができます。今のやり方でのopen accessが普及すると、その項目に書き込む数字が大きくなり、研究費のうちの実験に充てられる金額が縮小してしまいます。私は、会員間で意見を交換し、この状態の改善をめざした学会としての働きかけの方向を探りたいと思っています。
次号では、各ジャーナルが掲載する論文の多様化に触れます。
2014年2月
中西義信
会長便り第2号:h indexによる論文業績の評価
日本生化学会会員のみなさん、
前号(Dec 2013)で紹介したように、DORAの宣言は“Journal Impact Factor(IF)値を使って個々の論文を評価することをやめよう”というものです。論文の優劣は内容の評価に基づいて判定されるべきですが、内容の理解が難しい場合や数値化判定が必要な時があります。そのような場面ではIF値を使わずにどうやって論文を評価したらよいでしょうか。DORAを支持する人たちもその方法を模索中のようです(EMBO Rep. 14:947)。
論文の評価をそれが掲載された学術雑誌(ジャーナル)のIF値に基づいて行うことが適切でないとする意見の根拠は、“高いIF値を持つジャーナルにも被引用頻度の低い論文が多く含まれる”ことです。何度も引用されることが優れた論文の証しだとすると、被引用回数を論文ごとに比べれば優劣が判明することになり、その数値はThomson Reuters社のWeb of Scienceを利用すると得られます。
その考えに基づくと、個々の研究者の論文業績は全発表論文の被引用回数の総和で評価できることになります。しかし、“ほとんどの論文は引用されていないが極端に被引用回数の多い論文が少しだけある”時に、その業績をどう評価できるでしょうか。例を挙げて考えてみましょう。ともに5編の論文を持つA氏とB氏を比較するとします。A氏の論文の被引用回数は115、2、1、1、1、一方のB氏では15、15、10、10、10です。被引用回数の総和はそれぞれ120と60であり、A氏がはるかに優勢です。しかし、A氏では1つの論文がたくさん引用されているために総数が大きいのに対し、B氏は総数ではA氏に劣るもののどの論文も10回以上引用されて一定の評価を受けているといえます。どちらの業績が優れているとみるかは意見の分かれるところでしょう。これを解決する手法が、米国のJ. E. Hirsch氏によって2005年に考案されています(Proc. Natl. Acad. Sci. USA 102:16569)。Hirsch氏が提案する「h index(エイチインデックス)」とは、“N回以上引用された論文をN編以上持つ時に、その研究者のh indexをNとする”というものです。前出のA氏とB氏のh indexはそれぞれ1と5に算定され、h indexに基づく評価ではB氏の業績の方が優れていることになります。ノーベル物理学賞の受賞者(2005年までの20年間)のh indexの平均値は40ほどだそうで、生化学などの生命科学分野ではh index値25~30が“優れた”論文業績の目安とされることがあります。近年ではh indexが使われる場面が増えており、これを教員の研究能力判定の指標のひとつにする大学もあるようです。
しかし、h indexによる論文業績の評価法も万全ではありません。まず、被引用回数は積算値なので公開後の期間の長い論文の方が有利です。また、総説や実験手法を記述する原著論文の被引用頻度は一般にこれら以外の論文よりも高い傾向にあります。さらに、内容が同レベルであっても専門領域が違えば論文の被引用頻度に差が生じるようです。こうなると、さまざまな補正をしなければ適切な数値は求まらないことになり、もはやHirsch氏オリジナルのh indexではなくなってしまいそうです。私は、被引用などの数値ではなく内容を見てくれ、と言い続けようと思います。
次号では、多様化が進むジャーナルの形態を考えます。
2014年1月
中西義信
会長便り第1号:DORAによる論文評価標準の提言
日本生化学会会員のみなさん、
電子メールでお知らせしたように、これから毎月、私から会員のみなさんに宛てたメッセージ「会長便り」をウェブサイト上に掲載します。みなさんの研究やキャリアパスに役立つ情報を発信することを目的に、私が気になる世の中の出来事を記述します。
最初の数回は研究論文に関する話題を取り上げ、第一回目はSan Francisco Declaration on Research Assessment(DORA)による論文評価のやり方の提言を紹介します。
日々の実験で得られる研究成果は、学術雑誌(ジャーナル)上の論文として公表されます。その内容がすばらしければ、メディアで報道されたり別のジャーナルで紹介されたりして評価され、時には執筆者が讃えられます。しかし、論文の内容が優れているかどうかの判定は読む人によって異なるでしょう。研究成果の正しい評価はたいへん難しい課題です。
優れた内容の論文だけを掲載するジャーナルがあれば事は簡単ですが、そのようなものは存在しません。一方で、‘top-tier journal’とか‘high-impact journal’とよばれるジャーナルは存在し、Cell誌、Nature誌、及びScience誌がそれにあたることになっています。それらのジャーナルに論文が掲載されることで、ポジションを得たり研究費を獲得できたりすることが実際にあるようです(The Golden Club in Nature 502:291)。みなさんご存知のように、これらのジャーナルは高いJournal Impact Factor(IF)値を持ちます。IFは、Institute for Scientific Information社(現、Thomson Reuters社)を興したEugene Garfield氏によって1950年代に考案されました(「科学を計る–ガーフィールドとインパクトファクター」、窪田輝蔵著、インターメディカル、1996年)。以前よりIFの利用法はさまざまに議論されてきましたが、最近になって大きな動きがありました。それがDORAです。
http://www.ascb.org/dora/DORAの宣言は、“個人/機関/地域の研究成果の評価はその内容に基づいてなされるべきであり、IFの誤った使い方に依ってはならない”というものです。全文の和訳もウェブサイトに掲示されているので、ぜひ読んでみてください。当初の署名人には一部のtop-tier journalの編集長、トップランクの研究機関、及び多くのノーベル賞受賞者が含まれており、今でもその数は増えつつあります。そこにはCell Structures and Functions誌(細胞生物学会)とGenes to Cells誌(分子生物学会)の編集長の名前もありますが、私たちのJournal of Biochemistryはまだ加わっていません。これについては学会としての対応を含めて今後に検討される予定です。
次回は、IF値を使わずに論文や研究者の評価をどうやって数値化できるのかを考えます。
2013年12月
中西義信
バックナンバー 2014年-2015年
第1号 : DORAによる論文評価標準の提言
第2号 : h indexによる論文業績の評価
第3号 : Open-accessジャーナル
第4号 : Negative data論文
第5号 : Sham journal
第6号 : Reproducibility Initiative
第7号 : Peer Review
第8号 : Rubriq Scorecard
第9号 : Reviewer Experiment
第10号: Author’s Responsibility
第11号: Thinking in Japanese
第12号: URA
第13号: Lip-sync conference
第14号: To make women visible